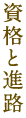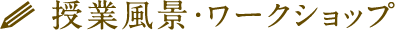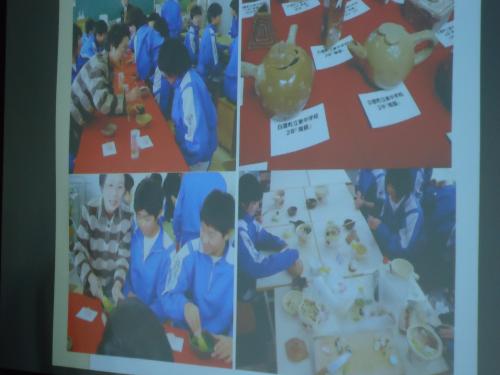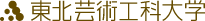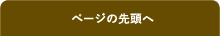「美術科教育法4」特別講師 須田一成先生の講義
今年度の授業もラストに近づいてきました。あっという間ですね。
「美術科教育法4」での特別講師の先生の授業をご紹介します。
今回の特別講師は、須田一成先生です。先生は現在山形県内の中学校で強弁をとっています。
先生の授業では、「こどもたちが考えること」、「多様な表現が生まれる授業内容であること」を大切にし、学校内に留まらない、様々な実践のお話ししていただきました。
山形に来る以前は、神奈川県川崎市で教員をされていたそうです。その頃の授業では、コンピューターを活用したポスターやCMの作成、多様な素材を活用した時計作りなど、技術などの他分野との連携もいえるような教材内容でした。
生徒が作った作品のメッセージを見て、思わず微笑んでしまいます。
特徴的なのは、グループをつくり、生徒同士がアイディアを出し合い、技術を持ち寄り、ものをつくりあげていることです。このような学習方法は、協同学習とよばれ、先生が教壇に立ち一方的に教えるのではなく、生徒同士が学びあう関係をつくりだすことを特徴にしています。
先生が山形で教壇にたってからは、授業を基盤として、生徒と地域を結ぶ取組を行っているように感じました。
白鷹町の地域の陶芸家の方から指導をしていただき、制作したお茶碗でお茶会を開催。地域の方を招いてお茶をたててもらい、生徒との交流の機会をつくりだしています。また、白鷹町で生産されている深山和紙の職人さんを取材し、生徒に紹介する導入を行っていました。制作したランプシェードは、地域のお祭りで展示され、地域の方の目を楽しませるオブジェとなっていました。
美術が生活から離れたところにあるのではなく、私たちの生活の近くにあること。生徒同士がアイディアを出し合い、学びあうことを通して、地域の課題を解決していく力になること。先生の授業にはそんなメッセージが含まれているのを感じました。
パワーポイントでは、授業をビデオ撮影したものが多く使用されていました。記録をとることの重要性も感じました。
学生たちは、先生の様々な「学びのデザイン」を見て、どんな思ったのでしょうか?