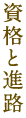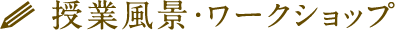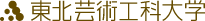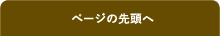大石田交流事業 本番1週間前!
こんにちは。8月から行っている大石田町の小学生へ向けたワークショップの準備もいよいよ大詰めになってきました。これまで、何度も試作を行ったり、遊ぶスペースとつくるスペースが混同しないようにと、会場デザインを考えてきました。
17日には、これまで試作した内容と、全体のスケジュールを当日参加メンバーと共有する時間を設けました。
この活動で一番大切なことは、「交流」を生み出すことです。
ひとりひとりが活動を通して、名前を覚えたり、楽しかったことを共有したりできること。以前、大石田で小学校の先生たちとの打ち合わせに参加したさいに、お話しがありました。ただし、交流には衝突もついてきます。今回活動を行う、小学2年生は自分の考えと他の人の考の違いを調整することが、まだ得意ではありません。今回も、3つの小学校の子どもたちが1つのグループをつくり、4つの屋台を回ります。どの順番で作るか、どのくらい時間をかけるのか、グループ同士で話をしながら進めていかなければなりません。衝突をさけて活動を進めるためには、大人が手助けをしてあげる必要もあります。活動をしながら、子どもたちの様子をどこまでみていられるかが勝負どころです!
さて、そんな話をした後に、活動の準備にとりかかりました。この日のために、教職担当者は巨大段ボールを電気屋さんから大量にもらってきました!さらには細かいパーツを作るために段ボールを回収していきます。
コアメンバーがそれぞれのグループの中心になって、作業を進めていきます。昨年度の段ボールタワーとは違い、63名分の子どもたちが活動しやすいように、おおよその素材を学生が準備します。すごい作業量になるのですが、この手間暇を惜しんでは活動はうまくいきません。
うちわグループでは、「うちわの持ち手になる割ばしをさしておいたほうがいい」など、本番をイメージしてさらに変化を重ねるところもあります。
また来週にも準備を行います。最後のひとぶんばりです。