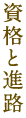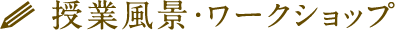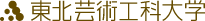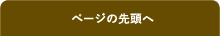授業風景をのぞいてみよう(美術科教育法4)
こんにちは。「授業風景をのぞいてみよう」シリーズです。
美術科教育法4では、前回の吉田先生に引き続き、特別講師の先生をお呼びして講義をしていただきました。
今回は、山形県で高校教員をされている菅原温子先生です。
授業の冒頭では、持参された作品や写真を使いながら、教員として、作家として、そして母親としてどのように「仕事」をしてきたのか語ってくださいました。
多忙な日々のなかで、子どもをおぶった状態で彫刻作品を制作していたというエピソードもあり、衝撃を受けました。
現在、芸工大では女性の割合がとても多いです。
学生は、大学卒業後に、仕事と生活のバランスを取りながら、自分の制作を続けていくことについて考えるきっかけをもらえたのではないでしょうか。
授業風景をのぞいてみよう(美術科教育法4)
池田教授の「美術科教育法4」の授業では、特別講師をお呼びして授業をしています。10月22日は、山形県教育センター指導主事をされている吉田先生にお越しいただきました。
私がおじゃましたときは「授業実践の紹介と模擬事業」として、「デザイン」を題材にお話しされていました。「デザイン」という言葉はよく耳にしますが、どんな意味を持つものなのかを語れる人は少ないかもしれません。
先生は、たくさんの製品を用意して、使い方を紹介しながら、「デザイン」の意味や魅力について伝えていきます。
授業の本質を生徒に理解してもらうために、言葉で丁寧に説明しながら授業を進めること。
実物にふれながら「こんなものがつくれるんだ」という『ワクワク』を感じてもらうこと。
吉田先生が授業で大切にしていることに触れることができたと思います。
また、教員をされながら、作家として活動されていることも紹介してくださいました。
授業を受けている学生は3年生。来年行う教育実習や進路と重ね合わせながら授業を受けることができたのではないでしょうか。
大石田交流事業 本番!!!
9月26日(木)は、大石田での活動の本番でした。活動タイトルは、『段ボールまつり~つくって・遊んで・楽しもう~』。この活動では、大石田町の3つの小学校の子どもたちの交流を生み出すことをねらいとしています。
少し緊張している学生たちに、「学校という現場そのものを体験してほしい」と、片桐教授が活動のポイントを投げかけていました。
学校についてからは、すごいスピードで動いていきます。
今回は、4人1組のグループで4つの遊びの活動を周ることができます。最後に、それぞれの活動で制作した作品を使って遊ぶという流れになっていました。
開始当初、子どもたちはざわついていましたが、2つめの活動に移ったあたりから集中して制作をしていました。活動ではペンやボンドなど使う道具が共通していたため、活動をこなしていくたびに子どもたちは道具の使い方が上手になっていました。
また、子どもたちは徐々にグループ活動を意識するようになって、はぐれてしまった子を呼びに行ったりと主体的に活動する様子がみられました。
これは、活動の中にグループで協力して遊ぶ場面を設けたことや、子どもたちが自ら順序を選択するという要素を盛り込んだために生まれたのだと考えられます。
学生たちも、はじめは緊張していましたが、少しずつひとりひとりの子どもたちの動きに対応できるようになっていました。また、全体を把握してくれる大学院生や4年生がいたため、大きな混乱もなく順調に活動を進めることができました。
ですが、課題もあります。子どもたちはビニールテープを切ることが難しかったようです。時間の制限もあるため、ほとんど学生が作ってしまうということもありました。また、自由に活動の順序を選べるため、1つの活動に対して人数にばらつきがでて、学生の手が足りなくなるなど、その場その場で対応しなければならないことが多々ありました。これらのことは、振り返りの時間で、じっくり考えていきたいと思います。
最後にグループごとに、学生も交えて振り返りを行いました。学生と子どもたちとの距離がとても近くなっていたのが印象的でした。
この活動後も、1年生と6年生の授業見学をさせてもらいました。6年生は映像を使いながらの英語の授業で、先生たちが子どもたちを集中させるときの声のかけ方、ふるまい方を見ているだけでも勉強になります。
1日中、大石田の子どもたちとかかわった学生たち。
感想を聞いていると、学年によって子どもたちの様子がまったく違うことに驚いていた学生が多いようでした。
みんな夢中だったと思いますが、活動ではひとりひとりの子どもたちと関わりを持つために、いろんな方法でアプローチをしながら関わりを生み出してきました。
学校を出るころには、これまでなかった子どもとのかかわり方のチャンネルを獲得しているのだと思います。
学生が帰りのバスに乗り込むとき、2年生も下校の時間でした。みんな玄関から飛び出して、「また来てね~!!」と大声で叫んでいました。
本当にそれが今日のすべてだなぁと思いました。
コアメンバーのみなさん、当日メンバーのみなさん、本当にお疲れ様でした!
大石田交流事業 本番1週間前!
こんにちは。8月から行っている大石田町の小学生へ向けたワークショップの準備もいよいよ大詰めになってきました。これまで、何度も試作を行ったり、遊ぶスペースとつくるスペースが混同しないようにと、会場デザインを考えてきました。
17日には、これまで試作した内容と、全体のスケジュールを当日参加メンバーと共有する時間を設けました。
この活動で一番大切なことは、「交流」を生み出すことです。
ひとりひとりが活動を通して、名前を覚えたり、楽しかったことを共有したりできること。以前、大石田で小学校の先生たちとの打ち合わせに参加したさいに、お話しがありました。ただし、交流には衝突もついてきます。今回活動を行う、小学2年生は自分の考えと他の人の考の違いを調整することが、まだ得意ではありません。今回も、3つの小学校の子どもたちが1つのグループをつくり、4つの屋台を回ります。どの順番で作るか、どのくらい時間をかけるのか、グループ同士で話をしながら進めていかなければなりません。衝突をさけて活動を進めるためには、大人が手助けをしてあげる必要もあります。活動をしながら、子どもたちの様子をどこまでみていられるかが勝負どころです!
さて、そんな話をした後に、活動の準備にとりかかりました。この日のために、教職担当者は巨大段ボールを電気屋さんから大量にもらってきました!さらには細かいパーツを作るために段ボールを回収していきます。
コアメンバーがそれぞれのグループの中心になって、作業を進めていきます。昨年度の段ボールタワーとは違い、63名分の子どもたちが活動しやすいように、おおよその素材を学生が準備します。すごい作業量になるのですが、この手間暇を惜しんでは活動はうまくいきません。
うちわグループでは、「うちわの持ち手になる割ばしをさしておいたほうがいい」など、本番をイメージしてさらに変化を重ねるところもあります。
また来週にも準備を行います。最後のひとぶんばりです。
大石田交流会 コアメンバーでの試作!
こんにちは。教職課程では3年前から、大石田町の小学生にむけて、ワークショップを行っています。この活動は、3つの小学校の小学生の「交流」を目的にしていて、小学校から依頼を受けて行っているものです。
今年も夏休み期間をつかって、コアメンバーが話し合い&試作を行っています。
今年は、使う素材は「段ボール」。
「だがしや楽校」の考え方をもとにして、複数の遊びを準備して、子どもたちが「選ぶ」ことができるような進め方にしようと考えています。選ぶことを通して、子どもたち同士で考えて自然と会話する機会が生まれるはずです。
参加しているメンバーのアイディアがもりだくさん!
「うちわづくり」では、作ったうちわを使ってバレーをしたり。
「ゆらゆらミニ迷路」では、大きな板状の迷路をグループメンバーで転がして、遊んだり
これらの内容には、「つくる」ことでじっくりと自分と向き合って、「遊ぶ」ことで自然な会話を生み出したいというコアメンバーの想いが入っています。
これからもっと、活動内容を具体化していけるように頑張ります!
授業風景をのぞいてみよう「共通演習4~子供の学びと遊び~」
こんにちは。7月も中盤に入り、試験期間に向けて授業もどんどん進んでいます。「共通演習4~子供の学びと遊び~」では、3回目の『だがしや楽校』の試作と準備が行われていました。
今回のポスターは夏らしい素敵なもの。屋台の内容も、海やうちわなど季節を感じられるものがあります。だがしやチラシ
「もこもこ しゃぼんアート」では、不思議な泡のタワーが出来上がります。泡が消えた後にできる模様はまるでレースの模様のようです。活動そのものが面白いので、たくさんの人と一緒に遊ぶのか?個人制作にするのか?遊び方によってまったく印象が変わるので、慎重に考えます。
「ゆらゆらんど」では、様々な素材を持ち寄って、その場にいる人たちとつくるものを考えていく、これまでにない屋台です。完成形がないため、たくさんの素材を支える支柱をどのように組み立てるか考えどころです。SAの学生が、これまで自分が実践したワークショップから具体的な知恵やワザを伝授していきます。SAがいることで学びがより深まります。
準備風景を見ているだけでも、それぞれに特徴があって、こだわった内容のものであることがわかります。
この授業では、アイディアだし、話し合い、試作、実践、振り返りと様々な活動の場面があります。そこで感じたことを、きちんと言葉にして振り返り、整理してきたことで、学生たちが話し合いのポイントを把握してきているのを感じました。
そして、前回よりも荷物の整理、片付けがスピーディーに進みます!この点も進化しています!
本番当日、晴れるといいですね!
授業風景をのぞいてみよう 「教育方法」
7月3日は、鈴木先生の「教育方法」の授業風景をご紹介します。
今回の授業は、「キャリアプランニング」の授業。教職課程なのに、キャリアプランニング?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは、これまで学んできた「問題解決型学習」を利用して、人生設計を戦略的に進めながら、日々の学生生活を充実させようとするねらいがあり、いわゆる「進路指導」とは異なります。
授業プリントは真っ白です。そこに、「将来の夢」と「今の自分」を書いていきます。ここまでは、誰もがきっと行うことだと思います。 鈴木先生は、そこに「マッピング」という方法を使います。そのことで、「今の自分」や「将来の夢」の具体的な内容を意識させていきます。
その後、学生生活の中の「山場」となる活動を書いていきます。(たとえば、「就職活動」「教員採用試験」いろいろありますね。)すると「いつ」、「どんな山場」があるのかがしっかり見えてきます。
将来どんな自分になりたいのかを明確にすること、そして自分の長所をもとにして具体的な準備を考えること。このように将来の人生をイメージしながら、日々の学生生活を意図的・計画的に送ることができます。この表を作り出すことは、学生たちにとって、教職だけでなく、学生生活、就職活動などを考えるうえで貴重な材料になるはずです。
履修している学生たちは、時間をじっくり使ってプリントに記入していました。真っ白いプリントは、たくさんのキーワードでうまったでしょうか?
だがしや楽校!(総合演習4(子供の学びと遊び))の様子
前回の「総合演習4(子供の学びと遊び)」では、準備風景をお伝えしましたが、その本番の様子もご紹介します。
6月23日(日)に、山形の南公園を舞台に「だがしや楽校」が開催されました。学科も学年もバラバラの学生たちがこの日のために授業後も準備を重ねて、自分たちの遊びの屋台を持ち寄りました。とてもいい天気の中で活動が行われました!日陰のところに遊びの屋台があります。今回は5つ出店。
最初に子供たちがくいついたのは『むにむにスライム屋台』。スライムをただ作るだけでなく、ガチャガチャケースや紙コップでスライムの家を作り、持ち帰れるのがポイント。まるでスライムがペットみたいでした。
ねりけしを使って小さい物を作る『ねりねり屋台』には、こども芸大に通う親子が遊びに来てくれました。「見本もないのに小さい物を作るなんて大変なんじゃ…」と心配していましたが、子どもたちからどんどんアイディアが出てきて、いつの間にかたくさんの作品ができていました。一度はまったら動けない屋台です。
『ペタコロ音楽家』では音楽を聴きながら手作りスタンプを押していきます。五線譜にあるのは音符ではなく、自分の感じた色や形です。学生のみんなもビーズでキラキラ光る楽譜づくりを子どもたちと一緒にを楽しんでいました。
『デコモンワールド』の屋台では、作ったモンスターを飾るためのジオラマはものすごい存在感でした!ジオラマの中には、マンションもあったようでみんなが作ったモンスターたちで満室になったそうです。
最後に紹介するのは、オリジナルの匂いをつくれる『くんくんアクション屋台』屋台。小さな箱の中に好きな香を入れていきます。「これいい匂い?」「〇〇みたい!」活動を通して自然と会話が弾みます。匂いのかぎすぎで、テンションが高い!?子もいました!
全部の屋台が作りこまれていて、充実しているのを感じました。(看板もみんなこってました!)また、集中してものづくりをする屋台、音や匂いなどの感覚を楽しむ屋台などレパートリーが多様だったこともあり、大人であっても飽きずに楽しむことができるものばかりでした。
学生のみんなは、実際に活動をしてみて、自分のねらいは参加してくれた人に伝わったでしょうか?子どもたちと実際に関わって、どんな発見があったのでしょうか?
次回の活動でさらにパワーアップしそうなので、またレポートします!
授業風景をのぞいてみよう「教育方法」
こんにちは。またまた、授業風景のご紹介。
7月19日(水)の「教育方法」の授業です。この授業は「新たな教育課題や子どもの実態を踏まえながら、教育場面での実践的な指導力の基礎を培うこと」を到達目標においた授業です。
この日は、共通のテーマを持った学生が集まり、テーマの内容をA41枚にまとめて発表するというものでした。総合学習の時間をテーマにしたグループでは、総合学習の意義や特徴が図でわかりやすくまとめられていました。発表に対して先生が「評価するときはどうしたらいいか?」など具体的な質問をなげかけ、学生が答えていきます。
ご担当されている鈴木先生が行う授業の特徴は、学生が大学で受けている授業やプロジェクトを例にして、課題解決型の学習方法などの新しい学びについて教えてくれることです。学生が、大学での学びの特徴を認識することで、指導する立場にたったときに授業の材料にできるのです。自分たちの周囲の出来事を客観的に捉えることの勉強にもなりますね!
また、次回、鈴木先生の授業の様子をレポートします。お楽しみに。
授業風景「総合演習(子供の学びと遊び)」
「総合演習(子供の遊びと学び)」の授業は、これまで見てきた授業とは違い、教育に関する各自の問題意識や興味関心に合わせ、学びを深めるための選択授業です。(詳しくは「学習の流れ」の「4年間の流れ」をご覧ください。)
その中でも「総合演習(子供の遊びと学び)」では、自分たちができること、やりたいことを持ち寄り、子どもからお年寄りまで地域の人が交流する機会をつくる実践的な活動です。既存の「図工の本」などは一切使いません。アイディア出しから試作、材料の準備まですべて自分たちで考えてつくりあげます。
6月17日の授業では、6月23日(日)の本番 に向けて、準備の真っ最中でした!
練り消しを使って、小さい食べ物などをつくる屋台、作ったスライムをガチャガチャに入れて持ち帰れる屋台、いろんなの素材でモンスターを作ってジオラマの風景に飾る屋台など、ものづくりの内容が多い中で、「匂い」や「音」など感覚を楽しむ屋台もありました。
授業には、同じく教職課程を履修している4年生の学生がSA(スチューデントアシスタント)として、学生のアイディアをまとめる手助けをしてくれます。「匂い」を楽しむグループは、最後にどんなかたちで表現するかを悩んでいましたが、いろんな香りを組み合わせて、香りに名前を付けるというかたちになりました。また、「音」をテーマにした屋台では、いろんな音楽を聴いて想像する色や形に合わせて、五線譜を書いた紙にスタンプを押して遊ぶそうです。とても面白そう。
来てくれる子どもたちのことを考えながら、自分たちができること、楽しいと感じることを形にしていくことで、教育に関する関心がより高まっていきます。本番が楽しみです。チラシは「カタケンぶろぐ521」でご確認ください。http://blog.tuad.ac.jp/doing/?p=1730
カテゴリ一覧
最新記事一覧
-
2013-11-12|その他
-
2013-10-22|その他
-
2013-09-27|その他
-
2013-09-23|その他
-
2013-09-04|その他
-
2013-07-16|その他
-
2013-07-03|その他
-
2013-06-27|その他
-
2013-06-27|その他
-
2013-06-19|その他