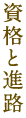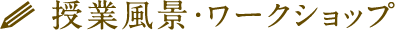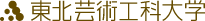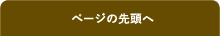授業風景をのぞいてみよう「教育方法」
こんにちは。またまた、授業風景のご紹介。
7月19日(水)の「教育方法」の授業です。この授業は「新たな教育課題や子どもの実態を踏まえながら、教育場面での実践的な指導力の基礎を培うこと」を到達目標においた授業です。
この日は、共通のテーマを持った学生が集まり、テーマの内容をA41枚にまとめて発表するというものでした。総合学習の時間をテーマにしたグループでは、総合学習の意義や特徴が図でわかりやすくまとめられていました。発表に対して先生が「評価するときはどうしたらいいか?」など具体的な質問をなげかけ、学生が答えていきます。
ご担当されている鈴木先生が行う授業の特徴は、学生が大学で受けている授業やプロジェクトを例にして、課題解決型の学習方法などの新しい学びについて教えてくれることです。学生が、大学での学びの特徴を認識することで、指導する立場にたったときに授業の材料にできるのです。自分たちの周囲の出来事を客観的に捉えることの勉強にもなりますね!
また、次回、鈴木先生の授業の様子をレポートします。お楽しみに。
授業風景「総合演習(子供の学びと遊び)」
「総合演習(子供の遊びと学び)」の授業は、これまで見てきた授業とは違い、教育に関する各自の問題意識や興味関心に合わせ、学びを深めるための選択授業です。(詳しくは「学習の流れ」の「4年間の流れ」をご覧ください。)
その中でも「総合演習(子供の遊びと学び)」では、自分たちができること、やりたいことを持ち寄り、子どもからお年寄りまで地域の人が交流する機会をつくる実践的な活動です。既存の「図工の本」などは一切使いません。アイディア出しから試作、材料の準備まですべて自分たちで考えてつくりあげます。
6月17日の授業では、6月23日(日)の本番 に向けて、準備の真っ最中でした!
練り消しを使って、小さい食べ物などをつくる屋台、作ったスライムをガチャガチャに入れて持ち帰れる屋台、いろんなの素材でモンスターを作ってジオラマの風景に飾る屋台など、ものづくりの内容が多い中で、「匂い」や「音」など感覚を楽しむ屋台もありました。
授業には、同じく教職課程を履修している4年生の学生がSA(スチューデントアシスタント)として、学生のアイディアをまとめる手助けをしてくれます。「匂い」を楽しむグループは、最後にどんなかたちで表現するかを悩んでいましたが、いろんな香りを組み合わせて、香りに名前を付けるというかたちになりました。また、「音」をテーマにした屋台では、いろんな音楽を聴いて想像する色や形に合わせて、五線譜を書いた紙にスタンプを押して遊ぶそうです。とても面白そう。
来てくれる子どもたちのことを考えながら、自分たちができること、楽しいと感じることを形にしていくことで、教育に関する関心がより高まっていきます。本番が楽しみです。チラシは「カタケンぶろぐ521」でご確認ください。http://blog.tuad.ac.jp/doing/?p=1730
授業風景をのぞいてみよう!〈美術科教育法3〉
授業風景をのぞいてみよう!第2弾です。
今度は、3年生が受講する「美術科教育法3」の授業です。担当は池田正先生です。この授業では実践的な授業の練習「模擬授業」を行います!
この日は2人の学生が、模擬授業を行っていました。授業を行うためにはまず「指導案」という授業の計画を考えます。授業の進め方、必要な道具、生徒への問いかけなど、具体的な計画書をつくります。 この指導案の作成を全員が行い、全員違う内容の模擬授業を行うそうです。
1つめは「メッセージを形にして伝えよう」という題材。 実際につくるのは、開くと仕掛けが飛び出すメッセージカードです。
教師役となった学生は、『池田先生をイメージすると出てくる言葉や物はなんですか?』と問いかけをして、生徒役の学生から意見を引き出します。 そこで出た言葉をもとにして、発想から制作までの流れを説明します。また、考えている合間には試作品を見せたりします。試作品があることで、生徒役の学生も興味津々です。
もう1つの授業では「手から感じ取れる表情(粘土を使った手の塑像)」を行いました。 自分の手やと友達の手を見比べながら、自分らしい手の特徴をさぐっていきます。 意見を出し合うことで、作品のイメージが膨らんでいきます。また、学生の机を回ってプリントの内容などを確認する「机間指導」も行っていました。
このように、授業に興味・関心を持ってもらうため、生徒の発想を引き出すために、様々な工夫が必要だということを学生たちは学んでいきます。 芸工大の学生は何度も模擬授業を行い、お互いにアドバイスしながら実習に備えているのです。実習に向けて、どんどん経験を重ねてください!
授業風景をのぞいてみよう!〈美術科教育法1〉
芸工大の教職課程は、希望する学生が選択して履修する課程です。 なので「いったいどんな勉強をするんだろう?」という疑問をお持ちの方も多いはず。 そこで、ほんの少しですが授業風景をご紹介したいと思います。
まず、ご紹介するのは「美術科教育法1」。
授業を行うのは、今年度から教職課程を担当することになった酒井清一先生です。約60名の2年生が授業を履修しています。
この授業では、学習指導要領の内容について学びます。学習指導要領とは、中学校や高校での学習のねらいや具体的な内容を示したものです。
この学習指導要領を理解することが授業づくりの第一歩になります。
段ボール祭り『大石田タワーを作ろう』
【日時】9月25日(火)
【会場】大石田南小学校 体育館
【対象】大石田小学校、大石田南小学校、大石田北小学校の小学1年生
【学生】40名
【内容】 大石田町では児童数の減少にともない、町内の3つの小学校の統合が予定されています。そのことから、大石田南小学校の校長先生から片桐教授に「交流事業」の活動内容考案の依頼があり、町内の3つの小学校の子どもたち同士が仲良くなることをねらいとしたワークショップの企画、運営を教職課程で行うこととなりました。 今回のワークショップでは、年生の学生が中心となって2つのことをねらいとして活動を考案しました。
1 身近な素材である段ボールを破いたり、ちぎったりして素材と向き合う時間をつくる
2 ひとりひとりがパーツをつくり最後に1つに組み合わせてタワーをつくることで、協同でものをつくる楽しさを感じてもらう
夏休み中には40名を超える学生が集まり、準備を行いました。
「サロン イン 滝山 夏休み寺子屋塾」に参加しました
【日時】平成24年7月25日(水)、27日(金)
【会場】滝山コミュニティセンター
【対象】福島から避難されている方(小学生、お母さん)約30名
【学生】25日:2名 27日:5名
【内容】 夏休みの期間、「福島から避難されてきた方たちが交流できる機会をつくろう」というねらいのもと、小・中学校の先生方が寺子屋塾を開催されました。そこに、学生たちもお手伝いとして参加しました。先生方の子どもたちへの接し方、会の進行を間近で見ることができ、教員を目指す学生にとっては、とても勉強になる機会となりました。
【25日の活動】
この日は、子どもたちに宿題を教えるほかに、図工の宿題のアドバイスも行いました。「宿題を教えるなんて初めて!」という学生がほとんどでしたが、一緒に考えたり、答え合わせをしていくうちに子どもたちとの距離がぐっと近くなりました。また、図工の宿題のアドバイスも子どもたちに人気で「犬の絵を描きたい」という女の子に、学生は絵のポイントを丁寧に説明していました。
【27日の活動】
この日は、身近な物をつかったものづくり活動を3つ行いました。宿題が終わった人から、ものづくり活動に参加できる仕組みです。 『まくだけまゆこさん』、『わしわし和紙』、『星ふる夜~糸で絵を描こう~』という3つの活動では、子どもたちだけでなく、お母さんやボランティアスタッフさんも一緒になって参加していました。手を動かす中で、自然と会話が生まれ会場全体が和やかな雰囲気となりました。 最後は、子どもたち全員が作品と3日間の感想を発表してくれました。 自分が作ったもの、楽しかったことを発表できて、みんな嬉しそうでした。
カテゴリ一覧
最新記事一覧
-
2013-06-27|その他
-
2013-06-19|その他
-
2013-06-18|その他
-
2013-06-18|その他
-
2013-05-20|その他
-
2013-05-20|その他