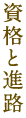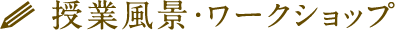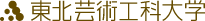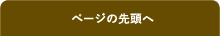「芸工大卒教員 学びの交流会」が開催されました
7月27日(土)、夏のオープンキャンパスに合わせて、
「芸工大卒教員 学びの交流会」を開催しました。

昨年度、第一回「卒業生の集い」として開催した集いを、
装いも新たに「芸工大卒教員 学びの交流会」として
全国の教育現場で働かれている卒業生にお集まりいただきました。
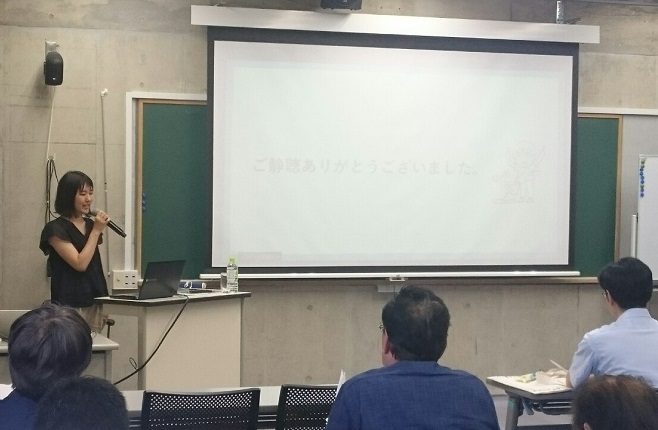
山形県内外から、小・中・高校、教育センターと、校種もさまざまに、22名もの方々がお集まりくださいました。
また、教員採用試験を受験予定の4年生も参加しました。
現場の先生方の生の声を聞ける貴重な機会ということで、緊張と意気込みいっぱいの様子です。

第一部では、各々の自己紹介でアイスブレイクした後、
現在教諭としてご活躍中の2名の卒業生から実践発表をしていただき、
様々な現場での生徒指導やクラス担当、授業実践などについての発表内容をもとに、
情報交換や意見交換が行われました。

第二部では、懐かしい顔ぶれに、お互いの悩みを相談しあったり、思い出話に花を咲かせたりと、終始和やかな時間となりました。

アンケートの結果を拝見すると、
「学生を交えたグループによる意見交換がとても良かった。」
「非常にすんなりと聞くことができる、精度の高い内容で、授業の様子を感じることができました。」
「刺激をうけました。」
など、充実した時間をお過ごしいただけたようで、一安心です。
改善点は次回につなげていきたいと思っております。
ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。
———
2019年度「芸工大卒教員 学びの交流会」 次第
≪第一部≫ 15:00~
1.開会の挨拶
2.会長の挨拶
3.アイスブレイク
4.実践発表・質疑応答
・橋爪里沙教諭(千葉県立松戸馬橋高等学校教諭)
・宮本紘子教諭(青森県立八戸工業高等学校教諭)
5.グループによる意見交換・発表
6.学長挨拶
7.閉会の挨拶
≪第二部≫懇親会 18:30~ ホテルメトロポリタン山形
教学1課 教職課程担当(2019.8.5)
教育学研究4(子供の学びと遊び):2017ワークショップ風景
7月9日(日),吉田先生担当『教育学研究4(子供の学びと遊び)』のワークショップが行われました.
教職課程を履修していても,実際に子供たちと触れあうことのできる機会はそれほど多くありません.
なので,このような機会は大変貴重なんです.
子供たちにとっても,大学生のお兄さん・お姉さんと一緒に,思いっきり工作を楽しむ機会は,なかなか貴重なのではないかなと思います.
授業を通して,学生同士でディスカッションしながら内容を考え,準備を進め,当日を迎えました.
今回のワークショップは,その名も『つくろう!あがすけワールド』
会場は山形市のお隣の町にある山辺町中央公民館.
多くの子供たちが集まってくれました!
「あがすけ」とはお調子者,目立ちたがり屋などを意味する山形弁.
子供たちはそれぞれに,自分がなりたいもの(魔法使いや勇者など)のコスチュームやアイテムを制作し,あがすけに変身です.
子供たちの自由な発想と表現力には脱帽です.
学生にとっても刺激になったのではないでしょうか.

最後は作ったコスチュームやアイテムを身につけ,お披露目です.
そして,あがすけワールドの王様から勲章と賞状が,子供たち一人ひとりに贈呈されました.
ワークショップは大成功!
学生たちもさぞかし充実した時間となったことでしょう.
このように,教職課程での学びを実践する場があると,これからの学習への姿勢が変わってくるのではないでしょうか.
大学では,補講・集中講義を終えると夏休みです.
夏休みを利用して,ボランティアやワークショップに参加してみるのもよいかもしれませんね.
実践の場は,多くの学びの機会になると思いますよ.
みなさん,健康で有意義な夏にしてください!!
教学課 教職課程担当者(2017.07.18)
中学生対象『卒展ツアー』を実施しました
教職課程履修中の学生各位
卒展期間中の2月11日に中学生を対象とした『卒展ツアー』を実施しました!
教職課程履修中の学生が中心となって進めたこの企画について紹介します.
教職課程履修中の学生が有志で集まり,ツアー全体を計画するこの『卒展ツアー』 に
今年は県内の中学校5校から美術部に所属する総勢60人の生徒さんが参加してくださいました.
卒展有志メンバーは17名.当日まで何度もミーティングを重ねてきました.
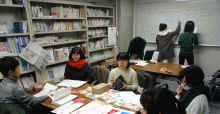
↑ 直前ミーティングの様子.
この旗は移動中グループがはぐれないように目印として昨年から考案されたもの.
今年は洋画の学生とグラフィックの学生の合作となっております.
とっても可愛くて,事務局員も感激しました!!
何度か繰り返されたミーティングでは
”中学生はどのようなことに興味を持つのか”,
”どのようなルートで回ったら限られた時間内で最大限楽しんでもらえるのか”など
卒展を楽しんでもらう,美術により興味をもってもらう,ことに加えて
安全に卒展ツアーを実施することも頭に置きつつ様々な案を出し合っていました.
いよいよ迎えた当日.
当日は今年度卒展の中で一番と言ってよいほど天気が荒れた一日でした.
中学生が無事に到着できるか心配しながらも学生たちはツアーの最終チェックを行ってくれました.
グループ分けして、見学開始!
各展示場所では先輩たちにアーティストトークを依頼し、
作品に関する説明をしていただきました.


作品を前に作者の話を聞けるアーティストトークに生徒さんも興味深々!
いろいろな質問を投げかけていました.
ツアーを終えた後は気になる作品をグループで振り返り…
代表の生徒さんに気になったポイントを発表いただきました!
最後はしっかり反省会まで開いてくれた学生メンバーでした(^^)
大学の授業では実際に生徒さんたちに関わる機会はかなり限られます.
教職課程の学びの中で得た知識,または疑問など実際の生徒さんたちにふれあい,
実践することがより学びを深めていくことにつながります.
「ボランティア、したことないな…」,「生徒さんたちに関わりたいな…」と
思っている皆さん!学内にもこんな素敵なチャンスがありますよ.
他にもさまざまな活動がありますので先生方からのアナウンスを聞き逃さないように
引き続きアンテナを張って,積極的に参加していきましょう!
参加メンバーの笑顔は活動が充実していた証ですね!!
もうすぐ4月!
春休みの現在は新年度に向けてまずはゆっくり休養!
そして,いろいろなものを観て・感じて興味を深める活動をたくさんして
また新たな表情で4月に戻ってきてくださいね♪
教職課程担当者(3.07)
教育学研究4(子供の学びと遊び)ワークショップ風景
今回は吉田先生担当の『教育学研究4』で行われたワークショップについて紹介します.
教職課程を履修していても実際に子どもたちと触れあうことのできる機会は
さほど多くありません.
今回のような子どもたちと触れ合う機会は大変貴重ですね!
参加してくれた子どもたちも,学生たちも皆いい顔しています~
さて,今回のワークショップでは
『子どもたちが学びながら遊べるワークショップ』 をテーマに
履修学生でディスカッションしながら内容を考え,準備,当日を迎えたようです.
みんなが考えたワークショップはこちら!
”変身 ファッションモンスター”

会場は山辺町中央公民館.多くの子どもたちが集まってくれた様子は以下をご覧ください!
子どもたちは各自でお面や衣装を制作.学生は子どもたちのサポート!
子どもたちの発想は素晴らしい♪
学生もいい顔してますね!
最後は作ったお面や衣装を身につけ,ファッションショー♪
みんなカラフルでかわいい.
このような感じでワークショップは大成功!
子どもたちは楽しすぎたようで,なかなか学生のもとを離れなかったようです.
帰り際名残惜しそうにずっと手を振っていた子もいたようで…
学生たちもさぞかし充実した時間となったことでしょう!
今回はワークショップでしたが,
なにかしらの形で教職課程での学びが実感できると今後の学修にも力が入りますね!
子どもと関わりたいな…と思っている学生は
授業のみならずボランティア活動への参加もお勧めです.
特にこの時期は子どもたちが夏休みなので様々なボランティアが見つかると思いますよ.
補講・集中講義を終えると夏休みです.
みなさん,健康で有意義な夏にしてください!!
教学事務室教職課程担当者(8.02)
秋にへんしん☆ファッションショー
10月26日(日)の秋晴れの良き日!
悠創の丘ワークショップが開催されました。
今回の教職チームは、秋をテーマに葉っぱを使って服をつくる「秋にへんしん☆ファッションショー」を行いました。
活動では、①親子でお互いの服を作りあう、②室内に設けた撮影コーナーで記念撮影ができる、③外を散歩する、と様々な仕掛けを用意することで親子でのコミュニケーションを大切にしたいと考えていました。

当日は3歳さんが多く、親子で一緒に服をつくる方たちが多かったです。
参加者の方は、葉っぱの色合いをよく観察して、配色を工夫して顔を作ったり、新聞紙の形を変形させて王冠のような帽子を作ったりと様々な作品の形をつくりだしていました。
服ができた子たちは、早速記念撮影コーナーに向かいます。
これは前日から会場準備をしていた、サイトウさんとカトウさんがつくりあげたもの。ここで写真をとりたくて、つられてやってきます。

ナガサキくん、コバヤシくん、男の子が先頭にたって、ぞろぞろと葉っぱ服の集団が悠創の丘を通ります。この日は紅葉を見に来たお客さんも多く「これは何をしているの?」と質問を受けることもありました。
こういった会話がきっかけで、美術の活動を知ってもらうことも大切なことだと思います。
最後に、木の下に集まって記念撮影。
参加者の方も学生も秋の空気を十分に感じられた1日だったと思います。
秋に変身☆ファッションショー~悠創の丘ワークショップ~
9月からは後期の授業が始まり、大学はにぎわっています。
さて、10月26日(日)には「悠創の丘ワークショップ」の秋の活動が開催されます。
それに合わせて、教職課程チームも話し合いを始めました。

アイディア出しをしたところ、みんな落ち葉を使いたくてウズウズしている様子。
お面や、落ち葉だるま、妖精、いろんなアイディアが出た結果、「ファッションショー」をテーマにして試作を行いました。

「原住民」のお面、落ち葉を付けた靴、新聞紙を使っているので、簡単に体の形に合わせて簡単に形をつくることができます。

テーマを設けなかったので、1時間後には、みんな個性的な姿に変身を遂げていました。

この試作をもとにして、学生たちは活動のねらいを整理していきます。
ひとりひとりが自由に制作することに重点を置くのか、親子での会話を重視するのか、大切にしたいことが分かれた際に、メリットとデメリットを出し合ったり、全体の流れを考えながら、検証していきました。

また、前回の振りかえりのさいに、WSを「集中型」(ひとりで集中してものづくりなどを行うタイプ)と「発散型」(体を動かしながらアクティブに行うタイプ)に分類。今回の活動にも当てはめて考えてみたところ、「集中型」と「発散型」を混在させた内容になりました。
たくさんの議論を経て、
落ち葉を使う事で、季節の移ろいを感じてほしい。
新聞紙などを扱うので、誰でも気軽にものづくりに参加してほしい。
そして、手を動かしながら親子の会話が生れるような活動にしていきたい。
話し合いの中でねらいを明確にしていきます。
もはや1つのプロジェクトになりそうなくらいの活動のボリュームですが、メンバーたちはいきいきと話し合っています。
これまでの悠創の丘WSの活動で学んだことを詰め込んで、また新しい活動を作っていきけるといいですね。
第3回 『だがしや楽校』活動風景
こんにちは。
今回は7月28日(日)に行われた「第3回だがしや楽校」の様子をSAのヨシダが報告します。
講義で最後となる今回のだがしや楽校は、くじ引きで班分けを行い0から企画を立てていく形で始まりました。
始めはなかなか案が出ずに悩んでいた班もありましたが、いきなり完璧な案をだそうとせずに企画のヒントになるような言葉(水、音楽、うちわetc…)を思い浮かんだ順にどんどん書き、その案を足したり引いたり練っていくことで企画が生まれていきました。
本番当日は真夏日ともいえるほど暑く、みんな汗だくになっていました。
ではその様子をのぞいてみましょう。
1つ目の屋台は「キラキラ音楽隊」です。

プラスチックコップの中にビーズやスパンコールなどをいれ、透明フィルターでふさぎ、両脇にペットボトルのキャップがぶら下がり、振るとシャカシャカと音が鳴る楽器をつくる屋台です。

中に入れる素材もプラ板の欠片があったりと、芸工大らしいものがありました。
2つ目の屋台は「オラウータンの森」です。

傘袋に水とセロハン、毛糸、モールを入れ色水のオーナメントのような飾りを作り、森を飾っていく空間系屋台です。遊びにきた子どもにバナナ型のスタンプカードを渡し、森に隠されたハンコを見つけだすという空間全体を楽しめるミニゲームもありました。
光にかざすとキラキラ光り、さらに水を使っていたので涼しい気分になれました。
学生自身がオラウータンになるというユニークな発想で屋台を盛り上げていました。
3つ目の屋台は「うちワッショイ!」です。

野菜や落ち葉、プチプチシートなどをスタンプしてカラフルなうちわをつくる屋台です。

オクラやピーマンなどたくさん野菜が用意され、子どもたちは形や色を楽しむようにスタンプしている様子でした。
4つ目の屋台は「はじけろ!花火~オレ色に染まれ~」です。

水彩絵の具液に丸めた布を付けて、白い大きな布の的に思いっきり投げて当てると絵の具が散って花火のような跡が残るという体を動かす屋台です。

的に当たった時にドンッ!と花火のような音が鳴っていたのが印象的でした。
中学生・高学年の男の子中心に歓声が上がり、盛り上がっていました。
今回の最後のだがしや楽校は前半なかなか子どもたちが集まりませんでしたが、学生同士で屋台を楽しんだり、他の屋台に遊びに行ったりいつもより視野が広がり、だがしや楽校全体の雰囲気を感じ取ることができたのではないでしょうか。
また子どもの数か少なかったので、ゆっくりのんびり子どもたちとコミュニケーションがとれていたようです。
全15回の講義が終わり、私からの感想を少し…。
だがしや楽校を通して学生たちと子どもたちの距離感は自然に近くなり、どのようにコミュニケーションをとればよいのか不安と第一回目の講義で感想を述べていた学生たちとは思えないほど成長していました。
SAとして学生が成長していく姿を近くで見て、その成長を学生に伝え、また学生から反応が返ってくるという循環を生み出したのは紛れもなく学生であり、SAはその循環のポンプ役になっていたような気がします。
教育学研究4 子どもの学びと遊びはまさに「みんなでつくる授業」でした。
おもちゃ箱の夏休み~第2回悠創館でのワークショップの活動報告~
こんにちは。
すっかりアップするのが遅くなってしまいましたが、7月27日(日)に悠創館で行った第2回目『四季を感じる創作教室』活動報告をします。
今回は有志で5名のメンバーが参加。試験週間だったにもかかわらず、短期間で内容の濃い活動をつくることができました。
その名も『おもちゃ箱の夏休み』です!
6mの長さの紙を壁に用意して、すきなポーズをしてもらい、体の形をクレヨンでかたどります。形は親子や友達同士でとってもいいですし、学生とペアになっても大丈夫です。形がひけたら、あとは体の部分にクレヨンで色をぬったり、シールをはって装飾していきます。
今回は、親子での会話、子どもと学生の会話など「コミュニケーション」を大切にして活動を行うことになりました。
前回に比べて準備物も少なかったため、学生たちに余裕があったように思います。

準備が終わると、自分のネームを作っていた学生たちがいつの間にかシールで背中に顔を描く遊びをはじめていました。

活動の前に、それぞれのブースの紹介を行います。「みんなはもう夏休みだよね。おもちゃ箱にも夏休みがあるって知ってた?」とイシモリさんが元気に説明してくれました。とても緊張しているとは思えない話かたで、子どもたちをぐっっとひきつけていました。

活動がスタートすると、「どんなことするんだろう?」と子どもたちが少しずつ近づいてきます。
体の形をとることを説明すると元気のいい男の子が、さっそくポーズを決めてくれました。
学生と子どもとの距離がぐっと近くなりますね。

準備のときに生まれた「シールをはって顔をかこう」というシンプルな活動が、小さい子にとって取り組みやすい内容になっていました。

学生が「これは何をかいたの?」と聞いてみると「これは、おばけがいて中にはいっちゃって、『ひゃっ!』って驚いているところ」と答えてくれます。

「コミュニケーション」を意識することで、学生はいつもより丁寧にこどもたちに問いかけをしていたように見えました。
子どもたちの言葉から、1つの絵にたくさんの思いがこめられていていることを知ることができます。
その豊かさには驚くばかりです。
学生が子どもたちの思いをきちんと受け止めていたので、子どもたちも「学生さんにもっと聞いてもらいたい」と思って集中力が続いていたのだと思います。
また、子どもたちだけでなく保護者の方ともじっくり会話ができていたように思います。
じっくり会話することで、関係性が生まれ、最後にお礼をいったり、片付けをして帰る子が多かったです。
今回の活動では、前回とはまた違う充実感を参加者の方に持ち帰ってもらうことが出来たのではないかと思います。
参加してくれた学生たちと、前回との活動を比較してよかった点、改善していける点を考えていきたいと思います。
悠創の丘WS 本番!
こんにちは。
遅くなってしまいましたが、6月29日に開催した「悠創の丘で芸工大生とつくろう!四季を楽しむ創作教室」の様子をご報告します!
前日の28日から会場の準備は始まっていたのですが、教職チームは活動が3つあったり、竹のドームをつくるなど準備することが沢山ありました。さらに、前日に集まれるメンバーが少なかったので、当日の朝も会場が開く8時30分に集まって準備作業を行い、何とか本番を迎えることができました。

参加者の方が少しずつ集まってきて、学生たちも緊張の様子。
前日から苦労して制作した、作品を飾るための竹の『ひみつきち』。教職チームの全てのブースで竹を使用しているので、ささくれで怪我がないように、注意事項を全員で共有します。

学生リーダーのヨネザワさんが、教職課程チームの活動内容を説明します。子どもたちの元気を引き出す挨拶がとてもうまいな~と思いました。

教職課程チームは、「竹クラフトで夏を彩ろう」というタイトルで4つの活動を行いました。
ひとつは『竹顔』。活動のスタートと同時にたくさんの親子でにぎわいました。

輪切りにした竹に、透明なテープをはって、ビーズなど好きな素材を入れて、装飾します。
まるで竹の筒の中にビーズが浮いているかのように見えます。とても涼しげですね~。

細かくカットした竹のパーツと糸を使って、竹で音が出る風鈴を作ります。
糸を竹にぐるぐる巻きにして、つるす部分をグル―ガンで固定します。グル―ガンはやけどの危険性がありますが、学生たちが子どもたちに使い方の注意点を説明していたので、子どもたちにとっては新しい道具の使い方を学ぶ機会になっていたと思います。

3つめは『竹ペンたて』
半分にカットした竹に糸を巻きつけることでペンにすることができます。親子で真剣に糸を巻いている姿が見られました。

全てのブースで糸を使っていたので、穴に糸を通したり、結んだりと、子どもたちにとって作業的に難しい部分がありました。その点については、子どもたちの視点にたって活動を考える点が不足していたといえます。
しかし、そういった難しいところは学生がフォローしていたので、この「不足点」を逆手にとって(?)、子どもたちとの距離を縮めているように感じました。(本人たちは無我夢中だと思いますが)

これらのブースで作った作品を、竹で作ったドーム『ひみつきち』に飾ることができます。
『ひみつきち』は、とても目立っていて教職チームの看板になっていました。
実際には作品を飾るというよりは、『ひみつきち』の中に入って寝転がって風景を眺める子や記念写真を撮る親子が多かったです。

子どもたちにとって2時間という時間は長いのですが、飽きる人はほとんどいなくて、親子でじっくりものづくりを行っている様子がとても印象的でした。

改善できるところはまだまだたくさんありますが、授業外の時間に有志で集まったメンバーで、これほどの規模の活動を実施できたのは本当にすごいことだと思います。
次回の本番は、7月26日です。
また頑張りましょう!
悠創の丘ワークショップ 本番準備!
こんにちは。悠創の丘WS本番まで、あと1週間。
募集していた45名の定員はすでにうまったそうです。やる気がわいてきますね。
さて、昨日は本番に向けて材料の加工を行いました。
教職課程グループは、竹を使った活動内容になっているので、全部で300程度パーツを切り分けます。
また、今年生えた新しい竹を使っているので、とても柔らかく手で割れる(!)ことも発見していました。

WSを行う際には、こういった地道な作業があります。
通常であれば大変な作業ですが、みんなで話ながら楽しく活動できるのはグループで活動することのメリットですね。
また、他の科の学生と話をすることで、自分の学科について改めて考察する場になっているようです。
作業はみんなの力であっという間に終わりました。
次回は本番直前の話し合いです!
ラストスパート頑張りましょう!
カテゴリ一覧
最新記事一覧
-
2019-08-05|ワークショップ
-
2017-07-19|授業風景
-
2017-03-07|ワークショップ
-
2016-08-02|授業風景
-
2014-10-28|ワークショップ
-
2014-10-10|ワークショップ
-
2014-08-08|ワークショップ
-
2014-08-04|ワークショップ
-
2014-07-08|ワークショップ
-
2014-06-20|ワークショップ