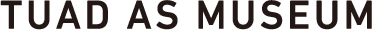日常が発光するとき―〈ひじおりの灯2006~2010〉
2011/07/01
肘折温泉は歴史ある湯治場である。しかしその効能の源は温泉ではなく、この地の〈コミュニティーの力〉にあるのではないか。肘折に行きたくなるときは、きまってあのすり鉢のような集落に生きる一人ひとりの顔が浮かんできて、会いたいな、と思う。
家族経営の小規模な湯治宿が路地にひしめき、常連客のなかには3〜4世代で通い詰めている人も少なくない。全国の温泉が地域ブランド競争によってサービスやオリジナリティーを磨き、顧客の囲い込みにやっきになるなかで、ここは普段着のまま親戚の家のような心持ちでくつろげる温泉地だ。〈湯治〉にはきっとそうした日常のままの弛みが必要で、それは今日的な観光の文脈で意図的につくり出せるものではない。
旅館は、そのまま湯守一家の日々の住まいでもある。他所に家があって出勤してきているのではない。たいてい玄関の脇にある居間に囲炉裏があり、仏壇や遺影があり、色とりどりのお供えもの、テレビや茶菓、お年寄りが孫と遊ぶための玩具など、いくつもの世代や時間が共存する生活空間が開かれている。
湯守たちは温泉旅館の経営者である前に、この山間集落のつつましい生活者である。彼らがプライベートな空間を開いてくれるから、湯治客の家族の時間が交わっていけるのだ。だから通えば通うだけ離れ難くなる。それはつまり、顧客のニーズに応える旅館経営ではなく、肘折というコミュニティーに客のほうから時間をかけて参加していく、ということなのだ。
『ひじおりの灯』は2010年の夏で、4回目の点灯を迎えた。灯ろう絵を描く30余名の学生たちは、分宿した先々で歓待を受けながら、灯ろうの図案を練っていく。4年をかけて両者の関係はかなりオープンになってきている。その橋渡し役として地元の青年団の存在は大きい。
この年、『ひじおりの灯』には肘折地区から3灯が出展された。地区の子どもたちから2灯、そして青年団からもうひとつ。学生たちは青年団を大学の版画工房に招待して彼らの制作をサポートした。若者たちの交流は双方向で深まってきていて、リピーターの卒業生のなかには、地元青年団の一員といってよいほど、地域にとけ込んでいるものも出てきた。
灯ろうの点灯にあわせて公開した肘折温泉の〈ひと/もの/こと/ばしょ〉を紹介するウェブサイト『ひじおり旅の手帖』は、2009年から卒業生の役野友美さんが、肘折ホテルに住み込みで取材と編集を進めてきたものだが、これを読むと、この湯治場が古くから歌人や画家、書家などのアウトサイダーを、有名・無名に関わらず手厚く迎えてきたことがわかる。
湯治場にやってくる人々は、どこかに傷や、痛みや、疲れや、感受性の渇きをもっている。ホスピタリティーという言葉はいかにも〈サーピス精神旺盛〉という響きをもっているが、肘折温泉のそれは痛みや歪みにより添う、あるいは湯治客が自らの内発的な力で治っていくのを邪魔しないように見守っていく、といった程よい距離感が、集落全体で習熟している。
肘折温泉の生活感覚が、訪れる学生やアーティストに開かれていけばいくほど、灯ろう絵には幽玄や悠久、あるいは民騨や土着信仰といった〈民俗的磁場としての肘折〉は影をひそめ、人々のつながりや日々の営みに注視した絵物語が紡がれていく。
飾らない、ありのままの肘折に接近していくことで、『ひじおりの灯』はかりそめの美に向かうのではなく、むしろ雛祭や精霊流しのように、日常の堆積がふっと発光し、肯定されるような、ある種の歳時記として地域に流れる時間に組み込まれている。
地域に根ざしたアートプロジェクトにとって、それはなんと幸福な道行きだろうか。
『ひじおりの灯』の風景自体はささやかな営みであるけれども、それを支える肘折温泉というコミュニティーの魅力はこのプロジェクトによって明確に顕在化している。鋭敏な人々は、すでにそのサインを受け取っている。
コミュニティーの(治癒)力。
それはこれからの日本社会にとって間違いなく不可欠なものであり、と同時に、肘折がひっそりと受け継いできた〈湯治文化〉の再興を予見させるのである。(Annual Report 2010「制作ノート」より再掲)
宮本武典(美術館大学センター主任学芸員)