東文研ORC_8ー9月の調査について
東文研ORC_8ー9月の調査についての説明会を下記の日程で行います。以下の地域の調査に参加希望者は必ず出席してください。
○長野県秋山郷
○秋田県男鹿半島
○青森県下北半島
日時:2009年7月30日(木) 18時〜
場所:本館5階、田口研前のガラス張りの講義室
以上、よろしくお願いします。
東北文化研究センター
岸本誠司
アーカイブス作業のアルバイト
今年度も東文研ORC事業「映像アーカイブの高度な活用に関する研究」にて、絵はがきや古写真のまとまったアーカイブス作業を実施します。
学生のみなさんにはアルバイトとしてこの作業に参加していもらいたいと思います。
以下の日程で説明会を実施しますので、希望者は参加してください。
日時:2009年7月30日(木)18:00
場所:東北文化研究センター会議室
東北文化研究センター
岸本誠司
東文研ORCプロジェクト2_八森調査スタート
東北文化研究センターのORC事業プロジェクト2「映像アーカイブの高度な活用に関する研究」の現地調査のお知らせです。
この夏より、これまで3年間にわたって実施してきた養蚕の参与調査学習をベースに八森地区と山形県内の養蚕に関わる民俗についての調査をスタートさせます。
下記の日程で説明会を行いますので、興味のある方は参加してください。
日 時:2009年7月29日(水)18:30〜
場 所:東北文化研究センター会議室
東北文化研究センター
岸本誠司
学科シンポジウム 『自立することから始まる未来』
1月31日に、毎年恒例となりました歴史遺産学科シンポジウムを開催しました。
去年に引き続き、メインテーマは「就職すること」です。
学科を卒業して社会で活躍中の先輩5名に、大学で学んだことや社会に出てから活かされたこと、考えたこと、就職活動への臨み方などを語っていただきました。
講師の先輩方のお仕事は、中学校の先生・博物館展示模型制作・NPO法人学芸員・雑誌編集者・不動産営業など様々。
働くということの厳しさについて、かなりリアルな実体験を交えつつのお話もありました。
しかしそれ以上に、仕事への熱意にあふれた先輩方の言葉は、しっかりと学生たちの心に響いたのではないでしょうか。
終了後、学生のみなさんに書いてもらったアンケートを一部紹介します。
「講師の方の話の中で、特に心に響いたことはどんな事ですか?」
・社会人はプロ意識を持ち、結果を出さなければならない
・大学生活の中で、自分にとって何が幸せかで楽しいかを探すこと
・自分を好きにならなければならない
・目標がないと前に進むのは難しい
・これをやりたい、という一念を持つ
・情報はアンテナをしっかり張って手に入れる
・あきらめない。というか社会に出たら、あきらめられない
・決断のタイミングと覚悟が大事
・お金を稼ぐのは大変だ
・自分の好きな仕事に就いていても、辛いことは必ずある
・歴史遺産学科にいたことを誇りに思って仕事をしている
などなど
感じ方は人それぞれだと思いますが、講演を聞いて心に残ったものを大切に就職活動に臨んでほしいと思います。
今まさに、3年生は就職活動真っ最中。
エントリーシートや履歴書の締切を気にしながらの参加だった人も多いようでした。
社会の一員として活躍する先輩方の姿は、みなさんの未来の姿でもあります。
がんばりましょう!


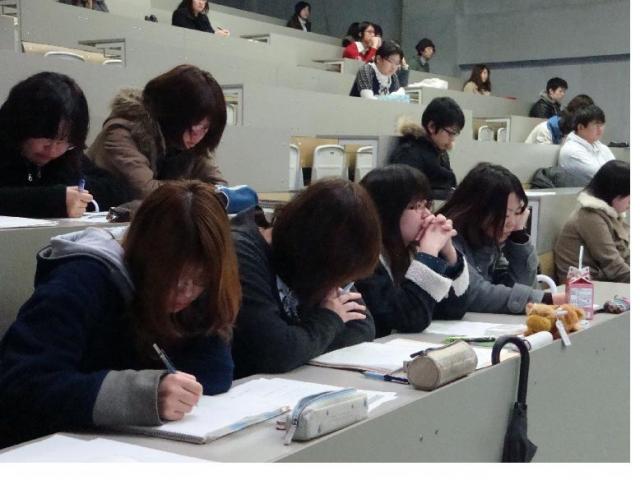

東北地方および極東ロシアにおける頭(かしら)信仰研究会
11月2・3日に「東北地方および極東ロシアにおける頭(かしら)信仰」研究会が開催されます。
東北地方には少なくとも中世以来、人間や動物の頭(かしら)を神聖視して祀る習俗や儀礼があると考えられ、その一部は頭骨信仰などといわれてきました。
現在、東北に生き続けているものに馬首信仰、山伏神楽の権現様(獅子頭)信仰、シシ踊りの頭儀礼、熊の頭骨崇拝などがありますが、それらはどう関連しているのでしょうか。
本研究会では、頭骨信仰も含めてそれらをとりあえず「頭(かしら)信仰」と名づけ、列島の南北にみる個々の事例の比較検討や相互の関連性を追求することをねらいとしています。
入場は無料です。ぜひお気軽にご参加ください。
——————————————————————————–
開催日時:平成20年11月2日(日)・3日(月)
会場:東北芸術工科大学 本館2階208講義室
——————————————————————————–
【日程】
<第一日目> 11月2日 13:30〜17:00
(1)開 会 13:30
(2)東文研所長挨拶
(3)問題提起
菊地和博「頭(かしら)信仰研究の意義について」13:35〜13:50分
(4)事例報告(各30分)
1.誉田慶信「慈覚大師木彫頭部にみる東北地方の宗教意識」
(岩手県立大学盛岡短期大学部) 13:55〜14:25 質疑10分
2.入間田宣夫「中尊寺領骨寺村における慈覚大師の首塚について」
(東北芸術工科大学歴史遺産学科) 14:40〜15:10 質疑10分
3.山口博之「中世墓における頭部の扱い」
(山形県教育庁文化遺産課) 15:25〜15:55 質疑10分
4.赤羽正春「東北地方の熊の頭骨崇拝」
(新潟県村上市立岩船小学校) 16:20〜16:50 質疑10分
(5)閉 会 17:00
<第二日目> 11月3日 9:00〜12:20
(1)開 会 9:00
(2)事例報告(各30分)
1.田口洋美「極東シベリアにみられる熊送りと頭骨」 9:00〜9:30 質疑10分
(東北芸術工科大学歴史遺産学科)
2.福田正宏「オホーツク文化の頭骨儀礼」 9:45〜10:15 質疑10分
(東北芸術工科大学歴史遺産学科)
3.菊地和博「シシの芸能にみる頭信仰と儀礼」 10:30〜11:00 質疑10分
(東北芸術工科大学歴史遺産学科)
4.全体討議 11:20〜12:20(60分)
(3)閉 会 12:20
——————————————————————————–
【主催】東北芸術工科大学
【企画・申込先】東北芸術工科大学 東北文化研究センター
詳細はPDFファイルをご覧ください


8月8、9日 高校生のための地域学ゼミナールを開催します!

私たちの身近にある地域文化を掘り下げてみると、そこには、今まで気づかなかったようなドラマティックに繰り広げられた歴史や、人が自然とともに生きていくために長い間培われてきた技術や心の世界が見えてきます。その発見はおどろきの連続です。
そこで高校生のみなさん向けに、地域文化のおもしろさを知っていただくため「高校生のための地域学ゼミナール」を開催します。今回は、出羽三山信仰や鉱山と結びつきの深い肘折温泉を舞台に、「火の民俗と文化」をテーマに、東北の地域文化について考えます。
高校生のみなさん、一緒に地域を歩いてみませんか。
——————————————————————————–
【日 程】
平成20年8月8日、9日(1泊2日)
[8月8日(金)]
13:00 新庄駅集合 → マイクロバスで肘折温泉へ移動
14:00 地域学ゼミナール「火の民俗と文化」会場:肘折ホテル
17:30 夕食
18:30 温泉街の散策・「ひじおりの灯」* の見学
20:00 “火の文化”に関する映像の上映会・夜語り 宿泊:肘折ホテル
[8月9日(土)]
9:30 肘折温泉民俗ツアー(地蔵倉、鉱山跡など)
昼食後、新庄駅にて解散
*「ひじおりの灯」・・・7月13日の開湯祭から8月20日の精霊流しの期間に、本学生制作の灯籠が夜の温泉街を灯します。
【開催地】
山形県大蔵村肘折温泉
【対 象】
高校生 (学年不問)保護者の方 高校の先生
【参加料】
高校生: 3,000円(食事・宿泊・保険含)
大 人: 8,000円(食事・宿泊・保険含)
※申込期限:平成20年 8月4日(月)
【講 師】
赤坂憲雄(本学大学院長・東北文化研究センター所長)
内藤正敏(本学大学院教授・東北文化研究センター研究員)
森 繁哉(本学東北文化研究センター教授・こども芸術大学教頭)
六車由実(本学芸術学部歴史遺産学科准教授・東北文化研究センター研究員)
岸本誠司(本学東北文化研究センター専任講師)
【お問い合わせ・申し込み】
東北芸術工科大学東北文化研究センター
TEL : 023-627-2168 FAX : 023-627-2155
E-mail:tobunken@aga.tuad.ac.jp
【主催】
東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科・東北文化研究センター
【後援】
山形県教育委員会 大蔵村 大蔵村教育委員会
——————————————————————————–
ゼミナールのチラシと申込書です。詳しくはこちらをご覧ください。

もののけ姫!

8月3日(日)13:00〜15:00、オープンキャンパスの模擬授業として、
「もののけ姫から歴史・民俗・考古の世界へ」が開催されます。
歴史遺産学科の先生たちも「もののけ姫」の大ファンです。
アシタカはどこから来たのか?何者なのか?
アシタカのキラキラ光る黒い石のペンダントが意味するものは?
エボシの村の秘密は?
タタラ集団って何だろう?
シシ神はどうして殺されなければならなかったのか?
病者の人たちはなぜ描かれているのか?
「共に生きよう」というアシタカの言葉にこめられたメッセージとは?
サンとアシタカの未来は?
歴史遺産学科の先生たちが総力をあげてみなさんにお話します。
最近の投稿
- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿
- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介
- 学生たちのアイドル
- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り
- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下
最近のコメント
- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より
アーカイブ
- 2020年6月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月






