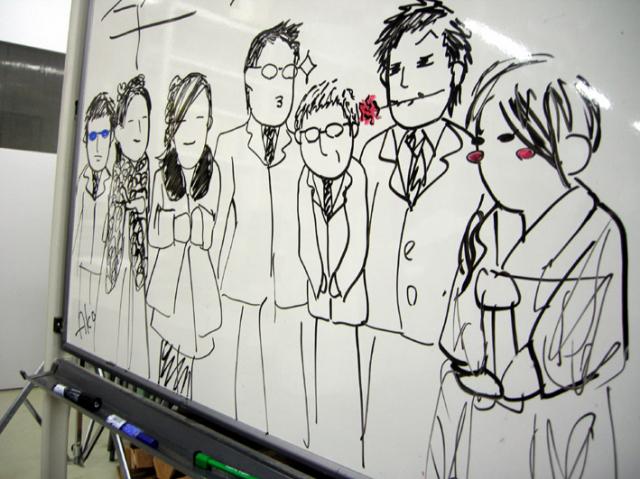北海道研修旅行 その2
北海道研修旅行つづきです。
18日(水曜)
車で上ノ国まで移動。主に倭人の暮らしを学んできました。「円空仏」や、鰊漁で栄えた「旧笹浪家住宅母屋」、解体修理中の「上国寺」、「勝山館跡」などを見学しました。中でも勝山館跡はアイヌと倭人の関係を表す、貴重な資料を見ることが出来ました。野外展示も、吹雪に負けず頑張って見てきました。
19日(木曜)
昼間は函館市内の博物館をまわり、夜は教育委員会の方と懇親会です。いやあ、楽しかった!もっとお話したかったです…。お店のアイスがあまりに美味しかったため、路面電車に乗り遅れてしまいました。ここで今回得た豆知識。「アイスに粉チーズかけて食べるとウマイ!」
20日(金曜)
午前中は五稜郭見学です。雪が降っていて寒いのと、「上から見ないと五稜郭の形が分からん」という理由であまりじっくり見学しませんでした。雪の無い時にまた来たいと思います。
そしてフェリーに乗って青森へ。波の高さは6m!とにかく揺れました。酔わないための一番の方法は、もう寝るしかないです。しかし、ここも雑魚寝状態なので、ほとんど眠れませんでした。何度も寝顔を撮られても全く起きないという、スゴイ方もいらっしゃいましたけど。
夕方に青森のホテルに到着しました。ご飯を食べたら即おやすみなさい。
21日(土曜)
朝に青森を出発し、あとはひたすら山形へ南下するだけです。だんだんと温かくなっていくのを肌で感じることができました。15:00過ぎに芸工大に到着。先生、吹雪中での長時間の運転本当にお疲れ様でした!
ほんと楽しかったです。
たくさん見て回ったと感じる反面、まだまだ見たりないという気持ちもあります。アイヌと倭人の関係というものは、少しの勉強で理解できるものではないと、改めて思いました。もっと北海道にいたかったです。
友人「いっそのこと、北海道に移住しちゃえば?」
私 「それは老後の楽しみ!」
by.W・T



北海道研修旅行 その1
どうも、極上霜降り肉よりも脳みその方が好きなW・Tです。だっておいしいんだもん。
実は2月13〜21日の間、福田先生と学生9人の10人で北海道に行ってまいりました。北海道のアイヌ文化を学ぶための研修旅行、つまり授業の一環です。日程は以下の通り。
13日(金曜)
芸工大を13:00出発、車で青森まで移動し、22:00八戸発のフェリーに乗りました。そのままフェリー内に宿泊です。敷布も無い部屋で雑魚寝でした。
14日(土曜)
朝、苫小牧港着。バレンタインなんて全く関係ありません。車で札幌を目指しながら、平取町立アイヌ文化博物館や萱野茂資料館を見学しました。平取はアイヌにまつわる資料が豊富に残っている町です。
夕方、札幌に到着。ホテルに荷物を預けたら、もう自由時間!私は札幌市内を徘徊…いえ、歩いて買い物をしました。他の学生はどんな楽しみ方をしたのでしょう?
15日(日曜)
昨日まで天気良かったのに…雪+風=吹雪です。そんな中で、「北海道開拓記念館」と「開拓の村」を見学しました。レトロな建物がイイ感じです。
そして「白い恋人パーク」。ここで北海道定番のお菓子を購入、クリオネも見てきました。この日の夜は吹雪で外出できませんでしたが、女性陣はここで買ったケーキのおかげで至福の時間を過ごすことが出来ました。
16日(月曜)
地下道を利用しながら、徒歩で札幌市内を回りました。北海道旧道庁、時計台、北海道大学を見学。時計台は日本三大がっかり名所として…ゴホゴホ、札幌の観光としてとても有名ですね。
北海道大学の博物館、月曜日は休館なのですが、特別に入場させていただきました。本当にありがとうございました!
夜、たくさん歩いて疲れたところでぐっすり眠れると思いきや、ある事件が発生。このせいで女性陣は全員寝不足になりました…
(事件の詳細については、本人のプライバシーもあるので自主規制させていただきます☆)
17日(火曜)
この日は1日中移動です。すごい吹雪かと思いきやいきなり青空になったりと、見ていて面白いです。頑張ってずっと起きていた甲斐があった…
函館滞在中に泊まる施設は、規則は少し厳しいですがとても綺麗な建物で満足です。今夜は昨日の分までぐっすり。
つづく
by W・T





チュートリ茨城旅行

チュートリ・どきどき野焼きの年度末旅行、今年は茨城方面に行ってきました。目的地は焼き物の里・笠間です。まずひたちなか市の虎塚古墳・十五郎横穴を見学、それから瓦塚窯跡の発掘現場へ。宿泊は夜景と星空がきれいな愛宕山のスカイロッジ。
2日目は笠間市内へ。稲田石の石切り場、笠間城、茨城県立陶芸美術館、笠間焼の小路、最後に水戸偕楽園をみて山形に帰ってきました。偕楽園の梅もなかなか見事でしたが、岩間の街道筋にある家々の庭先の梅も風情があってよかってです。里はもうすっかり春でした。
夜、山形に着くとそこは雪国。一晩で20センチほど積もったそうな・・・・。






稲田石・・・人は見かけで判断しちゃいけないよ

稲田石は茨城県笠間市稲田に産出する花崗岩。香川県の庵治石(あじいし)や岡山県の万成石(まんなりいし)などとならんで国産みかげ石の代表選手です。白っぽいのが特徴で各種用途に人気があります。採掘は近代に入ってから、みかげ石の本場、小豆島から職人が移り住んではじまったそうです。平地から採掘でき、埋蔵量も多く、大消費地を控えているという有利な面があります。
日本の石材市場は、いま価格の安い中国産など外国産が席巻しています。墓石の展示場へいくと歴然とした価格差に驚かされます。外国産といえば、かつては原材料のみの輸入でしたが、近年は灯篭などのような精彩な加工の必要なものまでが現地で行われ、製品として入ってきています。
稲田石歴史資料館(石の百年館)には採掘の歴史や工程の解説があり、近代化以前の道具が収集展示されています。ここは行政ではなく、株式会社タカタという一企業が管理運営しているところがみそです。鉄矢(くさび)や玄翁、ノミを使って人力で石を切り出し加工していた時代から、ジェットバーナーや黒色火薬、重機を使って大規模に採掘する現代までの流れを年表とモノ、図書資料で展示しています。
車を止め、資料館のとなりにある会社の事務所に入ると、こわもてのおじさんがひとり。「すみません、見学したいんですけど・・・・」というと、「どっからきた?」「山形からです。大学生なんですが・・・・」「そうかい、・・・お金いらないよ。みてって」
無人の資料館に置いてあるおみあげを買いたくて、事務所にかのオジサンを訪ねた学生はその外見に明らかにビビッていた。でも入館料一人300円をまけてくれたことを告げると、「オジサンはとってもいい人だ」と。そう、人は見かけで判断してはいけない。職人にはそんな人が多いのです。
少し離れたところに中野組石材工業という会社があります。ここでは会社の裏にある採掘場を公開しており、見学場所にはオブジェがならぶ公園があります。ここでは稲田石材商工業協同組合が主体となって毎年「いなだストーンエキシビジョン」というデザイン展が開催されています。
これまで古代から現代まで、たくさんの「石切場」をみてきました。あらためて思うのは、石切場遺跡の「芸術性」です。人が自然−石を利用するために闘ってきた痕跡。歴史の積み重ね、「時間」が凝縮された採掘場。それ自体が人類の現在や未来を考えさせるオブジェのような存在といえます。
石切丁場に魅かれる理由が少しずつ分かってきたような気がします。


その名も瓦塚

卒業生が発掘している瓦窯の現場を見学してきました。遺跡は石岡市瓦塚窯跡といい、常陸国分寺や国分尼寺に屋瓦を供給した場所です。5カ年で範囲確認調査と整備が行われる計画だそうです。
磁気探査等で10基以上(20基ぐらいありそう?)の窯の存在が推定されています。いずれも地下式で保存状態が極めてよいのが特徴です。過去に発掘された小型の瓦窯2基は天井が遺存しており、覆い屋がかけられ地元保存会の手で大事に管理されています。里山景観の保持も含め、地域に愛されて遺跡が保存されているいい事例です。
平場にあったトレンチの断面には瓦が山積みに捨てられている様子がみられ、まさに「瓦塚」でした。削平された法面には窯を輪切りにした断面が露出。壁面の粘土貼りや被熱状態がよく観察できます。


卒論発表会と追いコン

今年も恒例の卒論・修論発表会が行われました。例年は30〜35名を2日間に分けていましたが今年は1日でやってしまうという異例の措置。朝9時から始め、終わったのは夜8時半というロングラン。1月半ばの論文提出後も、レジメ原稿、展示ポスター、プレゼン用のパワポ作りと息抜くひまがなかったかもしれません。しかし、論文は熱く熱く書きとめたあと、一定の冷却期間をおいて再構成したり、ぜい肉をそぎ落とす作業がはいるともっと良くなります。ポスターを見たり、プレゼンを聞くと、提出後の1か月、大事に温めていた学生と、放り出してしまった学生の差がはっきりわかります。
ともあれ、4年生はこれで「大学」という大切な時間と場を卒業していくことになります。就活と卒論、ともに人生を豊かにいきていくための試練です。まじめに取り組んだ学生には明るい未来があることを信じています。
翌日、卒業・修了生の労をねぎらう学科の追いコンが開かれました。発表会とあわせ会のお世話をしてくれた3年生ご苦労様でした。来年はあなたたちが主役です。


桃山御陵と伏見城

京都「桃山陵墓地」は豊臣秀吉が築いた伏見城の本丸南斜面に、大正2年に明治天皇陵、大正4年に皇太后陵が築かれた場所です。近くには平安時代の桓武天皇のお墓もあります。
文禄元年、秀吉は関白の座を秀次に譲り、隠居城として京都伏見に城を作り始めました。文禄の役のため肥前名護屋にいたときです。この時の指月伏見城は文禄末年に地震で倒壊し、引き続き慶長元年〜2年、背後の木幡山(こはたやま)に築いたのがこの城です。翌年に亡くなるまで秀吉はここを拠点としました。
その後、関ケ原を勝利した徳川家康が慶長6年から入り、再建を進めましたが、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡すると、その役割を終え、元和6年に伏見城は破却・解体されたのです。この年はちょうど徳川大坂城の築造がはじまった年で、解体された伏見城の石垣石は大坂城にも持っていかれたと考えられています。
伏見城下町周辺の発掘ではこのような文献史料を裏付ける証拠が少しずつ見えてきています。石垣は解体されてほとんど残っていませんが、発掘された石垣石からどこまで分かるのでしょうか。秀吉期のものか、徳川期のものか。



松山城と「坂の上の雲」

全国城跡等石垣整備調査研究会(文化庁・開催自治体主催)が愛媛県松山市で開かれました。毎年1月に開催され、姫路、肥前名護屋(佐賀)、仙台、金沢、熊本と続き、今年が6回目。「石垣解体の諸問題−石垣手引書の作成に向けて」がテーマとなりました。四国各地の事例報告のあと、北垣聰一郎氏ほか4名のパネリストと、私がコーディネーターとなり、パネルディスカッションを行いました。来年は甲府、テーマは石垣修復の諸問題にうつっていきます。再来年は・・・(某市に内定)。この手の研究会は、飲み会の場で次の開催地が決まるのです。ぽんぽんと後ろから肩を叩かれると要注意!
この研究会は石垣整備に関する行政課題について議論する場としてスタートしましたが、近年は市民の関心が高く、年々参加者が増えています。今回は石工さんたちの集まりである「文化財石垣保存技術協議会」の研修会も兼ね、また、2日目には「城のあるまちのこれから」と題する活用をテーマにしたシンポジウムも行われました。
午後からは松山城の現地見学。解体修理工事現場や城全体の石垣めぐりをおこない、最後はなぜか坂の上の雲ミュージアムの見学というコース。いま松山は「坂の上の雲」(司馬遼太郎原作・松山が舞台)でもりあがっています。漱石や子規を輩出した文豪のまちを売りにしているのと、秋から豪華キャストによる同名のドラマ(NHK)が始まるからです。明治の国づくりに燃える若者の生き方や軍事国家に突入していく激動の時代を描いたドラマのようです。
きょうは全国的に寒い一日だったようですが、松山でも夕方に雪が舞いました。13:00から始まった石垣めぐり、小雪が舞うなか、16:30ごろにやっとミュージアムにたどり着く。展示を見ながら冷えきった体を温めました。
明日も朝から一日石垣ツアーです。あきもせず・・・・。






その後国鳥は…

どうも、「外出するときはビニール袋を常備している」W・Tです。久しぶりの更新です。
「キジはどうなったの?」という声をあちこちからいただいているので、現状をお伝えします。
実は、まだ頭骨しか処理していません。
骨格標本を作る時に肉を溶かす酵素を使うのですが、ある程度温度が高くないと酵素がうまく働かないんです。夏のときと比べ、制作にかかる時間・手間は共に倍になってしまいます。なので、頭だけで妥協してしまいました。
少し温かくなったら作業を進めていきたいと思っています。
ちなみに、写真は今回のキジです。
2つのワッカは「強膜骨」という、まあ簡単に言うと目の骨になります。
右の変な形をしたモノは「舌骨」です。そのまんま、舌の骨です。私の不注意で、左側の破損した部分を無くしてしまいました…
そのうち「骨格標本の作り方」や「毛皮のなめし方」などをアップして、皆さんにこの世界の素晴らしさを紹介できたら良いなぁと考えています。
…え、しなくてもいいって?
‥‥(; ;)
by.W・T
最近の投稿
- 史跡”楢下宿”の魅力ー芸工大生が調べた🔍楢下宿
- 歴史遺産学科 各種SNSについてご紹介
- 学生たちのアイドル
- かみのやま草屋根プロジェクト2019 楢下茅刈り
- 第30回かみのやまツール・ド・ラ・フランスin楢下
最近のコメント
- 映像学科と合同授業ー日向洞窟と写真撮影ー に より
アーカイブ
- 2020年6月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年8月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月