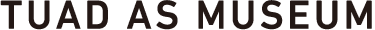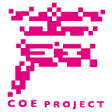最終日15日目。スペシャル企画「記憶と風景」
2012/11/10
最終日となりました。
スペシャル企画②「記憶と風景 -忘れられない風景-」の
ゲストは五十嵐太郎先生(建築史家、評論家、東北大学教授)と、
根岸吉太郎先生(映画監督、東北芸術工科大学大学長)です。
最初に五十嵐太郎さんは私たちの展覧会「記憶の声」にちなんで、
sounds from beneath という炭鉱の記憶を、声で表現している作品を紹介してくださいました。
その後、震災以降の話になり、自分自身の足で女川町など数多くの被災地をまわり、
自分自身の目で確かめ、自分自身の身体で体験してきたお話をしてくださいました。
気仙沼では重油のにおいが充満していて、
「視覚よりも他の五感での印象の方がより記憶に残りやすい」
という実感を伴ったそうです。
五十嵐さんの著書『被災地を歩きながら考えたこと』にもあるように、
五十嵐さんは建築の専門家として「震災の記憶」をいかに残すべきかを考えておられます。
例えばイタリアのジベリーナという地域は、1968年の地震で町が崩壊し、
その後町全体がまるごと移転しました。
しかし町がそこに存在していたという記憶は、
アルベルト・ブッリというアーティストによって白いセメントで町全体が覆われ、
ランドアート化され、残されています。
根岸先生は震災後はじめて山形空港に降り立ったとき、
通常ならついているはずの暖房が切られ、底冷えする空港の寒さを体験した身体の記憶が
今でも忘れられない、というお話からスタートしました。
3.11に関するそれぞれの物語は尽きません。
身体で感じたことは、身体の奥で時間とともに醸成され、個人の記憶として刻まれるのでしょう。
映画監督である根岸先生は
「映画はそもそも記憶をつくる仕事である」と述べています。
その根岸先生は最近「記憶がだんだん広がっていく」現象を感じたそうです。
「広がっていく」という感覚は、実体験がないにも関わらず、
戦争など過去の記憶を自分の身体のどこかで感じるものらしいです。
年齢を重ねるにつれ、そういう不思議な感覚を覚えるようになったそうです。
そして根岸先生にとっての記憶は、
「リアルだけど、脆いものである」と繰り返し述べられました。
「記憶」と「記録」は違うものです。
「記憶を伝えるのがアートの力なのではないか」と話す五十嵐さん。
五十嵐さんは2013年あいちトリエンナーレの芸術監督です。
テーマは「揺れる大地 われわれはどこに立っているのか 場所、記憶そして復活」です。
偶然とはいえ、本展覧会「記憶の声」と同様ずばり
「記憶」がテーマである のは、今の時代性なのでしょう。
ところで、皆さん気づきましたか?
今日の会場は三方向から囲われる形です。
なぜなら今日は観客が100人を超えることを想定し、
あらかじめ130人収容の座席数を設けていたからです。
実際、別会場(UST会場)の201大講義室でも、約100人の学生が聞き入っていたそうです。
今日はゲストが放つオーラなどもあって、
「声のステージ」に集中する、ある種の緊張感が生まれていました。
「今日はいつもと違って会場に緊張感があって、
それが僕にとってはなんだか心地よく感じるんです」と原さん。
原さんの作品づくりは今回に限らずいつも他者の声に耳を傾けることから始めています。
人だけでなく、古い建築物とも対話を行いながら、
世界各国で「窓プロジェクト」を手がけてきました。
その土地のおじいちゃん、おばあちゃんとも対話を行い、
「その人が語る物語こそ、リアルを感じる」そうです。
ブラジルでは「昔の日本人」に出会い、ある種の距離感を覚えながらも、
彼らに深い敬意を払った、というエピソードをお話してくれました。
実は五十嵐さんは、原さんの作品を台北や香港でご覧になっており、
窓プロジェクトのことを随分前から評価してくださっていました。
西澤さんも以前、伊豆の下田で使われなくなった大正時代の古い精氷場を、
建物の記憶を残しながらその魅力を伝え、
別な形で蘇らせるプロジェクトを手がけています。
今でこそ「リノベーション」という言葉が通じる時代ですが、
その当時は既存の古い建築物を蘇らせる、という概念はほとんどなかった時代でした。
*********
このように異なるフィールドで活躍する皆さんが、
それぞれの観点から語る、記憶に関するお話はとても興味深いものでした。
あっという間に時間は過ぎ、
終了予定時刻を超え、約2時間に渡るものとなりました。
その様子はUstreamで録画されておりますので、興味のある方はこちらをご覧ください。
**************
最後に参加型インスタレーション「記憶の森」の《言の葉》にメッセージを残すおふたり。
遅くまで残ってくれた皆さんと一緒に、恒例の記念撮影です。
展覧会の最終日に、素晴らしいひとときを皆さんと過ごすことができ、大変うれしく存じます。
***********
あっという間の15日間でした。
展覧会会場で、皆さんと共有した時間と多種多様なイベントの数々は、
私にとって「忘れがたい記憶」となりました。
学生スタッフcoiceの皆さん、イベントに参加してくださった先生方、
インタビューに応じてくれた多くの皆さん、大学事務の皆さん、
本当のたくさんの方に支えられながら、展覧会を無事に終了することができました。
この場をお借りして、ご協力いただきました方々に、心より御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
和田菜穂子(キュレーター)