既に発表されております「第1回文芸ラジオ新人賞」ですが、審査員の講評を公開いたします。第2回文芸ラジオ新人賞への応募の一つの指標にしてください。
イノベーション(innovation)というのは元はヨーゼフ・シュンペーターによる経済学の用語であるが、この頃は一般的に使われるようになった。ただ「進歩」という意味だと勘違いしている人が多い。本来は「結合」という意味である。受賞作の丸山千耀氏の『星屑のブロンシュ』には、イノベーションがある。純文学と童話とファンタジーと、彼女自身の幼い日の記憶の「結合」があり、そのことにより、新しい世界を切り拓くことに成功している。後は例えば「ブロンシュ」という存在を、ユングの言う集合的無意識の層に届くまで深めていってほしい。
吉川敦氏の『須弥山としゅみせん』は奇妙な、そう言ってよければトボけた魅力のある作品である。そのトボけた世界を何かエネルギーのある世界に「結合」できれば、新しい地平へ出られるのではないかと思う。ふくらませた風船は弱い箇所から爆発する。そういう小説を書いてほしい。
蒔田あお氏の『フェイス・トゥ・フェイス』はよくまとまってはいるが、やはり別の世界との衝突が必要であるような気がする。
文学も経済も、もはやイノベーションの向こう側にしか可能性はないのだと、今のぼくは痛切に感じている。
手法の斬新さでもテーマでも文章力でも世界観でもなんでもいい、一点でも図抜けていれば、受賞作に推したい。そう考えていたが、残念ながら、推したい作品はなかった。
小説としてのまとまりが比較的良かったのは、蒔田あお氏の『フェイス・トゥ・フェイス』だ。文章は安定している。が、ストーリー展開の強引さをカバーするだけの力はない。小説としての形を整えることではなく、破綻を怖れず、個性を強烈に発揮することに力を注いでもらいたいと思う。
受賞作は丸山千耀氏の『星屑のブロンシュ』だが、この作品の良さが私にはまったくわからなかった。最大の問題は、書き手と作中の「私」の距離が確保されていないことだ。この撞着によって、小説世界は、「私」=書き手の内的世界となる。客観的な視線など導入のしようがない。無邪気なままごと、あるいは、箱庭療法のロールプレイング的世界が無批判に繰り広げられるだけだ。
作者にはこの作品で満足せず、自分の慣れ親しんだ箱庭的世界を放棄して、現実としっかり向き合い、勇気を出して新しい小説世界の構築に挑戦して欲しい。この受賞が飛躍のきっかけになることを切に願っています。
まず『須弥山としゅみせん』だが、ひとつのモチーフでおしていくため、モノローグに陥ってしまっている。『フェイス・トゥ・フェイス』には、フィクションを創ろうという意思がみられるが、新人に必要であるはずの野心が決定的に欠けている。
『星屑のブロンシュ』は評価が割れた。とくに最後の展開がご都合主義的なのか否かで解釈の違いがみられた。ただ野心的な作品であることは間違いなく、最後は読者の判断に委ねることで作者の賭けにのることにした。

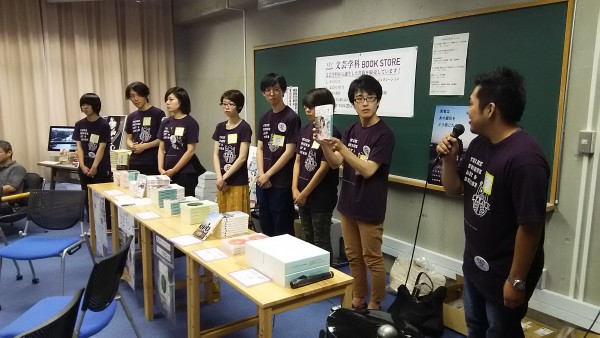

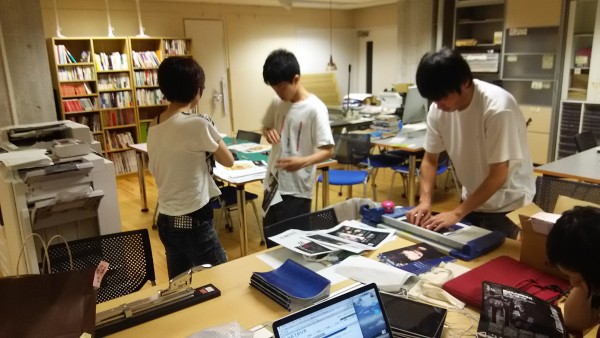
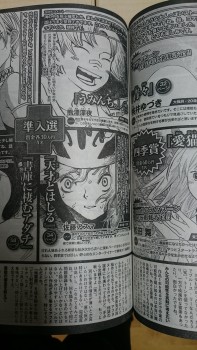
![アフタヌーン 2016年 09 月号 [雑誌]](http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/nav2/dp/no-image-no-ciu.gif)


![文芸ラジオ 2号 ([テキスト])](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qelXbU5RL._SL160_.jpg)










