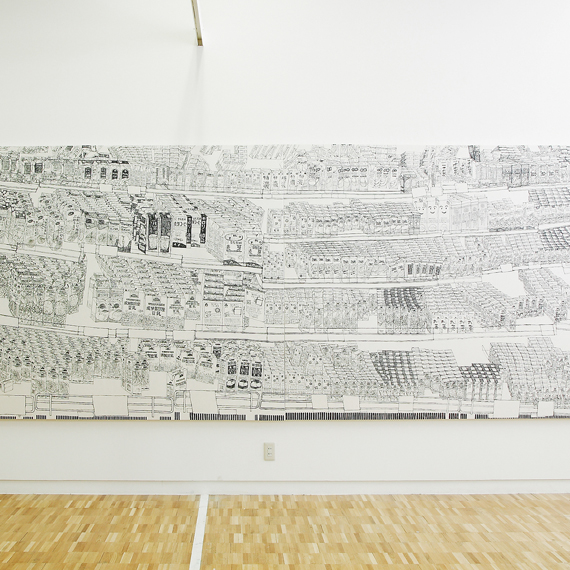過去照会
土屋裕太郎 Yutaro Tsuchiya
[映像計画コース]
マエキタミヤコ 評
プライベートな感じと、それが公になる境が溶けるところが、見ていてグラッとくるのかなと思いました。
酒井忠康 評
誰が言った言葉か思い出せないのだけれど、カメラを向けた時に相手が構えないというのは、いわゆる先天的なカメラマンだという写真家の話。写真の技術や芸 術性はその人の評価につながるけれども、その前に、カメラを持った時に相手が構えないで自然に撮られてしまう。そういうところが彼にはあるね。だからイン タビューされている相手は、非常に気楽に楽しそうに話している。そういう意味で、気持ちの良い作品に仕上がったのだと思います。
(2009年度 卒展プライズ受賞作品)