最初にして最後の投稿になりますが、どうも4年間文芸学科の副手をしていた池谷です。
私は静岡から芸工大に進学して、大学院に進み最初の就職も芸工大で
してしまったので足掛け10年間山形で過ごしました。
何を書こうか色々考えていたのですが、有益な情報というか、ここ行っとくと山形楽しいよ
スポットを書いてみようかと思います。
1、八百坊
芸工大から一番近い源泉掛け流しの公衆浴場です。お湯は熱めでぬるっとしてます。
気分転換に良い。あと風邪の初期に効く。湯冷めに気をつけて!
2、百目鬼温泉(どめきおんせん)
車が無いと行くのが無理ゲーな公衆浴場。お湯は濁っていて鉄分豊富。
畑を掘ったら温泉が出たなんとも山形らしい。間違ってもアクセサリーつけたまま
入っちゃ駄目。関節に効きます。
3、三百坊(蕎麦屋)
大学の裏山にあるおそば屋さん。建物も古民家を移築してあり庭を眺めながら食べる
お蕎麦は絶品です。静岡生まれとしては固い蕎麦よりこれぐらいがちょうど良い。
注文してから打つから時間の余裕のある時に!
4、肘折温泉 カルデラ温泉館
めずらしい炭酸質のお湯が楽しめるカルデラ館。木造の建物で午後に入ると日差しが
お湯に入り込んでノスタルジーに浸れます。あと、肘折に行ったら絶対羽賀だんご店の
お団子食べて下さい>< 私は山形で一番美味しいと思ってます。
あと出来たら宿泊して朝市行ってみてー地元の山菜とか売ってて凄い楽しいから。
都市部から来た学生の皆さんは色々戸惑うことが多いと思いますが皆さんも
これからの4年間自分だけのお気に入りの山形を見つけて楽しんで下さい。
最初で最後のブログがこんなんで良いのか?と若干思いますが、まぁこれはこれでのご愛嬌。
これからも学科のブログを宜しくお願いします。新しい副手のブログをお楽しみに!


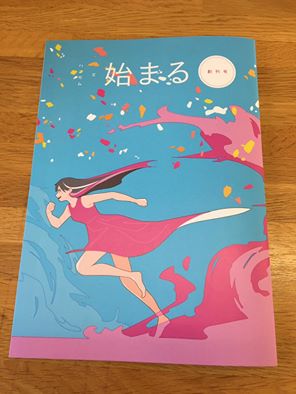









![連続テレビ小説 あさが来た 完全版 ブルーレイBOX1 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/518p3iOKrNL._SL160_.jpg)











