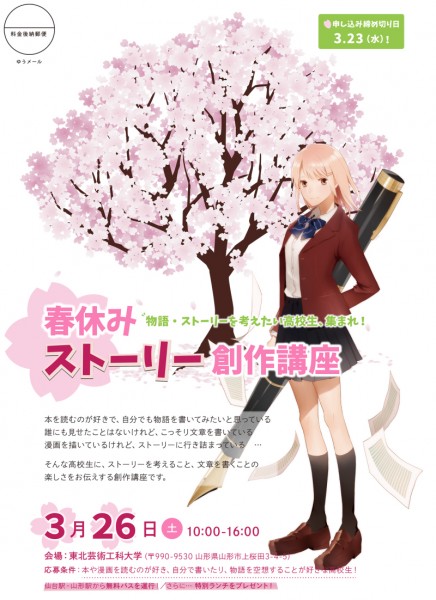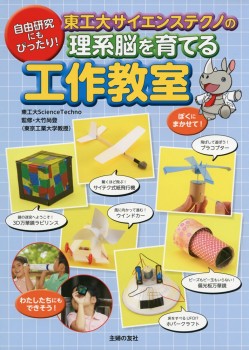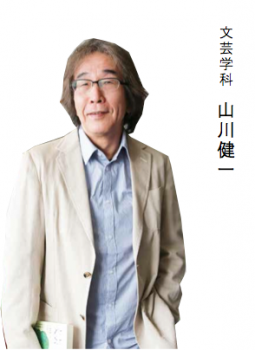自分自身が学生であったときには卒業式には出ていない。あとで事務所に行って、学位記をもらってきただけである。これだと5分で終わる。時間の使い方としては非常に合理的である。しかし教員となるとそうはいかない。私自身が専任教員になって2回目の卒業式が先日執り行われた。出席をし、行事をこなしていくだけで一日がかりの仕事になるのだ。
卒業式を終えた皆さんはこれからそれぞれ旅立っていくのであろう。大学という場所に同じようにいることはできない。もう一度、入学しなおしたとしても、そこで見えるのは違う景色である。大学院も修士、博士と通ってしまった私が言うのだから間違いない。なお学問の道に進みたいのであれば、一度、立ち止まって考えたほうがよい。相談にも乗ろう。これも長く通ってしまった身からのアドバイスである。さて、その皆さんに教員としてコメントを送るというのが、どうもこのような日には必要らしい。説教くさいことは何も必要はないと思っているし、他者の言葉に動かされていてはダメだろうぐらいしか感想も出てこない。
したがって本当にその場に行くまで何も考えていなかったし、自らの言葉を自分で探してくださいぐらいを言って短く終えようと思っていた。ところが私の前に話していた教員が春休み中、何をしていたのかという話から始めたので、即興で春休み中に読んだ本の話をしてしまった。
「後藤さん、クレームなのに、どうしてヘコまないんですか」
新人が客を怒らせた場合、私のところに回ってくる。私は平謝りし、上司にクレームであったことの報告をする。新人は新人で、自分で食い止められなかったことに少しは悪いと思うらしい。昼休みなどに、よく謝られたうえに前述の質問をされる。
「ぜんぶ、ハットリくんの声と言葉に変換するの」
(宮木あや子『憧憬☆カトマンズ』MF文庫ダ・ヴィンチ、12ページ)
これから就職をし、社会に出ていく(としておこう)皆さんは初めて自分に向けられる悪意や強烈な嫉妬などに直面するかもしれない。これまでは何だかんだ言いながら教員も職員も学食の人も購買部の人も親御さんもすべてが皆さんの味方であった。しかし庇護のないところで精神的にも孤立し、ただひたすら悪意を身に浴び続けなければならない日がこれから起こりうるかもしれない。その時は、宮木あや子の作品で描かれているように受け流して欲しい。他者の悪意をすべて受け止める必要はない。どうせ言葉は通じないのだ。ハットリくんでも地底人でも何でもテキトーに変換しておくといい。戦略的撤退だってありだ。ただし責任もすべて自分で取る必要がある。したがって、単なる撤退ではなく戦略的であることが望ましい。できれば最後は勝ちに行こうぜ、ぐらいのテンションである。
のようなことを喋った気がする。何せ前の晩にゲームをしていたら睡眠時間を大幅に削ってしまい非常に眠かったのだ。ブログを更新するのだから卒業式に関する写真ぐらい撮っておけばよかったのだが、それも思いつかないほど眠かった。
BGM:今井美樹「PIECE OF MY WISH」