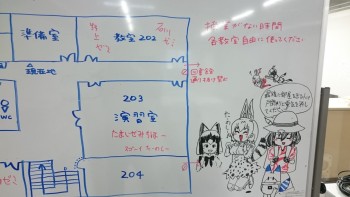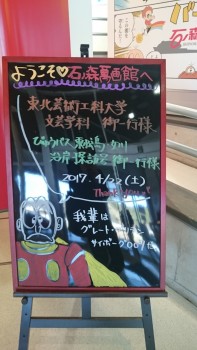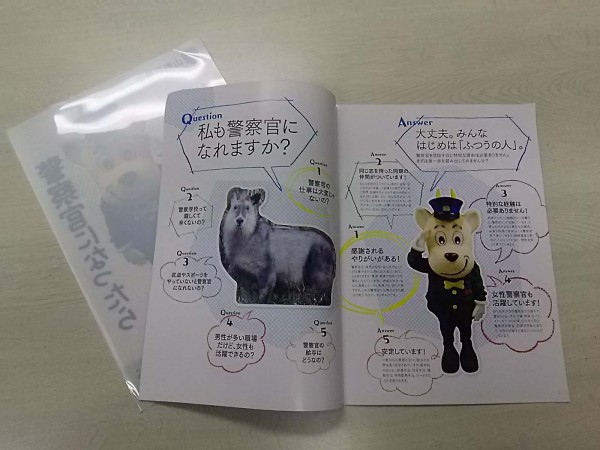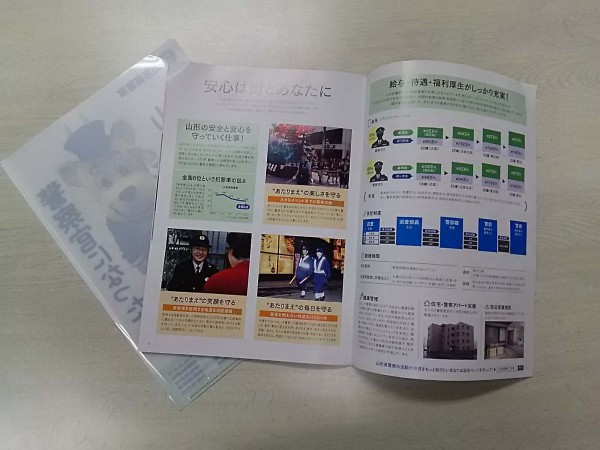文芸ラジオの編集作業は教員と学生が行っている。時に書き手も学生になるので、家内制手工業のようになってしまうことが多く、教員が上手く動かしていかないと迷走どころか激突して消えてしまいそうになる。これは特集作業も同様で、複数の人間による共同作業であり、メンバーの能力・気力が不均衡でいびつなパラメーターを描いている状況で行わなければならない。別に嫌だとか、諦めているとか、それでも頑張ろうとか、意味のない感情を上乗せしていく問題ではなく、現実としてそうなっているという話である。
今回の巻頭特集は猫である。そのために表紙では押切もえさんに猫を抱いていただいたわけだが、中身もまた猫をめぐって複合的な内容を目指している。まずは旅作家である小林希さんから旅先で出会った猫写真をご提供いただいた。もう、これだけでお腹いっぱいなのだが、小林さんには短編小説も書いていただき、まことにありがとうございますという感じである。そして写真というメディアだけではなく、イラストも様々な方に描いていただいた。『月詠』の大ヒットでおなじみであり、最近は川崎フロンターレの公認キャラクター「カワサキまるこ」を手掛けられている有馬啓太郎さん、少女漫画で活躍され、『世界の歴史』も描かれている芳村梨絵さん、実は私の大学の同期であり、『NEWまんが日本の歴史』などの歴史漫画でもおなじみの小坂伊吹さん、猫といえばかわいらしい猫を描かれていて、ぜひこの人にお願いしよう! と思った鈴木ネコさん……とプロの方々だけではなく、学内外のアマチュアの方にもお願いをしている。
小説は既述の小林希さんだけではなく、昨年9月の文芸ラジオイベントにもご登壇いただいたSF作家の高島雄哉さん(なのでこの作品は同じく3号に収録している講演録と同時に読むと、なお面白いです)、『薬屋のひとりごと』シリーズが大好きで、この人には絶対ご依頼しようと思っていた日向夏さん(新刊『カロリーは引いてください! ~学食ガールと満腹男子~』が富士見L文庫から発売中)からご寄稿いただいた。また私は創刊号から『文芸ラジオ』の編集に関わっており、創刊号では小松エメルさん、二号では秋山香乃さんと時代小説・歴史小説を手掛けられている方にご登場いただいている。これは端的に時代ものが好きなので、もっとジャンルとして大きくなって欲しいという極私的な願いも込めている。そして今回の3号では谷津矢車さんからエッセイをご寄稿いただいた。最新作『おもちゃ絵芳藤』(文藝春秋)では歌川国芳の弟子である芳藤を主人公に描いているが、今回のエッセイは国芳の猫ですよ。
前号2号の表紙といえば小橋めぐみさん。私がファンということももちろんあるが、本を愛する人たちというのは、問答無用で応援すべき存在である。今回も猫とからめながら本をめぐるエッセイをお書きいただいた。そして猫に関して評論が欲しい。猫と人間の付き合い方を考えている人はいないだろうか、ということで、早稲田大学の真辺将之さんに近代から現代日本における猫と人との関係について書いていただいた。素晴らしい。この評論により骨子が定まった気がして、原稿を受け取った際、感動したことを覚えている。お会いしたことはないのだが、実は大学の先輩なのでお名前は以前より存じ上げていた。この世は様々なところでつながっている。
それ以外にも学生の小説と漫画も掲載されており、そちらに関する私のコメントは個々人に直接、伝えていければと思う。これは編集者というよりは教育者としての活動である。
さて特集のタイトルは「猫というメディア」である。何がどうメディアなのかは巻頭文に書いたので、そちらをお読みいただきたい。どう受け止め、考え、収録作品を読んでいくのかは皆さん次第である。
(その3へ続く)