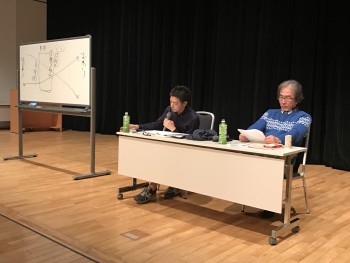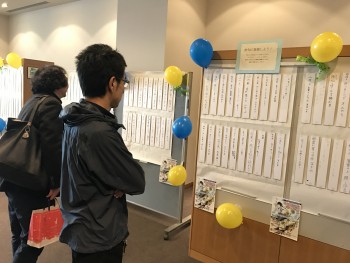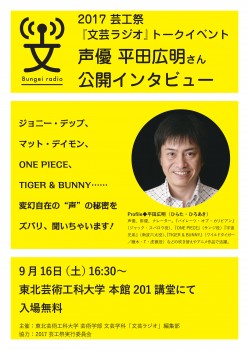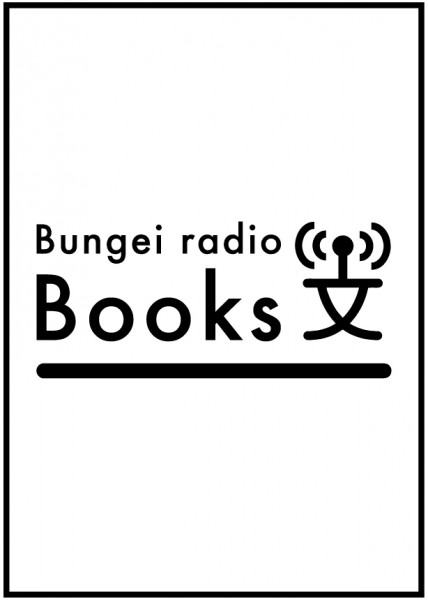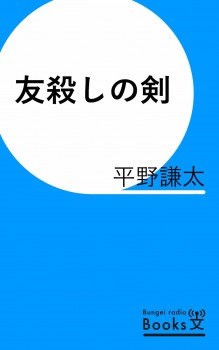文芸学科の学生作品を中心に発表する電子書籍レーベル「文芸ラジオブックス」がスタート!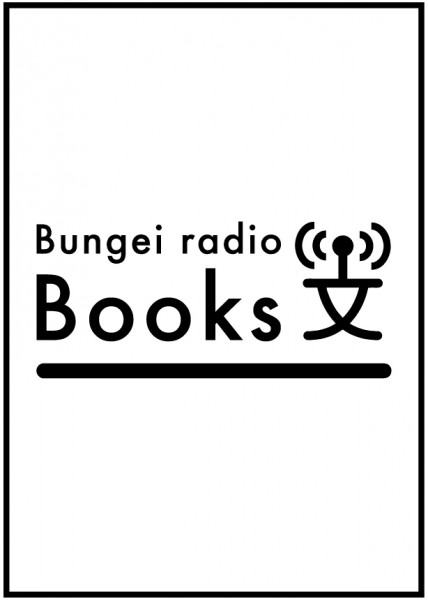
文芸学科では、かねてより学生・教員が多数執筆・編集に参加する文芸誌『文芸ラジオ』を年1回制作しております。このたび、その電子書籍レーベル「文芸ラジオブックス」が4冊の新刊タイトルでスタートいたしました。
文芸学科生の作品を中心に、学科や『文芸ラジオ』に関わりのあるプロ作家・アマチュア作家による作品が、KindleやiBookstore、楽天Koboなど国内20以上の電子書籍店舗でダウンロードが可能です。なお流通は電子書籍取次のモバイルブック・ジェーピーを通じて行われます。
皆様ご高覧くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
[文芸ラジオブックス 第1弾 4作品]

星屑のブロンシュ
丸山千耀 著
文芸ラジオ新人賞受賞作「星屑のブロンシュ」を含む珠玉の短編集!
[配信サイト]
honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE
kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon
koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan
Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM
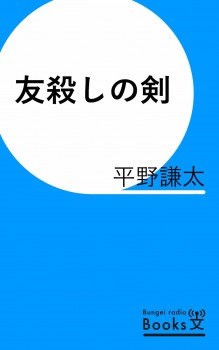
友殺しの剣
平野謙太 著
「文芸ラジオ」に掲載された著者初の時代小説集!
[配信サイト]
honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE
kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon
koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan
Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

光と闇のボーイ・ミーツ・ガール
佐藤滴/大川律子/塩野秋/成田光穂/山川陽太郎 著
「出会い」をテーマとしたアンソロジー第一弾!
[配信サイト]
honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE
kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon
koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan
Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM

どこかでオオカミが哭いている
森田一哉
80年代に活躍した「誰がカバやねんロックンロールショー」を率いたダンシング義隆の半生を描いたノンフィクション。
[配信サイト]
honto BOOKSMART どこでも読書 Varsity eBooks GALAPAGOS STORE
kinoppy リーダーストア ブックパス ドコモdマーケットBOOKストア デジタルe-hon
koboイーブックスストア iBookstore Kindleストア boocross eBookJapan
Booklice music.jp やまだ書店 yodobashi BOOK☆WALKER DMM.COM
[取材・内容お問い合わせ]
東北芸術工科大学 文芸準備室 文芸ラジオ編集部 野上勇人
E-mail bungeiradio@gmail.com