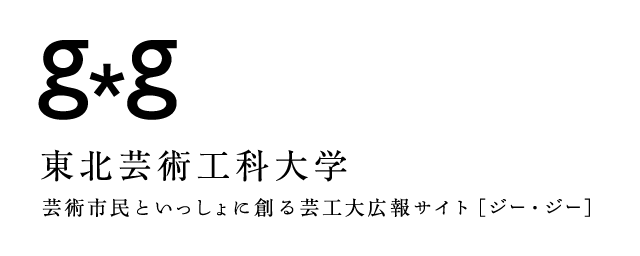デザインも多彩な柴野さん制作の紙製の服。8人の男性による試着ファッションショーはなかなかの壮観です。

大学院修士2年研究レビュー出品作品/"痕跡"をテーマに紙で制作された服
絵筆をミシンに代えて、一針一針思いを込めて。
平面を飛び出した日本画院生の新しい表現。

「まさか、紙で服を作るなんて……私自身もびっくりです。」と語る日本画の柴野緑さん。
これまでの研究・制作の中間発表として本館7階ギャラリーなど学内各所で開催した大学院修士2年研究レビュー。柴野緑さんの"痕跡"をテーマに制作された服も展示されました。紙で丁寧に作られ、微妙に着際された無数の服。なぜ、日本画専攻の大学院生が、実際に着られる紙の服をこんなに沢山作ったのか。そんな素朴な疑問を本人に投げかけてみました。
「昔は絵を描いていたんですよ。でも、まず絵ありきで、何を描こうか、どうしようか、ということではなく、もっと自分の中でやりたいことがあって、それを表現するために作品を作りたいと思うようになり、自分の欲求に従ってここに行き着きました。」いつの頃からか表現は平面の絵画でなくてもいいと感じるようになり、先生も賛同。学部の卒業制作で600個以上の木の枠を使ってオブジェを作ったことも、それを燃やして焼失させるというパフォーマンスを行ったことも、日本画のスタイルにとらわれない柴野さんならではの表現です。
そして、その作品が焼失したのを見たときに、作品が確かにここに存在した"痕跡"という概念が頭に浮かび、人が存在した"痕跡"を表現するアイテムとして服を選びました。「人間は服を着ます。それはその人に馴染んで、その人の生活の痕跡になります。それがいいなと思って」と柴野さん。ある人物が着ていた服を写し取って型紙パターンを作り、本当の服づくりと同じような工程で紙の服を縫い上げていきました。襟、ポケット、ボタンホールまで、かなりリアルに仕上げているのに、ほとんど色を使っていません。それは、表現したいと思った精神的なものや記憶といったものは、柴野さんの中では色のない世界だから。かすかに染められた色は、時の経過や雰囲気を出すためのもので、色という認識ではないといいます。
今回、8人の男性が柴野さんの作品を着用しg*gの表紙を飾りましたが、実際、人に着てもらうことは全くの想定外だったとか。服を縫って作ることに夢中になりすぎて、その先の、たとえば展示してみんなに見てもらう、人に着てもらうということにまで気が回らなかったようです。でも、縫うときは自分だけの世界だったものが、展示や試着を通して初めて鑑賞者と共感しあえるということを実感。今後は、作品が完成したらそこで一端区切って、次にそこからどんな芸術につなげられるかを考えるようになりました。鑑賞者から寄せられる質問や疑問にどう答えられるか、それも含めて作品なのだと気づかされたのです。
端からはいろんな方向を模索しているようにも見える柴野さんの表現。しかし、彼女の中ではしっかりとした一本道の上にいます。それが次にどんな表現につながっていくのか。それは周囲の大きな関心事でもあり、柴野さん自身にも予測不可能なことなのだそうです。