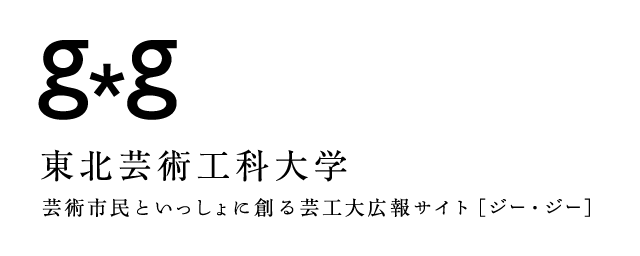制作メンバーと、赤に金で火の鳥が描かれた大きなタペストリー。

地道な作業と大きなスケール感で作品を作り上げた、
別名「八人の侍」(長沢教授含む)
山形交響楽団200回記念公演の空間演出『火の鳥』に、
日本画コースの学生7人が挑んだ

芸術研究棟の白い廊下に広げられた鮮やかな緋色のタペストリーは、山形交響楽団200回記念公演の空間演出として制作された『火の鳥』の一部。金色に輝く火の鳥が大きく翼を広げ、高く高く上昇していく様が描かれています。この飛翔をさらにダイナミックに表現するのは、熱く燃えるマグマのように赤く塗られ、3mの高さまで積み上げられた竹のオブジェ(紙面表紙)で、火の鳥はその上を舞うように掲げられました。
公演の当日は、多くの観客がこの作品と山形交響楽団が演奏するストラヴィンスキーの『火の鳥』を始めとする数々の楽曲が一体となり、空間を満たす様子を体験したはずです。

制作に参加したのは、長沢教授の呼びかけに応えた美術科日本画コースの有志7人です。主に「マグマ」の竹のオブジェを担当したのが白石さん、神津さん、江藤さん、大平さんたちの学部3年生。
万華鏡をキーワードに制作に取り組んだ白石さんは「誰一人欠けてもこのプロジェクトはできなかったと思います。肉体的、精神的にもハードでしたがスケール感のある仕上がりは感動的でした。」と、達成感をもって制作の現場を振り返りました。

神津さんは参加の動機を「日本画の平面に筆で表現を落とし込んでいく行為に、自分の中で壁を感じていました。立体をやりたい!という気持ちで悶々、うずうずとしていた時だったので、これはやるしかないと思いました。」と語り、大平さんも「平面での表現をする傍ら、彫刻など立体の存在感に興味と憧れがあり、展示をした経験もあったので参加しました。」と、日本画という抑えた表現を追求する者ならではの立体表現への欲求と、その魅力の大きさ聞かせてくれました。

火の鳥プロジェクトのメンバーたち。上から、白石琴美さん/神津舞香さん/江藤靖子さん/大平由香理さん(ともに日本画コース3年)
「日本画でインスタレーションというのが面白いと思いました。新しいことがしたかったんです」と語るのは江藤さん。元々現代アートへの興味を持っていた江藤さんは今回の制作を通して、チームワークの大切さ、言うべきことを言い、やるべき仕事をこなすことの重要性を感じたそうです。イメージを作って共有し、納得がいくまで話し合いながら心をひとつにすることは、ひとりで制作に向き合うことの多い日本画コースのメンバーにとっては新鮮な体験だったようで、多くのインスピレーションを受けたといいます。
竹材店の協力でマグマの為に提供された素材の竹は、2トントラック3台分。莫大な量の竹を切断し、洗浄と乾燥を経てから内側と外側を塗り分ける作業は昼夜を問わず、数日間続けられ、「ほとんど部活の合宿」(大平さん談)だったそうですが、その分メンバーの結束は固くなったようです。
大学院では鳥をモチーフに作品を生み出している、タペストリーの『火の鳥』を主に担当した大学院2年生の土井さんは「テーマが火の鳥と聞いて参加しましたが、実際に鳥を描く前にまず竹をなんとかしなくてはならない、というのが誤算でした。でも、やっていくうちに個性の強いみんなが家族のような繋がりを持てたことが、とても良かったです。またこのメンバーと一緒に大きなプロジェクトをやりたいですね。」と、メンバーへの信頼を語ってくれました。

アートディレクターの長沢明教授
アートディレクターを務めた長沢教授は、竹を素材に選んだ理由を「円形の断面を持つ竹は、音楽がもたらす調和による"和み"と真っ直ぐに成長していく揺るぎないイメージ」からであるとしましたが、それはそのまま制作に携わったメンバーの姿に重ねられていたかもしれません。普段の制作では触れることの少ない立体の持つ存在感、インスタレーションの可能性、イメージを共有するチームワークは、公演で好評を博しただけでなく学生たちにも大きな手応えと希望をもたらしたようです。