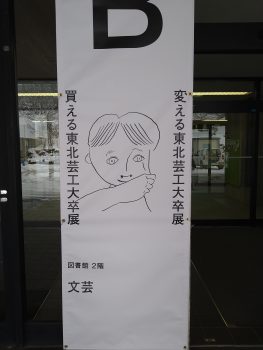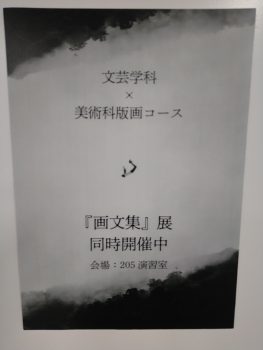2019年度の文芸論5のまとめを2020年度が終わりそうな2021年3月に書いている。この授業がスタートするまでは、一度も批評文や学術論文を読んだ経験もないのに「論文とか簡単に書けると思うので、研究者になれると思うんですよね」と学生から面と向かって言われる状況であったため、池田先生から授業を引き継いだときにまずは読む授業をやろうと思ったのである。
当然のごとくいきなり論考を執筆するのは無理なので、読んで接すること、内容を整理し、様々な考えや理論があること、最後に自分自身で書いてみること、この点を授業として取り組んでみたのである。
1:阿部純「好きなものを好きなように、どこまでも過剰により愉しく 自主制作メディアにおける「図像」の結び方」(『ユリイカ 特集 図鑑の世界』50巻14号、2018年)


私が赴任したときは学生たちの同人誌制作が活発で文フリへの参加も当然のように行われていたが、いつの間にかに外に出なくなっている気がする。自主制作という点ではZINEも同人誌も同じ枠組みなのだが、それぞれで認識の差異は存在しており、考えうるべきポイントだなと思っている。
2:田島悠来「越境・多層化する「アイドル」:人・物・場所の「アイドル」メディア論」(岡本健・松井広志編『ポスト情報メディア論』ナカニシヤ出版、2018年)


毎年のようにアイドル論を取り上げているが、アイドル自体に興味はない。けれどもなぜかアイドルをめぐる議論は面白く読んでいる。
3:西兼志「ライブ時代のアイドル/コミュニケーション・コミュニティ」(『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、2017年)


続けてのアイドル論である。メディアやコミュニケーションの問題に踏み込んで考えている。
4:柴那典「過圧縮ポップの誕生――「ジャンルの混在」と「八九秒の制約」から生まれた日本独自のポップミュージック形式」(高馬京子・松本健太郎編『越境する文化・コンテンツ・想像力』ナカニシヤ出版、2018年)


音楽の論考は実際に聞かないと始まらないだろうと流してみた。かけた曲は以下の通り。
斉藤由貴/卒業
AKB48/桜の花びらたち
BABYMETAL/ギミチョコ!!
THE MAD CAPSULE MARKETS/PULSE
聖飢魔II/蝋人形の館
MAKE-UP/ペガサス幻想
泉こなた……/もってけ!セーラーふく
どうぶつビスケッツ・PPP/ようこそジャパリパークへ
影山ヒロノブ/CHA-LA HEAD-CHA-LA
小沢健二/ラブリー
Betty Wright/Clean Up Woman
電気グルーヴ/Shangri-La
Bebu Silvetti/Spring Rain
TM NETWORK/Get Wild
JUDY AND MARY/そばかす
川本真琴 1/2
電気グルーヴ/ポケット カウボーイ
5:松井広志「メイルゲーム/ネットゲームのコミュニケーションと文化 ―多元的なゲーム史、ゲーム研究へ―」(松井広志・井口貴紀・大石真澄・秦美香子編『多元化するゲーム文化と社会』ニューゲームズオーダー、2019年)


ゲーム研究の流れを把握しつつ、メイルゲーム(手紙などで行われるPBM)を取り上げている。受講生の皆さんには昔のゲーム形態(しかもデジタルゲームではない)は馴染みのない様子であった。
6:加藤裕康「ゲーム実況イベント──ゲームセンターにおける実況の成立を手がかりに」(飯田豊・立石祥子編『現代メディア・イベント論』勁草書房、2017年)


ゲーム実況というとプレイ動画が喋りとともに配信されているイメージだが、ゲームセンターで行われる現象を取り上げている論考である。実際に見ないとわからないかもしれないと思い、複数のゲーム実況動画を流してみた。
7:嵯峨景子「吉屋信子から氷室冴子へ 少女小説と「誇り」の系譜」(『ユリイカ 特集 百合文化の現在』46巻15号、2014年)


少女小説研究を牽引している嵯峨さんの論考である。さておき受講生のなかには、これを読んで初めて少女小説というジャンルを知ったという人もいたので、それも一つの出会いである。
8:倉田容子「男装少女のポリティクス―一九七〇年代から八〇年代にかけての〈少女を愛する少女〉表象の転換」(西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える』ひつじ書房、2017年)


少しジェンダーを考えようとなった。現在進行形の百合ではなく、男装女性に含まれる様々な論点が迫ってくる論考である。
9:久米依子「トラブルとしてのセクシュアリティ――〈男の娘〉表象と少女コミュニティ志向」(一柳廣孝・久米依子編『ライトノベル・スタディーズ』青弓社、2013年)


男装女性を取り上げたので、男の娘を取り上げてみた。学生からのレポートも痛快な内容が書かれるなど、論点が複数把握されて面白い回となった。
10:石原千秋「読者にできる仕事」(『読者はどこにいるのか』河出書房新社、2009年)


作品自体を考えるのはもちろん重要だが、どう受け取られているのかという受容論も考えるべき点である。
11:小山昌弘「『風の谷のナウシカ』―物語の系譜マンガとアニメの相違点」(『宮崎駿マンガ論―『風の谷のナウシカ』精読』現代書館、2009年)


数年前にナウシカの論考を別の授業で取り上げて、ふとナウシカを見ているかどうか確認したら、数名しか見ていなかった事実を目の当たりにしたというのに、私はまた取り上げている。論考は物語論だけにとどまらず、マンガとアニメそれぞれを踏まえて考察されており、深い内容となっている。
12:小池隆太「物語構造論(ナラトロジー)―アニメ作品の物語構造とその特徴について」(小山昌宏・須川亜紀子編『アニメ研究入門 応用編』現代書館、2018年)


物語構造は文芸学科の必修授業で取り組んでいるので、復習と捉えている。物語構造論の流れを学ぶことができ、よくまとまった論考である。
13:河野真太郎「無縁な者たちの共同体――『おおかみこどもの雨と雪』と貧困の隠蔽」(『戦う姫、働く少女』堀之内出版、2017年)


毎年、最後の数回は具体的な作品論や作家論を取り上げるようにしている。最終課題では作品や作家を取り上げるのもOKにしているので、その先行事例としてである。この論考は貧困や労働の観点から作品を切り取っており、非常に興味深い。
14:泉政文「〈世界〉と〈恋愛〉―新海誠の作品をめぐって」(黒沢清・吉見俊哉・四方田犬彦・李鳳宇編『アニメは越境する』岩波書店、2010年)


ここで驚いたのは新海作品の認識度合いが高く、かなりの数のレポートで作品を踏まえたうえで論考批判を行っていたことである。具体的な作品内容を踏まえて語るのは必要な基礎能力である。
15:受講生の最終課題講評
毎年のように受講生の皆さんが書いた最終課題を検討していったのである。
〇過去の文芸論5
文芸論5と文献リスト(2017年度)
文芸論5と文献リスト(2018年度)
文芸論5と文献リスト(2020年度)