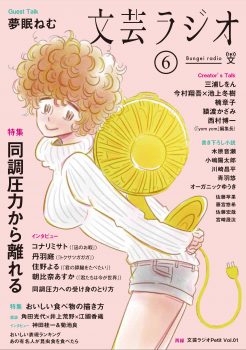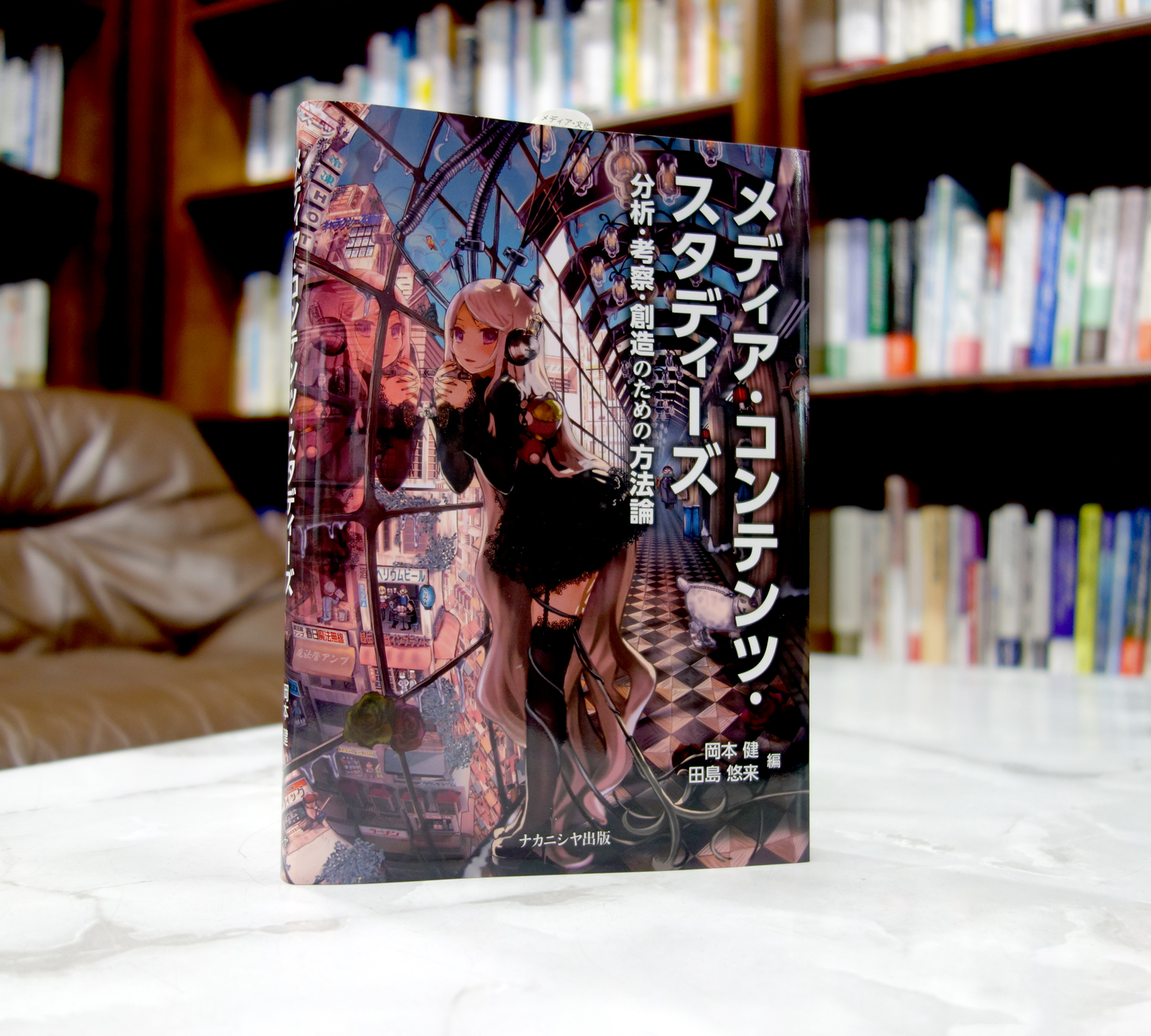Twitter はおもに仕事情報の告知にしているのだが、ときどき仕事の延長で思ったことを呟くことがある。7月上旬に、ある新人賞の下読みで経験したことを呟いた。
▼新人賞の下読みで、これは最終候補に残るだろう、いや、間違いなく受賞するかもと思って上にあげたら、「すでに電子書籍になっているので外します」と編集者から連絡があった。電子書籍にしたものを応募するなよ。応募するなら本になっていないものを。本にするのは落ちた後でいいではないか。残念。
僕が世話役をつとめる「山形小説家・ライター講座」や「せんだい文学塾」、教えている東北芸術工科大学や非常勤の宮城学院女子大学の創作の授業でも普通に話をしている情報だが、これがなぜかバズった。7月12日に投稿して、30日段階でリツイート数662、いいね数836。その後も増えているのかもしれないが、ともかくはじめてバズるというものを経験した。
で、いいねやリツイートをする人をみていると、作家志望者が多い。そうか、彼らは知らないのかと思った。山形や仙台の講座や大学に来てくれたらいくらでも教える(教えている)のだが、そうもいかないだろう。だったら、講座や大学でいっていることを連続ツイートしようかなと思って、新人賞に関するツイートを投入した。その数16本。以下に、まとめてみます。
▼公募の新人賞・文学賞の原稿は基本的に「未発表作品」。だから不特定多数の目にふれた作品(紙&電子書籍)はNG。投稿サイトに掲載されたものもNG(OKとするところもある)。ただし閉じられたサークル(小説家講座、何々教室など)での発表作品はOK。不特定多数の目にふれてないから。
▼電子書籍を賞の候補から外すのは当然だが、某新人賞の2次選考に上がった(最終候補ではない)という理由で落とす賞も増えてきた。かつては問題なかったが、誰もが検索できる時代では、A賞の2次通過作品がB賞の候補になっていると格好が悪い。編集部が完全な新作を求める傾向にもあるけれど。
▼2)応募者もその辺の検索事情を知っていて、別の賞に名前と作品名をかえて応募してくる。で、見つからないかというと見つかるのである。僕も他の評論家もそうだが、みな賞の下読みを複数している。「あ、これ某賞の下読みで読みましたね」と気づく。編集者に伝えて、その作品はボツになる。
▼最終候補作を決める予選会議(評論家と編集者の合同会議が多い)で一度も最終候補にならない書き手の話で盛り上がるときがある。みな複数の賞の下読みをしているから“常連” に詳しい。あの人は毎回同じ書き方で丁寧だけど面白くない、書く方法を変え、題材を別にすればいいのに、なんて話になる。
▼2)力はある、でも孤独に書いているし、あまり本を読まないからレベルアップしない。で、A賞で落ちたらB賞、B賞で落ちたらC賞、C賞で落ちたらD賞と送り先をかえるだけ。ABCD賞の下読みをやっている評論家たちの話題になるだけ。山形や仙台講座に来てくれたら詳しく書き方を教えるのに。
▼文学賞の下読み(一次または二次選考)・予選委員(最終候補作を選ぶ)をしていると「運」を考える。最終候補作が決まった後に問題(二重投稿など)が発覚してボツに。代わりに一作上にあげるのだが、こんなものをあげても選考委員は推さないだろうと思ったものが受賞作となったりする。過去に二回。
▼2)でも、そういう作家が意外と化けたりするから面白い。編集者としかと向かい合い、相手のいうことをきちんと聞き、書き直しにも何回も応じて仕上げるからだろう。運というものが、実は、その人の性格によって生かされるものであることがわかる。名前はいわないが、直木賞作家にもなった。
▼3)毎回予選委員が強く推しても賞をとれない最終候補作家もいる。何回も受賞できないと迷走して、受賞できるような作品を狙ってくる。でも大抵はつまらない。個性をなくした作品で逆に最終候補にあげられない。他賞を狙っても賞がとれない。実力はあるのに腐り、そのうち消えてしまう。
▼文学賞をとったもののフェイドアウトした人が、昔の栄光を求めてまた文学賞に応募してくる。元受賞作家たちが彷徨っている。でも賞をとって2、3作で消えた作家は伸びない。書けないからだ。編集者の要求に応えられない。元作家にはハンデをつける。よほどの傑作でなければ最終候補に辿りつけない。
▼いくら中身がよくても書き出しが悪ければ「作家は冒頭の1行で読者に見捨てられる運命にある」(打海文三)。それをもじるなら「新人賞の応募原稿は冒頭の20頁で判断される運命にある」。冒頭が退屈な原稿の9割は凡作。書き方を心得ている者は冒頭から惹きつける。その考えがないのは全くの素人。
▼新人賞の応募作で「これは三部作の第一部です」と記す人がいるが、作品が完成しているときは記さないほうがいい。三部作の第一部とは要するに「この原稿は完成していない」と選ぶ側は考える(そして落とす)。構想を語る新人の小説に傑作なし、と経験上いえる。未完成の作品がほとんどだから。
▼1作を後生大事にして各賞に送るのも困るが、毎年ではなく毎賞ごと新作を送りつける書き手も困る。新作が次々に書けるのはいいのだが、すべて薄味。作者の個性がなく、何でも(薄く)書けることをアピールしてどうする? 何でも書けることよりも、このジャンルは自分が一番だと思わせる傑作を書け。
▼A賞の落選作を書き直してB賞に送るのはいい。100枚削るのもいい。でもストーリーを改変していないなら書き直したとはいわない。それは同じ原稿。100枚削れるならもっと削れるかも。80枚の短篇ネタを400枚書いてくる応募者が実に多い。短篇ネタなのか長篇ネタなのかを考えてほしい。
▼大学の授業で逢坂剛『水中眼鏡(ゴーグル)の女』をテキストにした。大評判。『ミステリーの書き方』(日本推理作家協会編、幻冬舎文庫)で作者が語っているようにB・S・バリンジャーの作品のトリックを使ったものだが、ミスリードを含めて実に巧みではるかに劇的。特に脇役が誤導に効果を発揮している。
▼2)RTした山下達郎の言葉ではないが、詞・曲はもちろん大事だが、編曲も大事。逢坂剛「どんでん返し--いかに読者を誤導するのか」(『ミステリーの書き方』所収)でも語られているが、トリックの引き出し、またはジャンルの結合の仕方に新しさがある。逢坂さんの作品はいつも新鮮で驚きがある。
▼応募作の原稿の中に手紙が同封されていることがある。手紙を開くと大抵写真。全員女性の応募者なのだが、顔写真どころか水着写真だったりもする。なぜか背景がホテルの廊下だったり(何を考えてるの?)。いうまでもないが、小説を選ぶのであって顔は選ばない。水着になる暇があったら推敲しなさい。
以上の16本もけっこう話題になり、いいねやリツイートされた。そうなると作家志望者の期待に応えたい気持ちが出てきて、わりと積極的に、芸工大の授業内容についても言及するようになった。その辺の話も、いずれ、まとめて記載したいと思う。