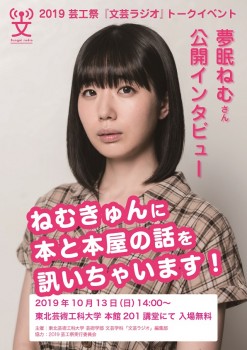森田季節さんの『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』(GAノベル)のアニメ化が発表された。まことにめでたい。
- 公式サイト
https://ga.sbcr.jp/sp/slime/index.html - タイトルが長いことをいじられているニュース
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1910/19/news015.html
その森田季節さんと毎年夏に集中講義を行っているのだが、この夏も例年のごとく行われた。森田さんのブログを見るとお分かりだと思うが、旅好きの森田さんは旅をしながら山形に来られ、旅をしながら山形から帰られたのであった。
授業は受講生個々人に合わせた内容にしているので、大枠は一緒でも一人ひとりではまったく違う取り組みになっている。そのため初日から最終日まで毎日のように全員の面談を行い、その日の課題を出していくことになる。受講者数がその年により違うため、面談時間は固定ではないが、それでも教員側からすると一日のほとんどが面談に費やされ、提出された課題を持って帰り、夜に読むということになる。それなりにハードである。
とはいえ個々人に向けたバラバラの内容というわけでもなく、大枠としては「ライトノベルを書くこと」が授業目的として設定されている。そのうえで今年はその日の授業のスタート時に玉井と森田さんとの対談を行うことにした。対談というより一方的に玉井が森田さんに聞いていくという形式が多かったような気もするが、さておき「現役のラノベ作家がこれまで(特に学生時代に)どのようなものを読んで、吸収してきたのか」、「学生のときは何をどれだけ書いていたのか」、「その後、プロとして何に取り組んできたのか」、「そして今、考えていることは何か」という点を重点的に聞いていった。
毎日のように話題をかえて喋っていったのだが、これら連日の内容はすべて「本を読み、小説を書く」に帰結していく。「小説を書く」というのは、文字通りの意味以上はないのだが、書かないとレベルアップも何もしないので課題のときだけ書くのではなく、日ごろから取り組みなさいということになる(先生っぽい内容である)。問題は「本を読む」のほうだ。単に漫然と受け身のまま読書をするだけではダメで、それをどのようにして能動的にアプトプットに変換していくのかが問われていく。いや、もちろん漫然と文章を書いても意味はないので読書だけの問題ではないのは確かだが、文章を書くという行為はそれ自体が否応もなく能動的にならざるをえない。それに対し、物語を受容することは、下手したらただひたすら読者としての自らの位置づけを変化させることないまま読み続けることが可能となってしまう。
そこで授業では森田さんが書かれた短編作品を読んでもらい、玉井が解説をしていく中で体感してもらうという手法を取ってみた。そう。ここで問題となるのは作者本人を前にして、作品解説をしていくのだ。自分が。玉井が。批評であったり評論であったり研究であったりするのは、作者自身の考えやテーマが作品に反映されていれば、それをくみ取って考えていくことになるが(そしてくみ取らなくても良いのだが)、それだけで成り立つものではない。研究などの文脈の中で、作品がどう位置づけられて、それをどの切り口で語っていくのかは、作者の立ち位置というよりは評者自身の立ち位置が求められていくことになる。
授業で取り上げた作品は森田季節さんの「まどろみは遠く、遠く彼女を運ぶ」(『切望小説。』所収)である。この作品はいわゆる百合小説と呼ばれるもので、そこからイメージされる通り耽美的であり、静寂な雰囲気は物語全体を覆うものとなっている。さらにこの作品のもう一つの特徴はポストアポカリプス的な側面で、耽美的な要素に退廃的な要素をも追加しているところである。単なる架空の世界をそのまま描くと、当然ながら読者とは違う百合物語という世界観に彩られてしまうのだが、現実世界との地続き状態を維持するためにポストアポカリプス的要素は一役買っている。現実世界に存在する土地や概念、事物が文明が滅びたあとにも残り続け、登場人物たちにというよりは読者に対して語りかける。この二つの要素により物語の完成度が一気に高まっており、SF的な百合小説として評価することができるのではないだろうか。みたいな話をした気がする(あまり覚えていないが)。
ここで授業として重要なのは森田さんの作品を作者や玉井がどう考えているのかではなく、受講生が何を考えるかである。物語を読むときに考えるべき点は複数存在するのだが、その一つには物語の構造を考えること、もう一つには物語の型を身につけることが創作に活かせる大きなポイントだと思う。もちろん取り上げるテーマ性など受容すべき点は多々あるのは確かだが、それは恐らく次のステップではないだろうか。物語の構造に関しては世間一般に物語論として流布しているものが多数存在するので(プロップとかキャンベルとか)一つひとつ説明するのは避けていくが、簡単にいえば主人公がどのタイミングで何を選択し、どのような行動を起こすのかということである。もちろんシステマティックに分量で切り分けていき、物語の展開を考えていくこともできるし(シド・フィールドとかを読めば何となくわかると思う)、もう少し曖昧に「序盤ではこういうことをしている」ぐらいでも構わない。とはいえ実はこれだけでは物語を生み出し、作品を書いていくことに直接的にはつながらない。
なぜなら構造をどれだけ精緻に作り上げていっても、極論では大枠でしかないし、普遍化すればするほど曖昧にならざるをえない。それはプロップやキャンベルのような古典的な物語論にも言えることで、大枠を広げれば広げるほど、どこかの要素は何かの作品に当てはまってしまうことになる。要は中身について考えていることにはならないし、普遍化すればするほど個々の作品に活用する意義が失われていく。
そのために内容の型を身につけることも考えたほうがいい。これは読書論の視点からいえば、ヤウスが概念化した古典的な「期待の地平」というものに近いのかもしれない。「ジャンルについての予備知識、それより前に知られた作品の形式と主題形成」(H.R.ヤウス『挑発としての文学史』岩波現代文庫、2001年)などから読者に対象作品への「期待の地平」が形成され、作品はその「期待の地平」をこえていかなければならない。授業で森田さんの作品を取り上げたときに、比較対象として話に挙げられたのは宮澤伊織さんの『裏世界ピクニック』シリーズであった。これは百合小説としての単純な対比でしかないのだが、森田さんの作品と宮澤さんの作品を比べるだけで同じ百合小説というジャンルではまとまらないということがわかると思う。
森田さんの作品は百合という耽美性を率直に打ち出し、そこにポストアポカリプスの退廃性を付与しているのに対し、宮澤さんの作品はネットロアの捜索という直接的な物語の目的を設定した上で、そこに取り組む二人の女性のバディものというキャラクター構造を取っている。百合小説という枠組みではあるが、そこで描かれている作品はここまで違うのは、「期待の地平」として想定しうる「あるあるネタ」を多様性ある中からセレクトして描き出していき、さらにそこから読者の期待をきちんと裏切っていくことにより浮かび上がってくる。
創作者として取り組むのであれば、単に小説を受動的に読むのではなく、「期待の地平」を認識するために様々なものを吸収し、「期待の地平」を乗り越えるためにやはり様々なものを吸収しなければならない。
ということを思いながら、今年の夏の集中講義をしたような気がするが、とにかく暑かったことが一番印象深い。