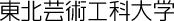入試課ブログ
煙発生
美術棟から道路を挟んで・・
学生が囲む中、煙がもうもうと・・・
(真ん中の後ろ姿は学芸員課程の後々田先生と洋画の松田先生だけどね)
これは北野先生の実験考古学研究法の授業です。
北野先生といえば・・・歴史遺産学科ブログ
弥生式と
縄文式。
途中温度を測ったりしてます。
朝まで降った雨の影響で条件はかなり悪かったそうです。
●お知らせ
▽金属工芸ワークショップ『銀のペンダントを作ろう!』
本学美術科工芸コース卒業生の川勝節子さん(H12年度卒業)と
本学工芸コースの在学生6人が講師を務めます。
ジュリーはジュリーでも
こちらは昨日の画像。
建築・環境デザイン学科の2年生のジュリー。
ジュリー?
ま、わかりやすく言えば「講評会」というわけですが。
(建築・環境デザインといえば「ヤマガタ蔵プロジェクト」。
蔵プロについては後日の特集をお楽しみに。いつにしよ~かな~)
今回は「木造住宅の設計」。
いま真ん中で図面を見ているのは元倉先生。
座っているのは相羽先生。
模型を前のテーブルに、図面を壁に貼って進めます。
まだ2年生だから・・・というよりは、
もう2年生なんだから、と思うことの方が多いんだけど、
「人前で発表する」「プレゼンテーションをする」ということに対しての
意識が低いように感じるんだよね。
以前ブログに書いた生産デザイン学科2年生の授業では直接2年生の学生さんに話をしたんだけど、
「誰に話をしているのか」というのがすっかり抜けていて、
「先生に説明する」ということしか考えてない人が多い。
目の前にはたくさんの学生がいるのに、先生にしか意識がないのが残念。
(知っている人しかいないという緊張感のなさもあるのかもしれないが)
あとは話し方。
どういう話を展開をすればうまく伝えられるのか、ってちゃんと考えてんの?
という人が多い気がするんだなぁ。
後ろまでなんて全然聞こえない人とかね。
文系や理系の大学に比べて、「多くの人の前で話をする」という機会は、
美術系デザイン系の大学の方が実は多いのよ。
そうであるならば、その機会をうまく使って自分の考えをより理解してもらえるような話し方、プレゼンの仕方というものを意識して欲しいと思うし、自ら勉強して欲しいと思うんだがどうよ。
少なくともあと1年で就職活動を迎える2年生には考えて欲しいと思うなぁ。
以上、芸工生へのお小言。
カレンダー
カテゴリー
- AO入試
- オープンキャンパス
- ここでしか読めない入試情報
- ぼやきとつぶやき
- 今から始める就職活動講座
- 今日のTUAD
- 入学予定者の方へ
- 入試課から
- 受験生からの質問
- 在学生による入試アドバイス
- 大学祭ライブ
- 未分類