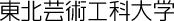入試課ブログ
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その3
蔵ツアーの魅力
司会
その後はどんな展開をしてきたのでしょう。
山畑
最初の試みが成功したことで、「うちの蔵も活用していきたい」「どうしたらいいんだろう」 という相談が舞い込むようになりました。 そこで、2004年は市内に点在する5つの蔵に呼びかけてイベント「蔵ネット」を仕掛けました。
[蔵ネットでの左官体験。初めての壁塗りを体験]
蔵プロとして面的な展開をすれば相乗効果が出るのではないかという考えからです。 オビハチさんではドキュメンタリー映画の上映、香味庵まるはちさんでは小学生対象のワークショップ、ギャラリー卿自楽さんでは木地玩具のイベント、のむらやさんでは落語会、文庸蔵さんでは本の展示、そして山銀本店さんでは古道具ポスター展……。市内の蔵マップも作って配布しました。ただ、メインの5軒は地理的にちょっと離れていたので、思惑どおりの賑わいにはならなかった。それから、立地条件や蔵主さんの意向があるから、必ずしも蔵オビハチのような展開ができるとは限らないとわかりました。
一方、一般の参加者を募って蔵を見学する「蔵ツアー」を始めました。蔵ツアーは毎回盛況です。なんといっても、よそのお宅の蔵の中を覗けるのがいい (笑)。 普段はよほど親しい近所の人だって蔵の中なんて見せてもらえませんからね。
竹内
わくわくして面白いよね。
司会
最近の活動はいかがですか。
山畑
今年2006年6月には、太田三郎さんという切手を素材とするアーティストを呼んで「おのや」さんでアーティスト・イン・レジデンスを展開しました。 一週間にわたって蔵を制作場所とし、 蔵をテーマに作品を制作していただきました。 また、 趣味で絵を描いていて、 蔵を増築してちゃんとしたギャラリーにしたいという蔵主さんがいて、 まさに今それを形にするギャラリープロジェクトが進行中です。
竹内
蔵プロとは別に進んでいた話なんですが、相談を持ち掛けられたことから、学生がどんどん提案していったんです。私たちが思っている以上に学生たちと蔵主さんは仲がいいですよ。大学のキャンパスでは触れ合えないような方たちと親しく話ができたり、一緒に考えながら活動できている。 当初より地味ではあるけれど、人的なつながりという点では大きなうねりが生まれている。蔵プロでの接触がきっかけとなって、町では確実に何かが始まろうとしているんです。
山畑
ただし、一番怖いのは学生の甘えです。大人の社会から見たら許されないことをやってしまった場合、「君らのやっていることは間違っているぞ」 ときちんと叱ってくださる方もいますが、 全員にそんな優しさを期待してはいけません。 そのあたり、 学生たちはきちんと心してかからないと。
司会
学生たちは次々と卒業していきますが、蔵プロはうまく続いています。 理念がきちんと継承されているんですね。
山畑
学生たちは放っておいても勝手に動いて、毎年独自の試みに挑戦しています。 不思議なことにちゃんとリーダーが登場して自然に世代交代しているんですよ。 ただ、フリーペーパーやウェブでの情報発信、それから人気のある蔵ツアーなど、誰もがわかる蔵プロの柱となる活動は続けていくべきですよね。そのうえで、今年の学生たちがめざすのはこれです、 と打ち出していくといい。
司会
毎年、 蔵が一つ一つ自立していく姿がイメージできますが。
山畑
いや、そこは頭の痛いところです。なぜなら、蔵が自立していく速度より、蔵がなくなっていく速度のほうがずっと速いんですよ。もっと何とかできないかという思いは常にありますね。
竹内
私たちは必ずしも山形全部の蔵を蔵プロに巻き込もうとは思っていません。 蔵を使った飲食店でも洋服屋さんでも、 いろんな形態の営業があっていい。 オーナーさんが蔵に価値を見出して、 使うことによって保存ができて、 なおかつ地域の人に親しまれながら営業していける蔵がたくさんあれば、 街全体にとって非常に好ましいと思っています。
・・・その4へつづく
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その2
蔵オビハチとの出会い
司会
最初、カフェ空間として蔵を提供してくださったのは、オビハチという屋号を持つ小嶋商事の小嶋正八郎さんでした。メインストリートから一本入った道路に位置していますね。なぜこの蔵に着目したのでしょう。
山畑
もともと屋敷の裏手にひっそり建っていた荷蔵なんですが、道路整備によって敷地が分断され、蔵が道路に面することになった。小嶋さんご自身、この機会に蔵を何とか利用できないかと思案していたという背景がありました。小嶋さんは屋根を修繕し、上下水道のインフラを整えて、道路に面する部分に漆喰を塗って、その先の学生たちができるところは何でも造作していいよといってくださったんです。
僕らがまず取りかかったのは大掃除。 初日は市民グループ 「まちづくラー」 が率先して手伝ってくれた。 次にカフェとして必要な厨房を作ったり、 トイレにペンキを塗ったりという作業に取りかかりました。トイレの施工や什器の製作は山形県長井市にある山形工科短期大学の学生が担当してくれました。実際に図面を書いてものを作るという経験のない学生が取り組んだので、それ自体も面白かったようです。 ただ、図面が読めない学生もたくさんいたから大変だった。
竹内
学生の設計図をもとに椅子を作ってみると、できあがったのはとてもじゃないが座れない(笑)。お金がないから自分たちで手を掛けるしかなくて、トライアンドエラーをくり返したんですよ。一つ一つ丁寧にやるしかないので、余計なことまで手が回らない。余計なことができない状況が功を奏したんです。いい雰囲気のカフェができたのは、そのおかげですよ。
山畑
学生たちは最後の方は相当疲労困憊していたけれど、三週間の営業で什器の材料費くらいは賄える収益がありました。身びいきではなく、芸工大の学生ってすごいなあと感じ入りましたね。 一人の学生がそれぞれネットワークを持っているんですよ。 陶芸を専攻する友人がコーヒーカップを作り、 彫刻を学ぶ学生は鉄製の照明器具を作った。グラフィックデザインを学ぶ学生はロゴマークや暖簾を作ってくれた。建築専攻の学生とは違う視点からカフェづくりにどんどん参加してくれたんです。大人との繋がりもあったので、プロとして活躍しているミュージシャンを呼んでジャズライブをしたり。学園祭とは違う、普通に町中の「みんなの行きたい場所」になっていましたよね。

[「ヤマガタ蔵プロジェクト」ポスター]
竹内
学生は学生なりに、蔵主さんは蔵主さんなりに「何かができる」という実感を得たんです。小嶋さんはこの試みの後、さらに蔵に手を加えて 「蔵オビハチ(灯蔵)」として営業を始めました。音楽ライブやアートの展覧会もするなど、持続した空間として自立しています。
・・・その3へつづく
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ
ここ2ヶ月ほど引っ張り続けてきた「ヤマガタ蔵プロジェクト」に関するご紹介。
年末年始にブログが全く更新されないのもせつないので、この蔵プロジェクトに関する記事を中心にできるだけ更新する予定です。
えぇ、あくまでも予定。
ちなみにこの記事は、東北文化研究センターが発行している東北文化友の会 会報誌「まんだら」に掲載された内容です。
———————————————————————
明治時代、二度の大火に見舞われた山形市の商家では、伝統的な耐火建築である蔵がさかんに建てられました。土壁を厚く塗って開口部を最小限におさえた蔵は、現在でも市内に約400、中心市街地だけでも150あまり建っていますが、老朽化や道路整備の影響などにより、次々と取り壊されているのが現状です。東北芸術工科大学の学生が中心となった「ヤマガタ蔵プロジェクト」 は、町から消えつつある蔵を地域資源として有効に活用し、中心市街地に活気を取り戻そうという主旨で、 2003年にスタートしました。その継続的な活動は、 2005年には日本都市計画家協会賞の「学生まちづくり部門賞」を受賞しています。日本の町づくりにおいては、 もはや大きく新しい建物を建てることではなく、すでにある古い建物を掘り起こし、新たな資源として再生させることが鍵となっているのです。 今回は、プロジェクトの発足当初より学生を支え、建築の視点から深く関わってきた本学の山畑信博助教授と竹内昌義助教授が語り合います。司会はプロジェクトへの参加経験を持つ東北文化研究センターの飯田恭子研究員です。
蔵プロジェクト、 始動
司会
ヤマガタ蔵プロジェクト(以下、蔵プロ)は2003年から、東北芸術工科大学の学生たちが中心となって展開してきました。皮切りは、荷蔵を改修してオープンした期間限定の 「オビハチ」でした。 私も蔵の隣の空き地にこしらえたかまどで、ドイツケーキを焼いたりしました。 後に「オビハチ」 はオーナーさんの経営によってカフェ・レストラン 「蔵オビハチ (灯蔵)」として営業を始め、今に至っています。 それまで眠っていた建物が、使うことによって息を吹き返した、保全された例ですね。
山形には中心市街地だけでも150の蔵が残っているそうですが、これほど多くの蔵があるとは地元でも意外と知られていません。お二人はなぜ蔵に着目したのでしょう。 蔵プロの誕生経緯についてお聞かせください。
山畑
まず前段があるんです。 1994年、山形市の委託事業によって芸工大の環境デザイン学科が市内の建造物の調査をした際、土壁と漆喰で作られた蔵の存在が大きく浮かび上がりました。山形市内には明治・大正に建てられた蔵が数多く残っていることが改めて明らかになったんです。
2000年には山形県・山形市・芸工大が連携して、地域社会とアートを結びつける「環境アート推進協議会」が発足し、そのとき、蔵でアーティスト・イン・レジデンスの活動をしてはどうかと企画しました。そこで翌年、追調査をしてみると、前回洗い出したもの以外にもあること、そして環境アートや蔵の利活用に興味を示す蔵主さんが多いことがわかりました。 ただ、蔵の総数はだいぶ減っていましたね。
司会
蔵プロへの伏線があったわけですね。
山畑
そんなとき、卒業研究のテーマで悩んでいた学生に、蔵をテーマに研究したらどうかとアドバイスしたんです。彼女は東京生まれで、山形で初めて蔵に触れた。そして、その空間自体に新鮮な衝撃を受けた。机上の提案だけでなく、蔵を活用して何かしてみたいという強い思いがわき上がってきたようです。
建物をリノベーション(改築・改修)して新しい空間を創るには独自の方法論があると思ってはいたのですが、明確に説明できなかった。学生と何度も話しているうちに、じゃあ実際の空間を作ってやってみようとなったわけです。すると、いろんな学生たちが集まってきました。その中にカフェをやってみたいという学生がいたので、プロジェクトの核として取り上げました。
竹内
そのあたりから私は建築デザイナーという立場で関わるようになりました。いったい何ができるのか、何をやったら面白いのか。そんな模索をしつつ、蔵プロが始動しました。常々、山形という地だからこそできる建築の実験をしたいと思っていたんですが、このとき私は、何かを始めるときに必要なのは潤沢な資金ではなく、素直な思いとか地道に手や体を動かすことだと学生たちに気づかされました。
司会
そんななかで気になるのは、最近、蔵がどんどん姿を消していることです。 それについてはいかがですか。
山畑
急激に減ってきたのはここ一〇年ですね。近郊に続々と大型店舗ができるのと比例するように、町中の空き店舗が増加して居住人口が減り、中心市街地が空洞化していった。道路整備事業の影響もありました。ところが、今度は中心市街地整備改善活性化法が施行されて、山形市もこの基本計画を提出したので、逆に郊外に店舗を出しにくいという状況になっています。 現存する蔵を活用することによって中心市街地に元気を取り戻し、蔵の消失を食い止めることができるかもしれません。
竹内
すでに郊外へと向かっている流れをこれから止めるのは至難の業だと思うんですが、中心に戻ってきたい人と、現存する蔵をどう結びつけて、人を呼び込むか。そんな観点からも蔵プロがお手伝いできたらと考えています。
・・・その2へつづく
大学事務局は12/28~1/4までお休みをいただきます。
入試課ブログも2度目の年越しを迎えます。
山形市はこのままだと雪なしの年越しかな?
大学事務局は、12/28(木)~1/4(木)の間、年末年始の休業となります。
お電話やメールでの入試に関するお問い合わせ、願書等の資料請求受付も上記期間中はお休みです。
休業期間中にいただいたお問い合わせや資料請求には、1/5(金)以降、順次対応させていただきます。
でも、このブログはちょっとネタをためこんでいるので、休業期間中もできるだけ更新するつもり。
っていうより、記事はもう準備できていて「公開」ボタンをポチッと押すだけにしてるので、年末年始も入試課ブログを見てちょ。
年末年始用にネタを投下。
○↓メディア・コンテンツデザイン学科未来デザイン学系サイトが更新されとります
http://www.future-design-johokeikaku.jp/index.htm
○2005年度大学院洋画修了 佐藤さんの作品が「ART-SCHOOL12月リリースシングル・ジャケットデザインコンクール」にて約1000点応募の中から1点選ばれ、「ART-SCHOOL」ニューアルバム「テュペロ・ハニー」2006年12月20日発売のCDジャケットに採用。
http://www.art-school.net/dis_single.html
○MUJI AWARD 01・良品大賞にて銅賞受賞
プロダクトデザイン学科3年生5名とプロダクトデザイン学科助手によるグループ「5+2」の作品「SORI 少し反った画鋲」が、株式会社良品計画主催の「MUJI AWARD 01・良品大賞」で「銅賞」を受賞。
2006年11月23日~2007年1月9日まで、無印良品有楽町店内Atelier MUJIにて受賞
作品展を開催。また、2007年のイタリア・ミラノサローネにて展示発表を予定。
http://www.muji.net/award/results.html
そいではみなさま、よいお年を。
ついに本番!
毎年恒例「柳川杯」。
(なんで「柳川杯」か、っていうと、主催してくださっているのが体育の柳川先生だからなのよ)
バリボー大会です。
学科・コースやサークルや友達どうしなどでチームを作って参加したのが24チーム。
入学前なのに講評会
先々週のことになってしまうけど、日本画コースAO入試ですでに合格が決まっている方々の「入学前課題講評会」が大学で開催されました。
早い時期に合格が決まってしまうAO合格者に対してモチベーションをしっかりたもってもらうとともに、スキルアップをはかってもらうことが目的です。
はじめに岡村先生から日本画コースの先生紹介がありました。
各人に対して課題が与えられていたので、それを個別講評です。
この辺は普通の授業ともう変わらない感じ。
その後ちょうど行われていた大学院1年レビューを岡村先生の解説で見学し、
アトリエ見学のついでに3年生課題の古典模写を見たり。
最後に1年生の授業「動物制作研究会」に混じって
芸工日本画授業の生の雰囲気を味わいました。
ってわけでオチも特にないレポートでした。
さて、のだめ見ようっと。
他学科の授業
一般入試・センター利用入試の願書で頭を悩ませている方もいるかと思いますが、
入試相談会などで説明すると
「え! そうなんですか!!」
とよく言われることがあるんだが、
「美術科の洋画に入ってもデザインの授業とか受けられるよ」
って言うとね、驚かれるんだなぁ。
(主に講義系の科目をとることができます。各学科コース必修となる「専門演習」を他学科の学生がとることはできません)
「入学した学科の勉強しかできないんだと思ってました」 と返ってくるのね。
大学は専門学校じゃないから、大学内にいる人間としてはそれが普通だと思ってるけど、高校生や受験生だとそこまで理解するのはまだ難しいよね。
そういう授業は、「※全学対象科目」という扱いになってます。
これは先週の「共通演習(日本的造形)a」という授業。
(この授業は厳密にいうと美術科の授業、というわけではなくて、学科関係なく誰でもとれる授業としてあらかじめ設定されている、と言った方がいいか)
↑のリンク先にも「※全学対象科目」という文字が見えると思います。
担当されている日本画の谷先生に伺ったところ、「日本画コース以外の学生が7割ですね」とのこと。
だから、彫刻や工芸など美術科他コースの学生はもちろん、歴史遺産やグラフィック、建築・環境の学生だって、この授業で日本画に取り組むことができるわけです、「全学対象」ですから。
ちなみにこの授業は日本画コースのアトリエではなく、本館2階の205演習室で行われています。
バス BUS
某知り合い
「あのさ~、あんたの顔を見てるとあの人を思い出すんだよねぇ~」
このブログを書いてる人
「え? だれ? (こいけてっぺーか?つまぶきくんか?ワクワク)」
某知り合い 「あれだよ、あれ。 ジャガー横田のダンナ」
こんにちは、入試課ブログです。
今年は降りませんな~、雪。
昨年の12月は異常に降ったけど、
天気予報を見ると今年中に積もることはなさそうな感じ。
今日の、じゃなくて19日火曜日の記事↓
ラッピング循環バス、子どもらの絵描き発車・東北芸工大[山形新聞]
子供が描いた芸術バス[朝日新聞]
こどもたちや保護者の方、在学生、大学関係者、
取材に来ていただいたマスコミ各社のみなさんがバスプールに集合です。
記事内にもあったけど↓がこどもたちのバス。
幼児教育士さんがこどもたちに説明してくれてます。
サプライズだよねぇ、こどもたちには知らされてなかったんだから。
もちろん在学生もいろいろとお手伝いをしてくれました。
兄弟バス♪
みんなで楽しそうに乗り込んで行きましたよ。
キヤノン株式会社 プレゼンテーション~ビジュアルデザイン系~
二日続けて会社説明会のレポート。
今日はキヤノン株式会社さんのプロダクトデザイン/ヒューマンインターフェイス系説明会に続いて、ビジュアルデザイン系の説明会。
「キヤノンってデジカメとかプリンタとかを作ってる会社なのに・・・
グラフィックを勉強した人がキヤノンに行ってどんな仕事するっていうのよ!」
とね、この間言われたのです、グラフの2年生に。
いやいや、その認識では困るのだよ。
この就職ガイダンスのときに映像コースの4年生が言ってた通りですよ。
・芸工生は、大学で勉強していることを直接活かしたい、という人が多い。
でも、活かす方法はいろいろとあるのに、それを知ろうとしない。
知らないままでは企業や業界を理解することもできない。
2年生に言うのはちょいと厳しいがね。
今回はビジュアルデザイン室のお仕事の詳細についてご説明いただきました。
新入社員の方の一日を追ったVTRなどからは、大変ながらも非常にやりがいを持って仕事に取り組まれている様子を見てとることができました。
さて、そのビジュアルデザイン室の仕事とは・・・
代表的なものとしては、様々な製品のパッケージデザインやパンフレット、広告などがあげられます。
実際にデザインされた実物を手に取りながら、そのデザインに至る現場の声を聞かせていただきました。
学生からは、デザイナーの皆さんを「鋭いですねー。」と唸らせるような質問も出ていました。
最後に、学生が持参したポートフォリオを講評いただきました。
企業の方にご覧頂くのが初めての経験で恥ずかしかったのか、緊張したのか、始めは出し惜しみしている学生もいましたが(そういうところがウチの大学らしいというか、可愛げがあるというか)、持って来ていた学生はみんな見ていただきました!
自分の力がどれくらいあるのか、
芸工の力がどれくらいあるのか、
芸工が他の大学出身者に比べて弱点となっているのはどこか、
逆に芸工出身の強みはどこなのか、
それをもとに自分は何をしなければならないのか、
何をすればもっと力がつくのか。
ってね、みんな結構考えてると思うのだよ、学生って。
それが客観的にわかるのは、やっぱり就職活動やデザイン実習に飛び込むことなんだな。
こればかりは経験をしなけりゃわからん。
そういうもんですよ。
動いたもん勝ち。
入試も同じでしょう。
模試を受けるから自分のポジションがわかる。
予備校に行ってみて自分のスキルレベルがわかる。
だからさ、大学入試は倍率あっても20倍とか30倍とかだったりでしょ。
就職活動って100倍とか200倍なんてザラよ。
1000人応募して1人しか採用されないなんて普通だよ。
なのにさ、
「就職する、っていうイメージが湧かない」 とか
「え~何からはじめたらいいかわかんない」 とか
のん気なことを言っている学生を見ると心配になるのだよ、おじさんは。
スズキ株式会社 会社説明会
ウインターセミナーにご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。
美術科日本画↓ 岡村先生講評中
美術科洋画↓ 木原先生講評中
ごめん、その他の学科・コースは撮る余裕がなかったよ。。。
土曜日はウインターセミナーのほかに学内でイベントをやってまして、一日中立ちっぱなし歩きっぱなしだったもんで足がパンパンだったんですよ。
そこで日曜は朝から足もみマッサージ+角質除去へ。
60分で3500円。
その足もみにはよく行ってるし、自ら望んで行ったとはいえ、
∑( ̄[] ̄;)!ホエー!!
あまりの痛さに変な声が次々と出る・・・
声にならない声も・・・
こんにちは、入試課ブログです。
さて、今日は足もみが本題ではなく。。。
先日大学で行われたスズキの会社説明会の様子を。
スズキ株式会社といえばバイクなどの二輪車やワゴンRなどの四輪車など、街やテレビでもみなさんご存知の企業だと思います。
今回は、デザインを担当されている春日さま、大西さまと、本学生産デザイン学科卒業生でスズキで頑張っている小木曽さんにお越しいただきました。
前回のキヤノンさんに続いて卒業生が母校での会社説明会に登場です。
大変充実した資料と現場のナマのお話をうかがうことができ、、様々な角度から理解を深めることができました。
また、学生が持参したスケッチを丁寧に講評していただき、質問にも温かく接していただきましたよ。
さらに、
実車の「セルボ」を見せていただくなど、本当に充実した説明会。
もうこれまでココで何度も書いてきましたが、こういったチャンスは逃さず使うべし。
カレンダー
カテゴリー
- AO入試
- オープンキャンパス
- ここでしか読めない入試情報
- ぼやきとつぶやき
- 今から始める就職活動講座
- 今日のTUAD
- 入学予定者の方へ
- 入試課から
- 受験生からの質問
- 在学生による入試アドバイス
- 大学祭ライブ
- 未分類