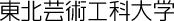入試課ブログ
衝撃の展開?
いやぁ~涙しました。
選手権の決勝で東北のチームが優勝するなんて・・・
クラブユース全盛の時代とはいえ、選手権の優勝というのはメディアに載るボリュームが大きいのでインパクトは相当強いですよ。
盛岡商業ほんとに頑張りました。
さて、今日から授業も再開。
今週・来週と授業があって、今月下旬には期末試験です。
学生は制作とレポートに追われる日々・・・
年末年始の時点でレポートに追われている人もいるようですが。
入試課は、入試の準備ですでにアタタフタタし始めています。
すでに願書を提出された方、受験票は大学からまだ発送していませんので、
もうしばらくお待ちくださいませ。
そんななか(←ASAYAN風にどぞ)
「すいませ~ん」
って事務局カウンターへ私を呼びにグラフィックデザインの1年生が。
「私が撮るビデオに出演して欲しいんですけど・・・」
「え? いつ??」
「いまです」
って、いまかよっっっ。
1階の廊下へ連行される。。。
「中に何着てますか??」
(見せつつ)「え、コレ着てるよ」
「とりあえず、脱いでください」
エ---------------ッ
しかもとりあえずかよっ! この後どんな衝撃の展開が待ってるんだよ!
というわけで上着を1枚脱がされて脱いでの撮影。。。
(話広げすぎだな・・・)
その後、着々と自分の撮影をして


「ありがとうございました~♪」って。
これはこの授業のビデオ体験「3分間映像日記」です。
昨年も誰かの作品に出演した記憶があるんだけど・・・
こっから私信
「あと3週間弱。。。」あーさまへ
コメントいただきました。が、内容的に載せないほうがいいかと思って(笑)
みんな同じように不安だから。情報流しているコチラとしても「これは余計不安にさせるんじゃなかろうか」といつも自問自答しながら書いてるのよ。いまやってることに自信を持って!
狙い目かもしれない
こんにちは、くまだまさしです入試課ブログです。
昨日も仙台を街ブラしてました。
爆弾低気圧?のおかげで雨はすごいし風もすごいし。
でもバーゲンだから人多いね。
某百貨店の催事場でやってる「大阪うまいもの食いだおれフェア」をのぞく。
「ほら、おにいちゃん食べてって」
次々と試食が目の前に出てきて角煮、たこ、梅干、あおさ、わらび餅・・・あと何食ったっけ?
とりあえず、「みっくすじゅーちゅ」のバナナ味は微妙・・・
その後宮崎あおいのポスターが欲しくてコンタクトを買いにコンタクトやさんへ行く途中、名掛丁のあたりでかな?偶然歩いてたうちの学生に会いました。
(あ、卒業生が店長やってる店に行くの忘れた!今度行くわ)
俺の顔見てそんなに気まずそうな顔しなくてもいいべよ。。。
ま、山形だとどんな店に行ってもうちの学生がバイトしてたりするから
遭遇確率はものすごくアップするわけだが。
さてさて、一般入試(前期)・センター利用入試(前期:1科目利用)の出願期間は15日まで。
金曜までで1割くらい届いてるかな。出願状況はまた後日。
いまの出願状況だとセンター利用入試(前期:1科目利用)は狙い目になる可能性が。。。
一般入試(前期)には出したけど、センター利用入試(前期:1科目利用)には出してない、という人が結構多いよ。ほんと思ってたより。学科・コースを問わず。
いまから出てくるのか、いまいち受験の仕組みを私たちが伝え切れていないのか。
「センター1科目+芸工の論述・実技系試験」というパターンは、今年がはじめての導入なわけですが、募集定員もきっちりとあるわけだし、一般入試を論述・実技系試験で受験する方で、センター試験も受ける人は出しておいて損しないと思われるので考えてみてね(ちなみに受験料は1万5千円)。
あけおめことよろ。
こどしも入試課ブログばよろしぐおねがいしてけろな~
こどしはさっぱりゆぎなくてよぉ~
ねんまづちぇっとふたみだいなんだげんどよ、東京さいだっけもんだがらどだなふうに降ったのっだがさっぱりわがらねんだず。浅草さいってでぎだばっかりの人形焼ばくたらんまいったらんまいったら。
==========これ以上書くと解読不能になるっぽいので山形弁終了================
まだ日陰には少し雪が残ってますが。。。
新年早々山形で高校の同級生と男祭り。
帰りに7時11時で山形では有名なラーメン店のカップラを購入して食す。
けど・・・微妙。やっぱりカップラはカップラだな。
今年も「お年玉」という行事により、財布の中から俺の漱石や俺の諭吉が強奪される。
みなさんはこの年末年始をいかがお過ごしになりましたか?
本屋に立ち読みに行って、ちりんちりん盗まれたりしてませんか?
自分的なこの年末年始一番の話題は・・・
「大相撲この1年」に閣下が出演していたことだな。
あ、年末年始も触れていただきありがとうございます。
何かお送りしましょうか?
「広報の手羽 さま」宛で届きますかね??
「入試課ブログ」もスタートして1年10ヶ月目に突入。
今年もだいたい毎日更新を目指そう。
いや目指したい、ので「入試課ブログ」をよろしくお願いします。
(とかなんとか書いてますが、年賀状を書き終えて出したのは今日の朝だったりする・・・基本的にナマケモノなのです・・・すんません・・・)
そーいえば年末に日本画の岡村先生から「そろそろ更新するからぁ」と言われてたんだっけ・・・
岡村桂三郎のひとりごと[ART ACCESS]
8日は各地で成人式が。
成人代表のあいさつをする学生の方、がんばってね~
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その7
オビハチの蔵再生 談/小嶋正八郎
その6までの対談に登場した、ヤマガタ蔵プロジェクトのカフェ「オビハチ」は、蔵のオーナーである小嶋正八郎さんのご協力なしには実現できない試みでした。 学生たちの実験の場であった「オビハチ」はその後、小嶋さん経営のカフェ・レストラン 「蔵オビハチ(灯蔵)」 として生まれ変わり、山形市内の人々に強い印象を与えました。小嶋さんにお話を伺います。
商家としての小嶋家のルーツは江戸時代末期に遡ります。本家は総合商社のような商売をしていましたが、明治になると取り扱い商品ごとに暖簾分けをし、オビサン、オビロクといった屋号を持つ分家がたくさん生まれました。「オビ」 は商人が締める角帯のこと。明治42年、私の祖父は分家してこの十日町にやって来てオビハチを名乗り、肥料や米、雑穀を商い始めました。蔵プロの舞台となったこの蔵は、 商品を貯蔵しておく荷蔵でした。
私が物心ついたとき、すでにこの蔵は荷蔵としての役目を終え、単なる物置となっていました。覚えているのは外壁に空襲を避けるための黒い墨が塗ってあったのと、悪さをすると蔵の中の柱に縛り付けられて閉じこめられたこと(笑)。今となれば懐かしいですが、小さい頃の蔵は恐ろしい場所でした。いま89歳の母も店に改造してからはファンになったんですが、以前はいいイメージは持っていなかったようです。暗くて何が入っているのかよくわからない。いったん調べだしたら際限がないような気がして、手が付けられない。そんな存在でした。
平成に入り、敷地の中に道路が通るという計画が持ち上がったときから、蔵をどうすべきか思い悩むようになりました。そうしている間に道路ができて、屋敷の裏に隠れていた蔵が表に出てきた。外壁はボロボロだし雨漏りもする。あきらめて壊そうという気持ちが強くなったとき、東北芸術工科大大学院生の井手理恵さんと知り合ったんです。井手さんは研究テーマである蔵を使い、何か実践してみたいというささやかな夢を持っていました。最初は私も真剣に取り合わなかったのですが、よく話してみると非常に熱意を持っている。そこで 「蔵をプロジェクトの柱であるカフェ空間に提供してみよう」 と決めました。蔵を取り壊すにしても数百万円かかると聞いていましたから、「壊す」という後ろ向きの考えを「作る」という前向きの発想に転換しようと思ったんです。そのあたりから芸工大の山畑信博先生や竹内昌義先生が加わって、市民グループ「まちづくラー」も入ってきました。タイミングよくいろんな思いが同時に動き出したんです。
私の負担で屋根を葺き替え、外壁を直し、トイレを作るところまで造作しました。掃除や内装は学生やまちづくラーに頑張ってもらいました。物置でしたからいろんなものが出てきましたよ。私が捨てるつもりだったものの中には、学生たちが持ち帰ったものもあります。持ち主にとっては珍しくもなく価値を感じないものでも、若い学生の目には新鮮に映るものがたくさんあったんです。それがなかったら、蔵はこんなふうに生き続けることもありませんでした。
「オビハチ」として3週間カフェを開業している間、私は出張などがない限り毎日お客として顔を出していました。事業家としては、人がどんどんやって来るのを見て「うまくいくかもしれない」と直感しました。 何より、マスコミが敏感に反応して報道してくれる。こうした事業は時流に乗りそうだ、本格的に営業してみようと決心しました。開業にあたっては、さらに資金を投入して改修しました。世間に熱があるうちに営業を始めたかったので工期は一カ月と決めて、素速くオープンしたんです。テーブルは母や祖母が嫁入りのときに持ってきた長持です。壁のポスターは、荷蔵に入っていたものを学生が写真に撮って作ってくれたもの。オビハチのロゴマークも学生が作ってくれました。
現在、お客様の七割は女性です。女性は男性のようにお付き合いで店を選ぶことは少なくて、 本当に好きな場所にしか行かないですよね。居心地がよいと感じてくださっているんじゃないでしょうか。こうして開業できて本当によかった。実をいうと、私があまりさっさと決めたものだから家内や娘からの風当たりは強かったんですが、今では応援してくれています。
ギャラリーもジャズライブもやる。ランチもあれば、ワインや焼酎もある。「品目を絞ったらどうか」とアドバイスしてくださる方もいるんですが、荷蔵はがらんとした空間だからこそ何でもできるんですよ。仮に完成された立派な座敷蔵だったら、提供するものは和風の雰囲気に合ったものに限られるでしょう。最初に、学生はジャズライブや落語、トークイベントなどいろいろな実験をしてくれて、何をやってもそれなりに楽しくて様になることが実証されました。 何も限定しない空間なんてほかにあまりないんじゃないでしょうか。事業として発展途上にあるのは承知の上ですが、 この形態でもうしばらく続けてみるつもりです。
[蔵オビハチの店内。古いものと新しいものがうまくマッチしている]
【この企画は今回でおわり】
明日からは通常営業しまっする。
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その6
蔵が持つ素材の力
司会
山畑先生は風土と建築をテーマにした研究をされてきました。世界中の建物をご覧になってきた観点から、蔵プロジェクトはどんな意味を持っているのでしょう。また、建築デザイナーとしてスタジオを持っている竹内先生にとってはいかがですか。
山畑
いろんな国の古い町を訪ねて、日本の町と最も違うなと感じるのは、素材の持つ力です。その素材で町全体の合意がなされているとでもいったらいいでしょうか。日本の町はインターナショナルな工業製品がいろいろ入ってきていますが、僕が興味を持つのは、地場の素材を使いながら、よく見ると新しいものも導入している建物なんです。
山形におそらく唯一残された、素材に力のある建物が、蔵なんです。蔵は磨けば磨いただけの美しさが出る建物です。古いものだけだと閉塞的になりがちなので、そこに若い人の新しいアイディアや、蔵主さんの思い、地域の人たちの思いが込められると、蔵は確実に再生していくでしょう。
竹内
よくヨーロッパでも観光客でごったがえしている町がありますよね。でも、健全な町の姿とはそうではなくて、地元の人がよく行くパン屋さんやギャラリーがあって、そこに観光客も行って楽しめる、そんなバランスのとれた町だと思います。 蔵プロがめざすのはそんな町づくりです。
建築デザインとは、与条件に応じて創り上げるものだとすると、新しいものを作るときと古いものを改築するときとの考え方に大きな区別はないんです。大切なのは、与条件に沿って何が必要で、そのために何をしなくてはいけないか。だから新しい建築をデザインするのも古い蔵を改築するのも、私の中では連続した考えなんですよ。蔵プロジェクトで面白いのは、古いものをつかって新しい価値観を作ること。 記憶の蓄積は後から追いかけてできるものではないから、記憶が蓄積された蔵の持つ価値は非常に大きい。私は残せる蔵は残すべきだと思うけれども、保存運動をやっているつもりはないんです。
蔵プロについてはもうひとつ、教員として関わることの面白さを実感しました。製図にはグラフィカルな能力を試されますが、蔵で人と相対して何かをしていくとなると、製図能力とはまったく異なる側面から学生の人格を見ることができる。この学生はこういう人なんだという新鮮な発見がありました。蔵プロの活動には、 相手とどうやって関係性を築き上げるか、いわゆる人間力がはっきり表れます。 外の方たちに育ててもらう部分が見て取れて、すごく興味深い。蔵プロに関わった経験は、 きっと将来どこかで役に立つでしょうね。
[オビハチで開催された蔵ネットジャズライブ]
司会
では最後に、これからの蔵プロジェクトについてお聞かせください。
山畑
願わくは、一般市民の方にもっと企画面で参加していただいて、芸工大単独ではなくて山形市の活動として広げていきたいですね。実際、当初は多くの市民の方々も参加していたんですよ。その運営方法は僕や竹内さんで考えていくことです。 具体的には「蔵座敷に泊まろう」という企画も考えています。蔵座敷は内部の造作に非常に手間が掛かっています。よい材質を使って、大工さんが技巧を凝らして作っている。ぜひこうした建築をみなさんに見てほしい。難しいかも知れないけれど、いつかは蔵座敷がネットワーク化されて市内に点在する民宿のようなものになるといいですね。
竹内
山形には本当に素晴らしい蔵座敷がたくさん残っていますよ。今すぐ活用できなくても、蔵主さんが壊さずに持っていてくれさえすればいいんです。私たちがこんなに蔵、蔵というのは、蔵がおそらく二度と作られない建造物だからです。蔵主さんはよく「その貴重さはわかっているけれど、維持が大変だから、自分が悪役になって潰すんだ」とおっしゃる。それもわからないことはない。でも、それよりも蔵を持っていることによって派生する価値について考えていただけたらいいなと思います。
蔵主さんあってのプロジェクトですから、蔵主さんが残そうという気になることが重要です。だから私からお願いしたいのは、たとえば蔵ツアーに参加した人がそこの蔵主さんに「いい蔵ですね」とか「こんな蔵があってうらやましい」とか、 とにかく蔵主さんが「わざわざ見に来てくれてありがとう」と喜んでくださるような言葉を一声かけてほしいということです。
司会
保存活用というだけでなく、新しい価値を見出し、新しい使い方を提案しながら新しい場所づくりをしているという点で非常に興味深いお話でした。どうもありがとうございました。
・・・その7へつづく
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その5
蔵が生む町歩きの楽しさ
司会
山形の蔵は通りから奥まったところにある場合が多いからこそ、郊外では体験できない歩いていく楽しみがあります。町歩きの楽しさと蔵の存在を、中心市街地の活性化問題と合わせて考えることができるのではないでしょうか。
竹内
中心市街地では住んでいる人の高齢化が進んでいます。高齢者向けマンションやコンビニエンスストアができる計画もあるようです。高齢者にとってコンビニは便利かもしれないけれど、とりたてて行きたい場所であるとは思えない。中心市街地の問題を語る際にはつい商業的な賑わいにばかり目が向きがちですが、むしろ街の中に人が行きたくなる場所をどれだけ持っているかの方が大事になってきますよ。その場所は誰が作るのかというと、 町の住人たちです。
何でも揃う郊外の大型店での買い物で満足している人たちは、もはや買い物のためだけに町中に来ることはない。したがって、中心市街地の店が郊外の商業施設と同じことをやっても勝ち目はない。郊外店舗には消費するものなら何だってあるけれど、 大人が満足できる雰囲気のいい空間はなかなかありません。大人が何に魅力を感じているかを突き詰めて考えると、蔵には大きな可能性があるといえます。
司会
子供を対象としたワークショップも開催していますが、 子供たちの反応はどうでしょう。
竹内
郊外のファーストフード店で満足している子供たちが蔵に来たらつまらないかというと、 そうでもないんですよ。「へえ、昔の建物なんだ」「ここにあるモノは何なの」なんて会話が成り立っています。利便性を追求して現在の暮らしができあがってきた文脈というか、自分たちの生活史を自然に理解できる場所なんですね。
[珍しそうに蔵を見つめる女の子。「蔵ネット蔵体験ワークショップ2」にて]
山畑
顧問として参加した山形県建設業協会の青年部でまとめた提言書があります。 そこには歩行者専用のフットパスや遺跡を結びつけて歩ける町にしようという内容も盛り込まれています。点在する蔵を繋ぎながら何か仕掛けると、歩いて楽しい、郊外の全国チェーンの店舗にはない、山形ならではの空間が生まれるでしょうね。
[蔵ネット蔵体験ワークショップにて。芸工生とこどもたち]
・・・その6へつづく
ヤマガタ蔵プロジェクトのゆくえ その4
取り壊されるその前に
司会
ところで、 山形の蔵には何か特徴がありますか。
山畑
それが面白いんですよ。江戸文化の系譜である店蔵と、北前船と最上川舟運によってもたらされた上方文化の蔵座敷が、この山形の地で交流しているんです。これは、二十数年前に山形県が行った調査報告書にも記載されています。全国的に地域づくりに生かしているのは店蔵が多いですが、山形では敷地の奥にある蔵座敷や荷蔵が多い。店蔵だともともと通りに面しているから使いやすいのに比べ、蔵座敷や荷蔵は道路に面していない。商用への転用が難しいのはそのためです。
蔵が数多く残っているのは、幸運にも山形市では大地震や水害が少なかったからです。江戸の文化も京都の文化も入ってきてる全国的にも珍しい町ですから、住人自身が買い物でもお茶でも十分楽しめる町になるといいですよね。それが結果として、町に観光客を呼ぶきっかけとなれば……。
竹内
蔵座敷は生活の場であり、昔は冠婚葬祭の場でもあった。それだけに、蔵座敷に今でも暮らしているおばあちゃんが亡くなったときどうするかがターニングポイントとなります。蔵主さんの選択としては、維持費も大変だし、処分して駐車場にしてしまおうとなりがちです。蔵座敷はこうやって敷地の裏手にひっそりと建ってひっそりと消えていくから、地元の人たちも意外とその存在に気が付かない。 とにかく建物の維持費は間違いなくネックとなっていますね。
司会
蔵を地域文化資源と考えるならば、行政がある程度の維持費を負担すべきという考えもあるのではないでしょうか。山形県金山町のように、町で産する金山杉を使った金山型住宅を建てると補助金が下りる例もあります。
山畑
行政が明確に蔵という私的財産を公共的に価値のある建造物とみなして、 保存するという強い意志があれば可能でしょう。ただ、現在の厳しい税収のなかでの実現は難しいかもしれません。
竹内
蔵の維持で最も経費が嵩むのは外壁。漆喰の補修です。屋根の多くは金属葺きですから、建築から数十年もたつと葺き換える必要が出てくる。せめて蔵に関する固定資産税を減免するなどの措置があれば、保存状況はだいぶ違ってくると思いますよ。
だけど、保存するには行政の対応を待つよりも、蔵主さんが「うちに蔵があるのはいいことだ」と誇りを持つ方が確実です。もともと蔵はステイタスの象徴だったんですよ。なのに、維持費の問題などがネガティブに捉えられて、厄介者のようになっています。これでは仮に補助制度があったとしても、めんどうな手続きをして補助金をもらうよりも壊した方が簡単だとなって、いずれはすべての蔵が取り壊される運命となります。
山畑
景観法や登録文化財での優遇措置を利用するという方法もあります。登録文化財になると固定資産税が減免されます。築後50年たつと登録条件の一つを満たすので、 おそらく山形市内にも登録できる蔵があるはずですよ。
竹内
蔵のある町並み景観や蔵を利用したお店の雰囲気が楽しめれば、一般の人たちも蔵がある町に住んでいるという誇りが生まれるでしょう。すると、蔵は個人の所有物でありながら共有財産となる。町にそんなキャパシティがあってもいいと思います。
司会
きちんと手入れをするとして、 蔵の耐用年数はどれくらいなのでしょう。
竹内
程度によります。左官屋さんによると、メンテナンスのための手入れと、綺麗にするための手入れは根本的に違うのだそうです。もとの姿に戻して綺麗にするには1000万円単位の金額が必要だけど、メンテナンス目的ならそれほどでもない。重ね塗が必要でない程度の痛み具合なら、負担も軽くて済む。つまり、どれくらいお金を掛けるのかは、その空間をどう使うかによるんです。蔵オビハチも正面の漆喰を塗って屋根を葺く補修に留めたおかげで、歩けば床がギシギシ鳴るという古さがいい具合の、たまらなく味のある空間となった。こんなふうに、まず蔵主さん自身が蔵の魅力に気づきさえすれば、私たちも使い方や保全のための提案やお手伝いができます。
山畑
意外だったのは、若い人が「古いのがいいね」といってくれたこと。蔵主さんが最も気づいていないところを若い人たちが評価した。でも、ただ古いだけじゃだめです。手入れされて丁寧に掃除されるなど、大切にされていることがすごく大事。そんなに難しい話ではないでしょう。ふつうに新しい建物を綺麗にしてるのと同じことですからね。
・・・その5へつづく
カレンダー
カテゴリー
- AO入試
- オープンキャンパス
- ここでしか読めない入試情報
- ぼやきとつぶやき
- 今から始める就職活動講座
- 今日のTUAD
- 入学予定者の方へ
- 入試課から
- 受験生からの質問
- 在学生による入試アドバイス
- 大学祭ライブ
- 未分類