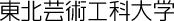入試課ブログ
うぃん
えぇ、サーティーワンでアイス買いました。。。
おもいっきし便乗商法に乗っかってます。。。
だって食べたいんだもん。。。
とある日の映像学科のスタジオ。
なんか撮影をしているっぽいですが、
もしかしてその指導をしているのは、
あら、モントリオール国際映画祭で「ヴィヨンの妻」にて最優秀監督賞を受賞した根岸先生じゃないですかぁ。
いや、これ実は授業風景じゃないんだけどさ(笑)
そんな根岸先生、本学と連携している映画館山形フォーラムで
「ヴィヨンの妻」の舞台あいさつをされます!
根岸吉太郎監督 舞台挨拶&トークショー付上映[山形フォーラム]
山形新聞でも紹介されています。
根岸監督、11月3日に舞台あいさつ 山形のフォーラムで「ヴィヨンの妻」上映後[山形新聞]
先日の試写会でのお客様からのコメントは↓
http://forum-movie.net/villon/
ハロウィンだかサーフィンだか知りませんが。
こんにちは、入試課ブログです。
ハロウィンっていつからこんなに日本でもやるようになったの?
みんなね、バレンタインとかホワイトデーとかクリスマスとかハロウインとかって、
まんまと企業の戦略に乗っちゃってるだけだとは思わないかヨ!
もうね、そんな企業の便乗商法にまんまと乗っちゃって
喜んでお金を出しちゃうなんてね、おじさん信じられないヨ!!
ほんとそんな企業の便乗商法にまんまと乗る人たちに
腹が立ってこんなの買っちゃったヨ!!!
ふんべよ
なんだかあさって1日から3日まで天気が悪いそうで。
こんにちは、入試課ブログです。
ちなみに山形市の予想最高気温
11/1(日)23度→11/2(月)10度→11/3(火)7度。
7度!!!
ゆぎふんべよ。
このブログの記録によるここ2年の初雪は、
2007年が11月19日、2008年が11月20日。
山形市のここ30年の初雪平年日は11月16日らしいんだけど、
今年は早まるかもしれないのぉ。
積もったりしなきゃいいのぉ。
今の時期に積もっちゃうとスベっちゃうからねぇ。。。狩野●考みたいに
で、昨日の企画書表現演習の様子の続き。
小山先生とTUYの結城アナによるかけあいやら、
学生からの経過報告やら、
サボっているように見えるかもしれませんが話し合いやら、
話し合いやら
話し合いやら。
あ、そうそう。
なかのひとは都合でいけなかったんですが、さいとうくんがレポートしてくれています!
マンガのメンタル[総合美術コースブログ]
漫画家で、本学の映像コース(現:映像学科)卒業生の佐俣ユミさんによる講演会。
高校生から
「マンガ家になりたいんです・・・」
というのは、美大の広報が、
言葉を悪くして言えばある意味聞き飽きた言葉なのですが、そういう人って
「マンガだけ書いていたい」
って人が多い。
他に例があるとすれば、
「ゲーム作りたい」
んで、ゲームに関することだ~けやりたい。
そうなんですかねぇ???
道はイロイロあって、いろいろまわり道したから身につくものもあるんだよね~
ちなみに佐俣さん、ドキュメンタリー作品を出品されていたんですね↓
佐俣由美 監督インタビュー 自分が楽になるためにつくったもの[YIDFF2003]
マンガ家になりたいアナタ、どう思います?
とかって書くと
「芸工大でマンガ家になるには映像学科に入ればいい」
とかって勘違いする人が出てくるのが困るんだけど。
24
まで読んで、
「へぇ~2代目毛利小五郎は、どきどきキャンプがやるのかぁ」
と思ったのはなかのひとだけじゃないはずだと考えてしまってぇ・・・本当にすまないと思(略)
こんにちは、入試課ブログです。
これで、どきどきキャンプのネタに毛利小五郎が増えるってことだな。
そのうち腕時計型麻酔銃を打たれて眠らされて、10年後くらいにアメトークの一発屋芸(略)
企画構想学科の企画書表現演習。
今日は小山先生が担当します。
ちなみに今日の授業にはゲストが
テレビユー山形の結城晃一郎アナウンサー。
山形県のみなさんには、どよまんでおなじみ。
結城アナからどんな話があったかはやっぱり秘密だよなぁ~
ま、いま企画構想学科のみんなは「マルシェ・ジャポンキャラバン」山形開催に向けて取り組んでいるので、
それに関すること、とだけ書いておきますか。
つづく。
ぶーれ
すいません、すっかり忘れてました。
こんにちは、入試課ブログです。
新しいブログがはじまって紹介するの忘れてた・・・
東北芸術工科大学図書館のブログさんが、新しい仲間に入りました。
図書館ではいつもいろいろな展示がありますので、
次々と紹介してくださるものと大変期待しております(笑)
あ、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、
学生ブログも大学の「モバイルページにて」絶賛展開中です。
まぁPCからも見れるから、右下の「リンク集」から飛べるんだけどね。
(なかのひとの独断と偏見により「モバイル優先」って言っちゃったので、
まだPC用のデザインを装備させてなくってすいませぬ)
さて、
豪快にぶれておりますが、映像学科1年生の授業を。
映像学科は、映画、CM、CG、アニメーション、写真などをまずは一通り勉強します。
で、これは写真の授業。
「べろだし」の様子。
「べろだし」は、巻き終わったフィルムからネガの先を出す作業のこと。
乾燥したフィルムを見てるとこです。
これらが、写真現像の道具たち。
一番下の入れ物で、現像液やら、停止・定着液やら、要は薬剤ですが、それを作ります。
白いかごに乗っているケースにフィルムを入れて、バーテンダーっぽく現像いたします。
こちらは、「リール」。
これを使って、暗闇の中で手探りでフィルムを巻き巻きします。
巻き終わったらさっきの写真に登場した白いかごのケースに入れておくわけ。
ここは、カラー写真の暗室。
3年生以上になると、ここにこもってカラー写真の現像ができるようになりますが、1・2年生は白黒のみ。
みんな結構動いているもんで、最後までブレブレな写真でお邪魔しました。
なやみどころ
全国の大学入試担当者にとって、
今年の一番の悩みどころはなんといっても新型インフルエンザ。
こんにちは、入試課ブログです。
目前に迫った推薦入試に向けても、入試課では頭を悩ませております。
まぁうちの大学はすでにAO入試を実施していて、
そのときはマスク配布とかしたわけですが、
当時よりも確実にインフルは広まってきてますし。
近くの高校に聞いても、「1・2年は今週学年閉鎖でして」という感じだし、
うちの大学でも感染した学生が出てきています。
来年1月の大学入試センター試験では、
例年1週間後に東京・大阪だけで実施していた追試験を
2週間後に各都道府県で実施することになったり、
国立大の個別試験では本試験の1週間後に追試験を実施という方針になっていたり。
なかのひと個人の意見として、
正直なところ大学が試験当日にできることというのは非常に限られてきます。
そのため、試験当日には必ずマスクを持参してもらうなど、
受験生のみなさんにご協力をいただく必要が出てきたりします。
推薦入試受験生の方には、受験票をお送りする際に
新型インフルエンザに関する注意事項などのプリントを同封しますので、
そちらを確認して各自準備をするようにしてください。
(受験票の返送は来週以降の予定です)
そもそも、一昨年には入試直後の採点や
合否判定作業の真っ只中に季節性インフルエンザにかかって、
スタッフに多大な迷惑をかけたいっつもブログを書いている入試課の人っていうのが
ここにいたりもするんですけど。
先週の様子。
デザイン工学部1年生の共通で、絵画・デッサン(応用)の授業。
前期には「絵画・デッサン(初歩)」っていう授業もあります。
ものすっごい逆光の写真ですいませんが、この日は屋外で写生を。
宮島先生がアドバイスしてます。
っていうか、この授業には「アニメのデッサン」とか「絵コンテ」なんかもあるのね~
なんか何かの道に導いている人みたいな写真になっちゃった(笑)
最近宮島先生をとりあげすぎか。
推薦入試アドバイス その8
こんにちは、入試課ブログです。
最後の推薦入試アドバイスを。
●美術史・文化財保存修復学科
美術史・文化財保存修復学科は、「面接」が必須。
そして、「共通小論文」または「共通デッサン」のどちらかを出願時に選択です。
○AOには落ちてしまったのですが、とにかく練習あるのみだと思います。
私は面接とプレゼンテーションの練習を毎日学校で担任の先生に見てもらいながらしました。
AO受験はプレゼンテーションなど緊張もしましたが、
少しばかり成長できたような気がします。
それに、AOに落ちたあと自己推薦を受けたのですが、
AOのときに面接練習をしていたので、時間に追われることなく試験を受けることができました。
私は練習することが一番大事だと思いました。
→練習しておくことで、自分の不安が少しでもなくなるものだと思いますしね。
練習するってことは、それを見守ってくださる先生や友達、親御さんがいるということ。
たまにチクリとむかつくことを言われても(笑)、
感謝の気持ちを持つのを忘れないようにしましょうね。
○推薦などはその学部や将来のことについて興味のある事や場所などに行って
自分で調べてみるなどのことをしていると
面接などのときにとても役に立つのでやっておいた方がよい。
また、小論文などは過去問を元にして練習を重ねると良いと思う。
→「面接」で話すことができることって、基本的にはその受験生の「実体験」に基づいたものでないと
説得力がないっていうのはまぁ常なんですよ。
だから、「面接のために」何かをするというわけではないけど、
試験までの残りの時間は少ないから、
ネットを使うだけでも芸工大に関するニュースを検索してみておくとか。
知ってると知らないのでは、自分が考える幅も違うもんです。
●歴史遺産学科
歴史遺産学科も、「面接」が必須に、
「共通小論文」または「共通デッサン」のどちらかを出願時に選択です。
○自己推薦での小論文のための取り組みとして、
身の回りの伝統ある芸能・文化を調べ、
それらの未来への在り方、またどのような物として
後世の人々に伝えていけば良いかを自分なりにまとめる事で文章力を養いました。
→これもまぁ「実体験」というものですね。
ただし、うちの小論文は問題が全学共通なので、
歴史遺産学科を受験するからその領域に関係するものが出るということではありません。
もちろん「自分なりにまとめる事で文章力を養う」っていうのは必要。
○面接などの練習をスムーズにいえるまで練習して、
自分のいいたいことをしっかり伝えることが合格につながると思った。
先生にも言われたことで、本を読んだり
新聞を読んだりした方が小論文対策になると思った。
→「本を読んだり、新聞を読んだり」
よく言われます。
でも、ただ読めば対策になるってもんじゃなく、
読んで何を思ったのか、何を感じたのか、文章に起こすのか、
そこまでしなくても箇条書きだけでもしてみるのか。
残された時間が少ない中でいかに効率よく準備をするかってことで。
はろげん
朝とか超さみぃ。
こんにちは、入試課ブログです。
なかのひとの部屋は、いまんとこハロゲンのヒーターを出してます。
朝起きたらハロゲンヒーターの前で正座しながらめざましテレビを見て、
しし座の運勢があいかわらず悪いことにがっかりする毎日。
さみくてさみくて、もうそろそろハロゲンだけじゃ対応できなくなりそう。
ちなみに、誰かなかのひとのハートを、あなたのハロゲンで暖(略)
昨日は、山形県内の高校2年生が見学に来てくれました。
はじめは教室で、なかのひと+この高校の卒業生で
いま企画構想学科1年生の学生さんによるかけあい。
いま授業でやっていること、なんでこの大学に?などなど、
短い時間でしたがあれやこれやとお話をしていただきました。
高校生の反応がよいってスバラシイ。
笑ってもらえるってスバラシイ。
笑われるってスバラシイ。
それだけでやった甲斐があったってもんです。
いまって、高校生の団体見学を案内しても、高校に伺って高校生と直接話をしても
「無反応」ということもたまにあるもんで。
その後
ちょうど図書館2階でグラフィックデザイン学科中山ゼミのお仕事展が開催されていたので、
中山先生とゼミ生によるスペシャルレクチャー。
ま、スペシャルって言っても15分しか時間がなかったんだけどさ。
(中山先生&ゼミ生さん、急なお願いだったのにありがとうございました!)
で、夜は夜で
中山先生のギャラリートーク。
写真が↑しかないんすけど、
あ、コチラのブログですとより詳しい写真やお話が。
チョー先生と宮島先生によるスペシャルトークの時間と被っていたこともあって、
はじめは30人くらいの参加者でしたが、
最後には美術科やプロダクト、企画構想の学生さんらも
次々と顔を出して6~70人くらいになってましたね。
で、あさって25日は、その中山先生も審査員を務められる「デザセン」の決勝大会です!
デザセン2009決勝大会[東北芸術工科大学]
企画構想学科の小山先生が今年も審査委員長。
そして今年は脳科学者の茂木健一郎先生、
デザイナーでムサビの原研哉先生を新たに審査員としてお迎えしました。
今日は出場チームが大学入り。
今年は北海道から沖縄まで9チームが決勝大会への出場権を獲得しました。
沖縄県の与勝高校のみんなは山形の朝晩の寒さに
ハロゲンヒーターが5つくらいいるんじゃないだろか。
夕方からは出場チーム&学生スタッフによる打合せが。
学生スタッフもこの大会を支える大事な大事なメンバーです。
高校生のみなさんも、芸工生のみなさんも、ぜひ決勝大会の会場へ。
ちなみに昨年の決勝大会の様子は↓のページから
各出場校ごとに動画でご覧いただくことができます。
第15回大会入賞作品[デザセン]
▼今日の記事
再興院展山形展が開幕 多彩な119点、ファンでにぎわう[山形新聞]
→今日から山形美術館で開催されています。
今日は学長の松本先生らのギャラリートークが。
日本画の先生&学生&卒業生も多数入選しています。
なぜアーティストは貧乏なのか
いやぁ・・・刺激的でしたよ。
こんにちは、入試課ブログです。
もうね、8回裏もそうだけどね、
9回表に鉄平の2ランが出た時点で
こちらはそりゃあもうチーム名じゃないけど
この試合を楽天的に見てるわけじゃないですか。
9回裏の札幌ドーム全体の稲葉ジャンプを見たときに
「マズイなぁ・・・」
と思ったけどさ、スレッジがバットに当てた瞬間にもう
って、サヨナラ逆転満塁ホームランを打たれた話じゃなくって??
そんな話はハムファンのムサビの竹林さんと二人で話せってもんですね。
あれです、昨日行われたハンス・アビング博士による
なぜアーティストは貧乏なのかの講演。
やはり興味をそそられるタイトル。
さすがに408講義室が学生さんや先生方、また一般の方も含めギッシリでしたね。
アビング先生が書いた本は、本学非常勤講師の山本先生によって翻訳されています↓
2時間を超えた講演会。
「アーティストとして生きていくのを早くあきらめたほうがいい人もいる」
という率直な意見には、会場爆笑。
その他モロモロあったわけだけど、そのあたりは現場にいた人だけに。
面白かったのは、質疑応答の時間になってからでした。
宮島先生からの質問。
「この大学を卒業して社会の中でサバイバルしていく上で、
いま学生がやらなければいけないことは何か?」
アビング先生からは、
「大学の中に閉じこもらず、いい作品を作ったと思ったら外に売り込んでいくこと。
そして、作品の質が高いだけではなく、その作品を外に押し出していく力が必要。」
要は、自分の作品を売り込むことのできる「コミュニケーション力」を持ちましょう、という意味だと受け取りました。
で、
「同じ質の作品が並んだときには、
押し出していく力(プレゼン力だったり)を持っている人の作品が評価されるものだ」
と。
まぁ、入試課ブログで散々書いてきた内容を改めてアビング先生から聞いて安心したというか、
うちの学生さんはそこが弱いなぁと個人的には思っているから、余計心配になったというか(笑)
アビング先生から学生のみなさんに質問が投げかけられました。
「芸術大学に居て、卒業後芸術とは全く違う職業に就くことを恥ずかしいと思うか?」
この質問に答えた学生さん、立派でした!!
こればかりは、人によって意見が異なるでしょうけれども。
まぁ世の中一般的に見ても、例えば教育学部に行った人が学校の先生にならなかった場合、
「なんで教育学部行ったのに先生にならないの?」って聞かれるのが常。
それが芸術系だとなおさらだし、
「芸工大に入れて授業料も払って、
なんで大学でやってたことと全然関係ない職業に就くのよ!!」
と世の中の人がチクッと言うのも、わからなくはない。
学生自身も「自分はこれじゃないとできない、ダメ」と決め付けている傾向にある。
よく言えば、こだわりがある。
悪く言えば、視野が狭い。
アビング先生が「アートの経済は、例外的な経済である」と言っていましたが、
学生が就職していくという過程においては、
この「例外的」であることをいいわけにしている人もいるなぁと感じたり。
昨日の講演が、なにかに気づくきっかけになればいいなぁと思いました。
おわり。
芸工大のぴーちくぱー つづき
またまた、携帯メルマガとの連動企画。
こんにちは、入試課ブログです。
メルマガ担当の入試課スタッフぴーちくによる入試体験談をお送りします。
————————————–
今日から自己推薦入試の出願開始ですね。
わたしも自己推薦だったからとてつもなく懐かしい。
みなさん早めに願書を出すといち早く安心するから早く出すといいよ。
かく言う私も消印有効の本当にギリギリに送ったんで、内心かなりあせりまくりで・・・。
でも受験票が届いてほんとに良かった。
受験票用に撮った証明写真が異様にうまく撮れていたこともあるけど(笑)
そんなぴーちくは、受験の1ヵ月前に登校中になんと事故に遭いました!!!
親の車に乗っていて、後ろから追突されました。
私は後部座席で寝ていたので、全く予想できずむちうちに・・・
おかげでコルセットを巻いて、大好きな体育にも出れず、
背もたれのない予備校の丸イスがとてもきつかったのを覚えています。
でも事故に遭ったことも、裏を返せば「当たった」。
「受かった」という意識に変わり、自信満々で受験することが出来ましたよ。
受験前に我が家では子犬が生まれて、それも良い方に取ることができました。
親も受験の間待っていた車にサッカーボールが当たったそうで(笑)
どんだけうちには「当たるんだ」と(笑)
受かったなと確信したそうです(笑)
確信が当たり、私は芸工大に無事合格することができました!
受験の前日は両親と前夜祭?をしました。
しゃぶしゃぶと寿司とたらふく食べて、満腹でぐっすり寝ました。
当日は私の受験スタイルというのがなんとなくあって、ちゃんとスカートを下ろして、髪は1本!!
前髪はパッツンで。
これが定番です。
これが私の受験スタイル!
大学側としては特に服装は決まっていませんよ。
映像コース(現:映像学科)の試験内容は、
「この地図の地名から物語・伝記・伝説を考えて書きなさい」みたいなもので、その地図は月面地図でした。
まず思ったのは「月に地名があったのか!」ということ。
知らなかったよ。
アルペン山脈とか蒸気の海とかしめりの海とか。
メルヘンな地名がいっぱい!!
私は「蒸気の海」で描きました。
人と人とを重ね合わせたとき、人の色が変わる。
融合して蒸気になる様を描こうとシェイクスピアのロミオとジュリエットが頭に思い浮かび。
モンタギューとキャピュレットという家名が邪魔した2人の愛をどう貫くのか、
融合するためにピストルを使った2人の物語。
ロミオとジュリエットの他に例として、
水と油を出して、融合するために酢を使ったとか描きました。
融合したときに2人は蒸気となって消えたのです。
のような内容です(笑)
思い出すと結構覚えているものですね。
面接までの待ち時間は何をしていいのか分かりません。
控室は大きな部屋で、周りはみんなライバルなわけですからね。
絵を描いたり、本を読んだり、他の人の試験スタイルをピーコ並にチェックしたり。
待ち時間が長いとだんだん飽きてきて、正直眠くなることもあります。。。
でも、寝ちゃ駄目です!
だって一応待ち時間も試験の時間だもん。
今か今かとどきどきしながら待ってくださいね。
(映像学科は今年作品の持込なしですが)
美術予備校に通っているとき、友だちが持っていく作品のことを話していました。
作品の持込を全く考えていなかった私はかなり焦りましたよ。
高校は美術部でも美術選択でもなく書道ばっかりやっていたので、
書道と絵をどうにかくっつけようと考えたら、水墨画にたどり着きました。
さっそく本屋さんに行って、水墨画の本を購入。
本の名前は「やさしい水墨画」。
水墨画といえば、“竹”のイメージがあったので、竹を練習しました。
本に描いてあるものは片っ端から描いた、それが試験3日前のことだと思います。
面接は初めて描いた水墨画とずっと描いてきた書道を持って行き、
先生に披露しながら、ゆるやかな感じで進みました。
今考えれば、あんな下手な水墨画をよく持って行ったな、とか
思うところがいっぱいあるけど、勢いだったなと思います。
怖気づいて試験を受けるより、強気で行く気持ちが何よりも大切だなと感じました。
実際に私は芸工大を受けて落ちる気など全くなかったので、
この辺の気持ちが勝ったのかなと思います。
—————————————
ということで、かれこれ○年前の話だね。
このときなかのひとはすでに入試課スタッフになっていたので、
「月面地図」の話をされて「そんなのあったっけな~」と懐かしく。
あんちゃん
今日は宮城県内の高校で授業をいたしてまいりました。
こんにちは、入試課ブログです。
「大学の授業体験」みたいな感じで、「福祉」とか「経済」とかっていう様々な領域から、
生徒さんが自分の興味のある領域を選んで参加するっていうもの。
他の領域はみんな教授とか准教授とかが来ているのに、
芸術領域だけ教授でも准教授でもなく、
うちの学生から主な仕事が入試課ブログを書くことだと思われているちょっと三浦春馬っぽい猫背の事務局のペーペーなあんちゃんが
控室にちょこんとなんの貫禄もオーラもなく座っていて明らかに1人だけ浮いてる・・・
誰だ、
「あんちゃんか?ほんとにあんちゃんか?」
って思ったやつは。
あんちゃんだよ。
ってこのネタわかるのかな??
誰だ、
「『あんちゃん』 じゃなくて 『おんちゃん』 だろ」
って思ったやつは。
あんちゃんだよ。
教室の準備ができたとのことで、担当の先生に連れられながらおんちゃんあんちゃんはそそくさと控室を退室。
高校2年生向けに「美術って?デザインって?」という感じでの話を。
う~ん、伝わったかナァ~
何が大変って「90分」やらなきゃいけないってこと。
まぁ写真だ、動画だ、といろいろ駆使しながらお話させていただきましたが、
みんな授業が終わってから担任の先生に出さなければいけない
高校側で用意されているこの授業のプリントに書き込むのが必死で、
果たして話の内容を聞いているのか、
パワーポイントに書いてることをただ書いてるだけなのか途中不安になりましたよ。
かといっておんちゃんあんちゃんから、「メモするのヤメテー」とも言えないし。
高校の授業とかでもそうだけど、単に黒板写しただけっていうのは頭に残らないからねぇ。
後半はあえて実例を動画で見せたのでさすがに手が止まって画面を見てくれていたけど。
先生って大変だわ。
さて、今週は学内でもいろいろとイベントがあります。
まずは、明日21日(水)18:40~開催されるこのショッキングというか、
「アチャー」って感じのタイトルの講演会。
なぜアーティストは貧乏なのか[東北芸術工科大学]
オランダから「芸術経済学」を研究しているハンス・アビング博士をお迎えして開催されます。
もうね、ズキュンと突き刺さるようなタイトルですが(笑)、
でもよく読むとこう書いてあるんです。
生前わずか一点しか作品が売れなかったといわれる
オランダの画家ゴッホを例にあげるまでもなく、
優れた作品を生み出しながらも
アーティストは昔から貧乏であった、というのは
19世紀の半ばにつくられた神話にすぎません。
芸術にまつわるこのような神話と誤った情報を芸術経済学の立場から考察し、
アーティストたちに未来への明るい希望を与えようとするのが
ハンス・アビング博士の画期的な研究『なぜアーティストは貧乏なのか─芸術という例外的経済 Why are Atists Poor? The Exceptional Economics of the Arts』です。
会場は407講義室。先着250名です。
ちなみに国内で開催されるのは、うちの大学と東京芸大と大阪の国立国際美術館の3ヶ所だけ。
グラフィックデザイン学科ブログでも紹介いただいています。
で、このグラフィックデザイン学科では、今日から図書館2階で開催されている展示が。
中山ゼミのお仕事展[グラフィックデザイン学科ブログ]
あさって22日(木)の18:40-は中山ダイスケ先生によるトークショーもあるみたい。
こういうときこそチャンスですな。
案外他学科がどんな課題に取り組んでいて、どんな仕事をしているのかってわからないもの。
この機会に美術科の学生でも、建築・環境の学生でもぜひ話を聞いてみてはいかがでしょ?
同じ22日(木)の18:00からは、?徳鉉展 “Flash Back”のイベントとして、
?徳鉉先生と宮島先生によるスペシャル対談が。
?徳鉉 × 宮島達男|スペシャルトークのお知らせ[美術館大学構想室ブログ]
いやいや、いろいろあっておんちゃんあんちゃんのカラダが3つ欲しいナァ。
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
カテゴリー
- AO入試
- オープンキャンパス
- ここでしか読めない入試情報
- ぼやきとつぶやき
- 今から始める就職活動講座
- 今日のTUAD
- 入学予定者の方へ
- 入試課から
- 受験生からの質問
- 在学生による入試アドバイス
- 大学祭ライブ
- 未分類