スイカ・プロジェクト開始!

6月22日、23日に、尾花沢市の未知の駅「のり蔵」さんという不思議な個人物産館のドームハウスに、スイカをモチーフにペイントする共同プロジェクトを行います。
みなで一つの作品を社会の現場に描くということは、総合美術コース初めてです。
来週、各自がスイカの第一次図案を描いたのを検討することになりましたが、それにあたって、本物の尾花沢のスイカの成長を、大学のアトリエ近くでもまじかに見ながら、自分たちもスイカ農家の立場になるようにして栽培しながら、観察し、それを図案に反映させていく、尾花沢スイカ農園の出先的なミニ農園づくりを、雨上がりの今日、行いました。
まず、農園は、以前に、山形市卸売り市場からもらってきておいた、マグロのトロ箱です。
ここに、依頼主の藤井さんからいただいた、尾花沢の品種、祭ばやし2苗を植えます。

土は、ホームセンターから全種類の土を買ってきました。フィールドワークチームは、何でも記録です。一つ一つ、会社名、土の配合素材を、手帳に記入してから、土をあけていきました。

なんだか、それぞれの土の商品によっても、配合も色も手触りもみな違うことがわかりました。

何と、見事な土のグラデーション。全部の土を買って比べる人なんて、あまりいないですよね。まずは、土の勉強から始めました。

いやあ、あんまり、日差しが強くて。若い女性には、お肌が気になるかな? と、ビーチパラソルで、日陰をつくりながら作業を続けて…。
(スイカ柄のパラソルも、いいなあ)

完成した総合美術農園(そうびファーム)に、スイカが植えられました! ゾウさんのじょうろで水かけして、さあ、これから観察開始です。
スイカ割りができる夏を楽しみにしながら。
自分たちで、スイカの栽培も体験学習していきます。
私の教科書
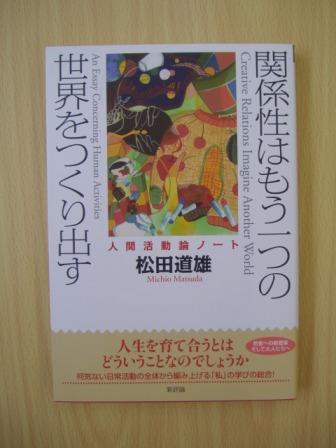
私の考えを大学生のみなさんが読んで考え、自分でも試行実践してみることができるような「教科書」としてまとめてみたのが、『関係性はもう一つの世界をつくり出す』です。
私という存在が、この世で生きることは、地球上のあらゆるモノ、人類がつくりあげてきたモノとの関わりとともに、人間どうしの関わりの総合的な営みによります。
通常、モノを相手にする原理は、工学などの理系学問が代表的です。これに対して、人を相手にする原理は、心理学などの文系学問が代表的です。
とかく、私たちは、分かれた学問をそれぞれに学んでいるように、モノと関わることと、人と関わることを、別々に分けて学んでいます。
しかし、…。実際の私たちの生活は、みな、一体として関わっています。
それらを、これまでの大学生との試みの事例なども踏まえて、まとめてみました。
総合美術コースでの私の実践は、この本が隠れた教科書になっています。読んでみたい人は、研究室「ブックカフェまつだなるど」にどうぞ。
この本の表紙の絵は、この春卒業した本学デザイン工学部生の馬飼野華恵さん。こども芸術関連の私の授業に受講した馬飼野さんが、手をあげて制作しました。
私が条件に出したのは、本の中味(私の考えをまとめたもの)を一枚の絵に、自分なりにとらえて表現してみること。
何度も、何度も、直しての作品でした。
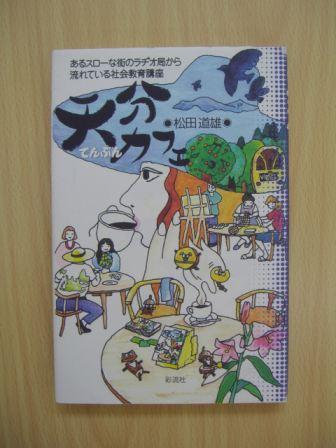
実は、この表紙づくりの先行事例があります。
この本です。この本の中味(私の創造のための想像的試論)を、表紙に1枚の絵に表現してくださいと、山形市内の独立系デザイナーに依頼しました。
この時には、表紙の絵を見せて立てることができるよう、1冊ずつのダンボールの梱包も、開いて開けて折り返すと、写真立てならぬ本立てになるよう、ダンボール会社とも試作お願いしました。
文字通り、「絵になる本」がコンセプトでした。
文字の列記だけなら、iPadで、いいでしょう。とすると、本は、これから、ますます物質としての魅力づくりも付加した本づくりが必要になることでしょう。ここにも、アートの出番はありますね。
自然が先生

昼、ちょっとだけ日向ぼっこを芝生の上でしたら、芝生に、不思議な形の小さな葉のようなものが落ちていました。

その形状を見て、すぐ連想したのは、研究室の机の上に置いていた、プラスチックの止め具です。もともと、この小さなプチ止め具が気になっていて、だれが、どんな発想から考案して、どこの会社でつくっているのか、調べようと思っていたところでした。もっと、発展応用のアイデアを考えようと思っています。

さて、この葉?はどこから落ちてきたのだろうと、上を見上げると…。

それは、例のこの1本の木です。
植物、動物、昆虫など、自然から学ぶことは、工学などの高度な研究でも行なわれています。一方で、自然体験学習の必要なども説かれていますが、その際の、「自然は大切」「自然からはいろんなことを学ぶ」ということも、あいまいでオブラートに包まれています。
市民レベルで、個々に具体的に、「自然が先生に」なって、何かを生み出すことも、まだまだ可能性の余地は膨大にあることでしょう。
最近の投稿
最近のコメント
アーカイブ
- 2014年3月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
カテゴリー
- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)
- エコキャンパス
- コトづくり(未来プロじぇくと)
- つなげる楽校
- フィールドワーク(地球ガッコウ)
- 人生勉強手帳
- 人間活動論ノート
- 未分類
- 発想する!授業
- 着想家の仕事時間
- 社会参画
- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)
- 食民芸術論







