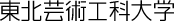被災地域文化財資料等のレスキューと保存修復 ~東洋絵画修復ゼミの活動~ 報告2
昨年12月に、美術史・文化財保存修復学科(以下、美文学科)東洋絵画修復ゼミで行った、3.11の震災で津波被害に遭った石巻市個人所蔵の扁額(へんがく)、屏風(びょうぶ)の20点の保存と修復の活動について報告致しました。少々時間が経過してしまいましたが、今回はその続きで第2回目の報告です。
1. 企画展「レスキューの先へ~被災した扁額と屏風の修復と保存~」のこと
2012年12月20日(木)~22日(土)に、東洋絵画修復ゼミの4年生が保存修復を行った被災した作品について広く知ってもらうため、東北芸術工科大学図書館スタジオ144で企画展を開催しました。21日(金)には会場で講演会も行いました。年末の3日間という短い期間でしたが、来場者には大変関心を持って観て頂きました。所蔵者の方も石巻からお越し頂き、とても感慨深く作品をご覧になっていたのが印象的でした。学生たちと共に、当時の状況などを伺い、改めて震災の悲惨さを痛感しました。
講演会は、12月21日(金)午後の1時間に渡って、3名で以下の内容を発表しました。
○「歴史を守り、震災を伝える土蔵―石巻市本間家土蔵のレスキュー活動―」
東北大学災害科学国際研究所助教 蛯名裕一
○「被災した扁額と屏風の保存と 修復について」
東北芸術工科大学 美術史・文化財保存修復学科 准教授 三浦功美子
○「扁額「満盞流霞」の修復について」
東北芸術工科大学 美術史・文化財保存修復学科 東洋絵画修復ゼミ4年 棚橋美沙希
東北大の蝦名さんには、NPO法人宮城歴史資料保全ネットワークの活動の歴史資料レスキューについてお話をして頂きました。4年生の棚橋さんは、本格修復をした扁額作品について、三浦は20点の作品の保存と修復の概要についての報告をしました。
平日の午後にも拘わらず、学生だけでなく一般の方々も聞きに来ていて、関心の高いことがわかりました。
2. 保存処置の続きと修復の経過のこと
報告1は、19点の保存処置についての内容でした。
洗浄や裏打ちなどの保存処置をした作品の中で、扁額装だった12点は、ブック型マットに装着しました。
ブック型マットは、版画作品などを額装にするときに使われているマウント方法です。
素材も中性ボードを使用しているので、保存性もあります。このまま額縁に入れれば、飾ることもできます。中性ボードのケースに収納しました。保存性と取り扱い易さを考慮した形にしました。

作品をブック型マットに装着をしている。
ブック型マットは、ウィンドゥマットとベースマットの2枚を一体化したパネル。ベースマットの方へ、作品を付けて固定して、ウィンドウマットを被せて、作品だけが見える形になる。このまま額縁に入れて飾れる。
本格修復を行い仕立て直しました作品「満盛流霞」について。
○作品「満盛流霞」概要
形状:扁額装(へんがくそう)
組成:絹本墨字
作者名:日下部鳴鶴
寸法:修復前 額全体 縦544㎜×横2240㎜
本紙 縦410㎜×横1958㎜
修復後 額全体 縦530㎜×横2223㎜
本紙 縦410㎜×横1953㎜
縁(へり):金箔地台紙
本紙は絹地に力強い墨の文字が書かれています。本紙の周りには金箔地の台紙が貼ってあります。扁額は横の長さが2mを超えるかなりの大きさです。
被災による水染み、塩の結晶の痕、パルプ屑の付着、破れなどの損傷があります。
本紙とボロボロになっている金箔地台紙を修復しました。額装のパネルと漆塗りの額縁を新調しました。また、以前は本紙を保護するためのグレージング(ガラス板もしくはアクリル板)が入っていなかったのですが、今回の修復では大気や光から護るために紫外線カットアクリル板を付けることにしました。
本紙と金箔台紙の処置は、写真撮影、状態調査、扁額からの本紙と台紙の取り外し、本紙表面に付着しているパルプ屑などの除去や墨の剥落止め、洗浄、旧裏打紙を剥がし、新たに2層の裏打ちを行い、補強をしました。
新しく作成した下張りパネルに貼り込んで額装に仕立てました。約23工程を行い修復と額装の仕立てが終了しました。
扁額などの日本の伝統的な額装の構造は、「額縁」と「パネル装」からできています。パネル装は、骨組子(木の骨組)に何層もの和紙が貼り重なっています。和紙の層は工程ごとに違う方法で貼ってあり、これを「下張り」といいます。丁寧な下張りですと7~8層の和紙でできています。その表面に本紙を貼ります。
下張りの役割は、パネル自体に強度を持たせることです。紙の層によって、温湿度の変化による骨と本紙の伸縮の差を吸収して、本紙にストレスなどを与えないようになっています。
作品に使用した材料(紙、額縁、マット、接着剤など)は、将来にわたって作品の保存性を維持できるものを選択しています。
震災から救助された作品です。長く後世に伝えていくためにも、適切な保存や修復を行うことを心掛けて、学生たちと行ってきました。
1. 所蔵者に納品をしたこと
3月12日(火)に震災から2年経って、ようやく所蔵者にお返しすることができました。
東洋絵画修復ゼミ4年生5名が、約1年半をかけて、扁額・屏風の修復と保存を、卒業研究も兼ねて行いました。
学生たちは3年進級にしてゼミに所属するとすぐに、被災作品の状態調査が始まり、戸惑いもあり大変だったと思います。それでも、しっかりと作品に向き合い、保存と修復を行ってきました。1年半の間でとても頼もしくなり、卒業して行きます。
また、作品が所蔵者に戻ることで、地域の文化遺産を通じて復興の一助となれることを心より願っております。
最後に、当大学文化財保存修復研究センターの先生方、研究員、NPO法人宮城歴史資料保全ネットワークの皆様、たくさんの方々にご協力を賜りました。そして何よりも美術史・文化財保存修復学科の学生たちが頑張ってくれました。
今回の扁額と屏風の保存修復と企画展開催は、当大学東北復興支援機構TRSOの2012年度学科等企画による復興支援活動にかかる助成事業として行いました。
深く感謝申し上げます。
そして、東北の1日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。
美術史・文化財保存修復学科 准教授 三浦功美子
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 5月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
最近の投稿
アーカイブ
- 2019年5月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年10月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年2月
- 2017年10月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年8月
- 2015年6月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月