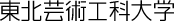2年生の演習~立体保存修復演習2~
こんにちは、2年生のYです。
今日は立体保存修復演習2をご紹介します!
この授業では、仏像が座っている蓮の台座のうちの1枚である、蓮弁を彫っています。
一人一枚の蓮弁を彫り、最後に葺くと、1つの台座が完成するのです。
歴代の先輩方が彫った蓮弁は、今も飾られています。
文化財保存修復センターの4階でいつも授業をしています。
4階は広いのでのびのびと場所を使えて良いですね(^O^)
木を彫るためには、まず道具の仕立てが必要です!
道具を仕立てた上でなければ良い作品を彫ることは出来ません。
本来のみ研ぎは、それだけで修得するのに数年かかると言われるものです。
道具を仕立てたら、彫り始めます!
適当に「蓮弁っぽいもの」を彫るのではなく、一人一人が資料を探してきて参考にする蓮弁を決めています。
修復には、美術史的な観点も必要なんですね。資料集めも怠ってはいけません。
ちなみに、ほぼ全員の参考作品が違うため、他の人の蓮弁を見てもあんまり参考になりません!
まさに、自分との闘いなのです!(笑)
2月には全員の蓮弁が完成し、歴代の先輩方の蓮華座に仲間入りします♪
いつか皆様の前にお目見えする日がくるかと思いますので、可愛がってやってください(*^_^*)
野菜
こんにちは。立体ゼミです。
12月に入って一気に寒さが厳しくなりましたね。本当に寒くて寒くて、辛い日々を送っています。
立体のゼミ室は吹き抜けなので暖かい空気が上へ上へ、、、
作品のために温湿度に気を配らなければいけない時期ですね。冬だけでなく年中気を配っていますけどね。
そんな寒い中、野菜が登場。
小さい大根が可愛いです。
先輩方が美形のオクラを選定していました。楽しそうでしたが、最終的には「美形のオクラなんてわからない。」とのことでした。
美形のオクラは別に食べるわけではありません。(もしかしたら食べるかもしれませんが)
何に使うのかと言えば、型を取るために使います。
やったことがない人が多く、それならやってみようと前々から話していたことが実現しました。
石膏やデグプリント(歯医者さんで歯型取るのに使ったりするやつです。ミントの香り。)などなど、色々なものを使って型をとります。
美文学科は作品を作る学科ではありませんが、作品の作られ方を知っているのと知らないのとでは違いますからね。
なんでも試してみるのが勉強になります。とか偉そうに書きますが私は作業をのんびり見学していました。見るのも勉強になるんです、、、
身動きの取れないオクラ
出来上がった野菜はせっかくなので補彩の練習に使用される予定になっています。
どんなふうに出来上がるのか楽しみです。
2年生の演習~日本美術史演習~
こんにちは、2年生のYです!
今日は2年生の授業の中から、日本美術史演習をご紹介します。
日本美術史演習では、先生と5人の愉快な生徒たちでアットホームな雰囲気で授業をしています♪
それでは突然ですがここで問題です!
これはなんと読むでしょう?
縦に伸びた「m」ではありませんよ。
答えは・・・・
「つ」!!
漢字の「川」を崩した変体仮名です。
変体仮名は、漢字を崩して作られた仮名文字で、平安時代から明治の初めまで日本で使われていたものです。
この授業の前半では、この変体仮名を用いて書かれた『大和名所図会』という作品を読んでいます。
題名の通り、絵がとっても綺麗な作品なのですが・・・
こーんな、文字しかないページもあったり・・・・
(というか、文字だけのページがほとんどなんです・・・)
文章の流れから文字を判断したり、変体仮名一覧表と照らし合わせながら四苦八苦しています。
読めなくて途中で詰まってしまうと、長坂先生から「これは○っていう字だろう?」
というお助けが入るので、変体仮名初心者の私たちでもなんとか読み進められています。
難しそうに見えるかもしれませんが、
「これを1ページ読み切った時の達成感は何物にも代えがたい!!」
・・・と思えるようになってきました。感覚が麻痺してきているのでしょうか?笑
変体仮名は日常生活では殆ど使わないものですが、展覧会に行って
巻物や古文書が少しでも読めたりすると楽しいですよ!
みなさんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか?(^^♪
修士1年生研究レビュー開催
カレンダー
最近の投稿
アーカイブ
- 2019年5月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年10月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年2月
- 2017年10月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年8月
- 2015年6月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月