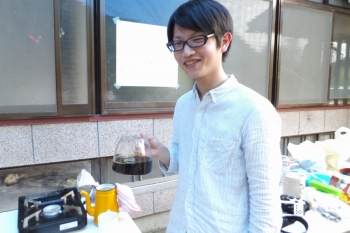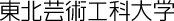弟子入計画
大学の裏に住んでいる百姓のおじいさん、岡崎さん。
茶さじや竹箒、縄を綯って素敵なかごバックを作ったり、とても器用な手しごとをされます。
手に職をつけたい私は岡崎さんに弟子入り志願をして、放課後農芸の人と共にもの作りの勉強中。
先日は竹箒の作り方を見せて教えていただきました。
そして今日はそんな弟子入り計画第二弾【縄を綯う】
岡崎さんの手つきを見ても全然理解できず、やらないと分からんということでトライ。
やりながら手の動きを教えてもらいました。
藁を手のひらで転がすように合わせていくと意外といい感じに縄になりました。
コツを掴むとリズムよく楽しく進みます。
わたしの綯った縄
岡崎さん曰く、すべては縄から始まる。
昔は家作りにも縄を使っていたそうな。
その家は中で煙を焚いて維持すると100年保つと。
なんか生きてるなあ、とおもいました
岡崎さんが納屋からいろいろ出してきてくれました。
一番左の草履は100年前のもの。真ん中は雪の時履くものだそうです。
蓑はくぐという植物で軽くて水をよくはじきます。縫い目がおしゃれ。
装着。
どれも軽くて体にしっくりきました。そして機能的。
草履は日常で使いたいレベルです。
今日は雨のなか畑作業したので蓑使ってみたかったなあ。
いろんな情報媒体がある今日ですが、人から人へ直に伝えることには力がありますね。
見て聞いて手を動かして体で感じて、縄を綯った感覚と岡崎さんの縄を綯う手の動きが自分の中に濃く残りました。
こうして一人一人の体と感覚を媒体として伝わっていくのが伝統なのでしょうか。
放課後農芸の畑の外での報告でした。
————————————————
記:芸術学部美術科彫刻コース 渡部萌
堆肥隊―堆肥の切換し③―
8月20日17時より、農芸畑にて堆肥の切換しを行いました。
切換しは今回で3回目の作業です。
温度や白カビもいい感じで、ほんのり温かいです。
踏むとふわふわしていて、足が取られる~
最初は枯葉だらけだった土も、もう葉っぱの姿はなくなっていました。
温度や水分、空気、微生物に力を借りて発酵頑張ってたんですね。
良い堆肥へ着々と近づいている予感。
できた堆肥で作った野菜は栄養満点おいしいこと間違いなしです!
夏休みが始まって10日程が経ちましたが、8月も終わりに近づいています。
残暑の中での作業はまだ汗がにじみ出てきましたが、風が気持ちよかったです。
赤とんぼも堆肥の様子を見に来てくれました。
なんだか秋の気配を感じます…
いや、夏は終わっちゃいませんよ!
作業の後には飯塚さんにおいしいスイカをごちそうになりました!
夏はやっぱりコレですよね~
帰り際のお話。
日本では海外で規制されている農薬が何倍も使用されており、ホルモンに影響するということ。ミツバチが減っているということ。
スーパーの野菜には自分の知らない間に想像もつかない程の農薬が使用されているんですね。
自分で野菜を作り、食べられることがどれだけ安心できることかと改めて思いました。
学食のコンポストの方も順調のようです。
いつかこの堆肥で野菜を作れるように!切換し作業はまだ続きます。
――――――――――
記:コミュニティデザイン学科 稲村菜美
シェフが畑にやってきた!
8月・9月の毎週火曜は東北芸術工科大学で放課後農芸「昼ごはんカフェ」
今回は特別ゲストに 群馬のイタリアンレストラン「CENTO(チェント)」の梅山シェフ、
山形の農業生産法人アグリパークZAOの赤松シェフをお招きしての開催です!
畑を一回りして、収穫したばかりの野菜を使って下ごしらえスタート。
 いつもと同じ場所、同じ機材?と思わず疑う調理風景。
いつもと同じ場所、同じ機材?と思わず疑う調理風景。
フライパンのなかの食材の様子は(やっぱり)自分たちで作る時と大違い。
まずはサラダから!
赤松シェフが育てた「プンタレッラ」というタンポポの葉のような野菜に、
柳川先生が前日に釣り上げたキスや、雪の結晶型のパスタ(aGarey)が乗せられています。
そしてパスタが2種類。
夏野菜のトマトペンネ 枝豆のペペロンチーノ
頂きながら作り方、素材の味の引き出し方、最近のイタリアンの潮流など、聞いたことがなかった話がぞくぞく。
 自分たちが育てた野菜の、自分たちの手で引き出せなかった別次元の味を知ってしまいました。
自分たちが育てた野菜の、自分たちの手で引き出せなかった別次元の味を知ってしまいました。
レストランの客席では完成された形だけにしか出会えません。
いつも畑で見て触って食べている食材が、シェフの手にかかると・・・
「野菜って、ここまで美味しさが引き立つんだ!」と新たな発見と、プロの腕前に圧倒されます。
シェフのお2人の姿をみていて、ふと「プロの仕事」について考えてみました。
・限られた環境で最大限の成果をだす方法を瞬時に判断する
・素材をよく観察し、五感、科学的知識、経験から味を引き出す
・専門的知識をもたない人にもわかりやすく伝える
この3つのことが印象に強く、アートやデザインにも通じる大切なことだと思いました。
食の奥深さ、プロの技にわくわくした昼ご飯カフェでした。
梅山シェフ、赤松シェフ、素敵な体験をありがとうございました。
群馬県前橋市下小出町2-54-6
http://www.eurobrezza.co.jp/cento/
山形県上山市高野字家老山3-37
—————————————————
記 ファシリテーター 阪野 正義
堆肥隊 -堆肥の切換し-
8月12日の朝から堆肥の切換し作業を行ってきました。
始めの頃はなかなか温度が上がらず心配していましたが、以前撒いた米糠のおかげか温度は上々。
50度まで上がった堆肥の温度も、昨日の作業時点では30度まで下がっていました。
絶好の切換し日和です!!
前回と同様に堆肥を掘っては返し、掘っては返し……この作業が疲れるんです!!
こうした手間を考えると、農業の高齢化が進んでいる日本で化学肥料が使われてしまうのもわかる気がします。
「農薬反対!」と言うのは簡単ですが、こういった作業を通すことで見えてくるものも有るのだと思いました。
私たちが切換し作業を頑張っているなか、微生物たちも頑張ってくれたようです。
堆肥の中に手を入れてみるととても温かくて、ポカポカしていることがわかります。
以前は見られなかった白カビも見られました。調べてみると白カビの発生は発酵が始まっているというサインのようです。
作業の途中には、畑を管理してくれているであろうおじ様に「これは良い堆肥だ!!」と褒めて頂きました。
小雨が降るなかの作業となってしまいましたが、堆肥作りは今のところ順調と言えるでしょう!
次の切換し作業までに堆肥がどのように変化していくのかが楽しみです!
また、堆肥隊では大学の学生食堂と連携して生ゴミコンポストも作っていきます!
普段は捨てられてしまう生ゴミ。しかし堆肥へと姿を変えることで畑との循環が生まれるのです。
興味のある方はぜひ参加して下さいね!!
ーーーーーーーーーー
記:建築・環境デザイン学科1年 但木美咲
昼ごはんカフェ「カレー」
2014-08-05
大学も夏休みに入りました
チュートリアル放課後農芸では、夏休み期間中の毎週火曜日に
「昼カフェ」と称した”みんなでご飯を作って食べる会”を開いています。
野菜は畑から採れたてのものを、調味料や食器類は持ち寄りで。
おいしく、楽しく活動をしています。
そんな昼ごはんカフェ、第一回は「カレー」です!!
目標は11:30に『いただきます』をすること。
朝09:30に学校の裏の畑に集合して簡易のテント作り。
竹とブルーシートだけでも十分日が避けられるんです。
野菜を畑から採ってきたら、サラダ用にトマトときゅうりを冷水で冷やしておきます。
トマト・きゅうり・茄子・オクラ・ピーマンなどなど、沢山の夏野菜を収穫しました。
他にも、みょうがやしそなどの薬味も収穫。
やっぱり採れたては良い香り!
今回のカレーは二種類。
お米を入れたパエリア風カレーと、ココナッツミルクを入れたタイ風カレーです。
お水は入れずに、野菜の水分だけでつくります。
ガラムマサラやローリエ、クミンを入れてスパイシーに。
辛みは畑で採れたハバネロで!
刻んだ生のハバネロを食べるという強者も…
11:30、予定通りにカレーが完成しました!
サラダはオリーブオイルとクレイジーソルトで味付け。
みんなでテーブルを囲んで、「いただきます!」
ハバネロが思っていたよりも辛く、じわっと汗が吹き出てきます。
お好みでココナッツミルクを足してみたり、二つのカレーを混ぜてみたり。
農芸の授業でお世話になっているお母さんもいらして、
そのお子さんとも一緒にご飯。
たらふく畑の恵みをいただきました。
食後には、岩井さんの淹れたおいしいコーヒーがふるまわれました。
外でのむコーヒーもまた素敵ですね!
玉手さんがお手製のジンジャーエールを持ってきてくれたりと、
自然とおしゃべりも弾みます。
後片付けは、丁寧に。
カレーに使わなかった野菜は、みんなで山分けします。
おいしいご飯が食べられて、何より楽しく、お野菜までもらえるなんて…!!
次回は「そうめん」の予定です。
みょうがとしそが大活躍する予感!
みんなでおいしい時間を過ごしましょう!!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
記:コミュニティデザイン学科1年 奥山直
堆肥隊 ―堆肥のその後―
7月7日に場所を移動しながら切換えし作業を行った堆肥は半年ほど放置しておいたものだったため、雨水を吸ってしまい湿度が多く、その後温度が上がりませんでした。
ということで、リベンジ!
7月29日の夕方めげずに切換えし作業を行いました。
ちなみに切換えし作業とは…
堆肥の有機物の分解してくれるのは好気性菌に分類される微生物。
この好気性菌が代謝するために酸素を好むので、堆肥の天と地をひっくり返す作業をすることで発酵を促します。
さらに、今回は微生物が大好きな米ぬかをサンドイッチ状に挟み込んで確実に温度を上げる作戦です。
実家が農家のメンバーが大量の米糠を持ってきれくれたおかげで順調に作業に取り掛かれました。
夏休み前の試験やレポート期間でしたが、なんのその。
5人でガツガツ堆肥を掘って米糠を振りまいて、掘って振りまいて、掘って振りまいて…。
雨が入らないようにシートをかけてこの日は作業終了です。
3日か4日後に50℃くらいになったら一安心です。
頑張れ微生物!
・
・
・
そして
・
・
3日後の8月1日の夕方確認したところ・・・・


50℃いきましたー!!
がんばったー微生物~!
嬉しすぎて記念写真!
10日後くらいに温度が30℃くらいまで下がってきたら、もう一度切換えし作業をします。
これをあと何回か繰り返して堆肥完成です!
9月蒔きの野菜には間に合ってほしいのですが。。
半年先、一年先、3年先…を想像しての作業。
慣れないけど体に染み込ませていきたいものです。
_________________
記:農芸ファシリテーター 飯塚 咲季
放課後農芸とは
最近の投稿
最近のコメント
- ご報告 〜代表 引き継ぎ〜 に より
- 小麦の収穫! に より
- 堆肥隊、腐葉土つくり に より
アーカイブ
- 2025年5月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年10月
- 2021年7月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月