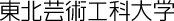<堆肥隊>
4月12日に自然堆肥の切り返し作業を行いました。
天気は晴れ!日差しが暖かく、ようやく山形にも春が来たのだと実感できました。
堆肥を空気に触れさせる為に、ひたすら切り返す作業。
「学年上がりましたね〜」
「新歓どんな感じですか?」
他愛ない会話をしながら楽しい作業です。
前回に引き続きカブトムシの幼虫がこんにちわ(^^)/
「カブトムシの幼虫はバターで炒めて醤油をかけると美味しいらしい」という情報もあり、
ぎりぎりまで悩んでいる人もいましたが結局食べずして終わりました。
(私は始めから勇気がないです)
そして最後に気付いたのは踏む工程を忘れていたこと…。
今からでも大丈夫でしょ!!と前向きに考えてふみふみ、ふみふみ…
切り返し作業を終えれば次は野菜の苗づくりです。
堆肥の箱の中が温床になるので、ポットに種をまいて育ててみようという実験です!
苗を買うより種から育てた方が愛着も持てますし!!
種はトマトの【甘太郎】、カボチャの【かわいいカボチャ】
【飯塚カボチャ】、キュウリの【ときわかぜみどり】です。
堆肥隊でつくった堆肥と鶏糞、畑の土をポットに入れて種をIN。
それぞれが何のポットなのか分かるように、その場に落ちていた竹で
簡単なプレートを作ってみました!
思っていたよりもナイスなできで、手作り感がより愛着を持たせてくれます!!
ポットに種を植えたら場所を移って堆肥の箱へ
芽がでて安定するまでは、毎日の温度管理と水やりが待ってます。
芽が出るのが今から楽しみです!

記:建築・環境デザイン学科 但木美咲
春、畑開き
長い冬の山形にもようやく春が訪れ、心地よい日差しで目覚めます。
生活も、あたらしく動き出す季節、
畑もいよいよしごとはじめ。
昨日は春菊、赤シソ、かぼちゃの種を蒔きました。
大学裏の畑の、道路に面した小さなスペースです。ときには通りすがる人と立ち話も。
作業の途中、ハイキングのご一行に気持ちのよい挨拶をかけてもらいました。
春のあたたかさに、心も開いていきます。
お天気の勢いにのって、落ち葉堆肥の切り返し作業もしました。
秋に拾い集めた落ち葉も、一部堆肥が完成していました。
分解され、細かく、さらさらに!感動です。
さらに、堆肥箱の中にカブトムシの幼虫を発見。あまりの大きさにびっくりしてしまいました。
落ち葉の栄養で育ったぷりぷりの赤ちゃん、堆肥の中にそっと戻しました。
堆肥隊の活動も継続していきますのでお楽しみに。
記:美術科テキスタイルコース 玉手りか
堆肥隊《ポスター》
現在活動中の堆肥隊・生ごみコンポストのポスターが、学食一階食券機付近に掲示されています。
食券機の近くということもあり、友達や先生からも「ポスター見たよ〜!」
とのお声をかけて頂き、嬉しい限りです!
各メンバーの個性が表れた素敵なポスターとなっており、
この一枚を通して多くの人たちに興味を持ってもらえたら嬉しいです。
雪の影響から年末年始は活動を一時中断していましたが、
段々と雪も溶け始め「そろそろ再始動を!」と思っています。
突然ですが、小さじ一杯の土の中にどれくらい多くの微生物が住んでいると思いますか?
場所や環境にもよるのでしょうが、一億くらいと言われているのです。
土中には計り知れないくらい多くの微生物がすんでいるのですね。
私たちが休んでいる間にも、コンポストの世界の微生物たちは冬の間も必死に生きているんだな。
そう思うと春休みだからといってだらけていたらいけないという気持ちになってきます…。
冬が来れば春はま近い。桜は静かにその春を待つ。
かつて経営の神様と言われた松下幸之助はこのように話したそうです。
春はいつ山形へやってくるのでしょうか
私も静かに春を待とうと思います
堆肥隊《穴堀り》
夏休み前から計画していた堆肥隊の生ごみコンポスト。
日本の農業でみられた畑・人・食物の繋がりを放課後農芸でもできるのではないかと思い始まりました。
生ごみコンポストを制作するにあたり、私たちは2つの方法を考えました。
一つはコンポスト用の容器に野菜くずを重ねていく方法。もう一つは直接地面に穴を掘る方法です。
今日は大学裏の畑に朝8時集合。
そして下準備としての穴掘り作業を行いました!
先ずは場所の確保として、
草刈り&芋掘りをしました~
とても大きなさつまいもを収穫!
秋の味覚GETです(^^)!
そして穴堀り開始です!
「一人一つ穴を掘ろうか~」
「勝負しましょうよ!」
「掘った穴に名前付けていいですか!?」
なんて和気藹々と始まった穴堀り。
だがしかし!
大学裏の畑は石が多く、しかも大きい!
掘っても掘っても中々進みませんでした…
途中でいちじくを収穫しに行く少女。
泥にはまる青年。
皆に恋愛相談しだす少女……
大変な作業ですが、皆とおしゃべりしながらの穴堀りはとても楽しめました!
そして!
結果的に!!
今日一日では終わりませんでした!!
堆肥隊の皆さん。
私たちの穴堀りはまだ終わりませんよ!
ちなみに今日の成果はこの通りです~
野菜くずを利用した生ごみコンポストが成功するためにも、これから話し合いと検討を重ねてより良いものを作っていきます!
建築・環境デザイン学科
1年 但木美咲
堆肥隊―堆肥の切換し③―
8月20日17時より、農芸畑にて堆肥の切換しを行いました。
切換しは今回で3回目の作業です。
温度や白カビもいい感じで、ほんのり温かいです。
踏むとふわふわしていて、足が取られる~
最初は枯葉だらけだった土も、もう葉っぱの姿はなくなっていました。
温度や水分、空気、微生物に力を借りて発酵頑張ってたんですね。
良い堆肥へ着々と近づいている予感。
できた堆肥で作った野菜は栄養満点おいしいこと間違いなしです!
夏休みが始まって10日程が経ちましたが、8月も終わりに近づいています。
残暑の中での作業はまだ汗がにじみ出てきましたが、風が気持ちよかったです。
赤とんぼも堆肥の様子を見に来てくれました。
なんだか秋の気配を感じます…
いや、夏は終わっちゃいませんよ!
作業の後には飯塚さんにおいしいスイカをごちそうになりました!
夏はやっぱりコレですよね~
帰り際のお話。
日本では海外で規制されている農薬が何倍も使用されており、ホルモンに影響するということ。ミツバチが減っているということ。
スーパーの野菜には自分の知らない間に想像もつかない程の農薬が使用されているんですね。
自分で野菜を作り、食べられることがどれだけ安心できることかと改めて思いました。
学食のコンポストの方も順調のようです。
いつかこの堆肥で野菜を作れるように!切換し作業はまだ続きます。
――――――――――
記:コミュニティデザイン学科 稲村菜美
堆肥隊 -堆肥の切換し-
8月12日の朝から堆肥の切換し作業を行ってきました。
始めの頃はなかなか温度が上がらず心配していましたが、以前撒いた米糠のおかげか温度は上々。
50度まで上がった堆肥の温度も、昨日の作業時点では30度まで下がっていました。
絶好の切換し日和です!!
前回と同様に堆肥を掘っては返し、掘っては返し……この作業が疲れるんです!!
こうした手間を考えると、農業の高齢化が進んでいる日本で化学肥料が使われてしまうのもわかる気がします。
「農薬反対!」と言うのは簡単ですが、こういった作業を通すことで見えてくるものも有るのだと思いました。
私たちが切換し作業を頑張っているなか、微生物たちも頑張ってくれたようです。
堆肥の中に手を入れてみるととても温かくて、ポカポカしていることがわかります。
以前は見られなかった白カビも見られました。調べてみると白カビの発生は発酵が始まっているというサインのようです。
作業の途中には、畑を管理してくれているであろうおじ様に「これは良い堆肥だ!!」と褒めて頂きました。
小雨が降るなかの作業となってしまいましたが、堆肥作りは今のところ順調と言えるでしょう!
次の切換し作業までに堆肥がどのように変化していくのかが楽しみです!
また、堆肥隊では大学の学生食堂と連携して生ゴミコンポストも作っていきます!
普段は捨てられてしまう生ゴミ。しかし堆肥へと姿を変えることで畑との循環が生まれるのです。
興味のある方はぜひ参加して下さいね!!
ーーーーーーーーーー
記:建築・環境デザイン学科1年 但木美咲
堆肥隊 ―堆肥のその後―
7月7日に場所を移動しながら切換えし作業を行った堆肥は半年ほど放置しておいたものだったため、雨水を吸ってしまい湿度が多く、その後温度が上がりませんでした。
ということで、リベンジ!
7月29日の夕方めげずに切換えし作業を行いました。
ちなみに切換えし作業とは…
堆肥の有機物の分解してくれるのは好気性菌に分類される微生物。
この好気性菌が代謝するために酸素を好むので、堆肥の天と地をひっくり返す作業をすることで発酵を促します。
さらに、今回は微生物が大好きな米ぬかをサンドイッチ状に挟み込んで確実に温度を上げる作戦です。
実家が農家のメンバーが大量の米糠を持ってきれくれたおかげで順調に作業に取り掛かれました。
夏休み前の試験やレポート期間でしたが、なんのその。
5人でガツガツ堆肥を掘って米糠を振りまいて、掘って振りまいて、掘って振りまいて…。
雨が入らないようにシートをかけてこの日は作業終了です。
3日か4日後に50℃くらいになったら一安心です。
頑張れ微生物!
・
・
・
そして
・
・
3日後の8月1日の夕方確認したところ・・・・


50℃いきましたー!!
がんばったー微生物~!
嬉しすぎて記念写真!
10日後くらいに温度が30℃くらいまで下がってきたら、もう一度切換えし作業をします。
これをあと何回か繰り返して堆肥完成です!
9月蒔きの野菜には間に合ってほしいのですが。。
半年先、一年先、3年先…を想像しての作業。
慣れないけど体に染み込ませていきたいものです。
_________________
記:農芸ファシリテーター 飯塚 咲季
堆肥隊 活動開始!
自然堆肥を作りたい。
大学の授業なんだから化学肥料を買ってきて使うのでは勉強にならない。
ここにある素材、例えば学食の生ごみなどで堆肥を作って畑と大学で循環を作りたい。
授業農芸でこう言った子がいました。

しかしながら、4月に入学した1年生が4月から始まる授業で使う堆肥を作るには間に合いません。
現在授業では完熟たい肥を元肥に、部分的に化成肥料を、さらに追肥でまた化成肥料使用しているのが現状です。
収量が確実に確保できて、すくすく順調に育つ化成肥料。収穫の喜びは野菜がたくさん実った方が皆で分け合えるし良いかもしれません。
でも…授業農芸の理念にはこう書いてあります。(冒頭一部抜粋)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なぜいま東北芸術工科大学は「土を耕す」のか。
自然との対話を通して、自然の摂理を知り、
人間中心主義の驕りから覚醒するためである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私個人の考えとしては化成肥料の存在は人間中心主義の驕りの塊ではないかと…思っているのです。
慣行農法がいいのか、有機農業がいいのか、という議論自体は重要ではありません。
「自然との対話を通して、自然の摂理を知ること」「これまでの”当たり前”に疑問を持ち、それを問いかけにすること。」
が大切なんじゃないかなぁと思っています。
クリエイティブな大学にいる私たちは、ここで得た技術で人々を戦争に駆り立てるCMだって作れる、人の欲望を駆り立ててどんどん新しい製品を大量生産する。でも、その裏側で人が死んでいく。いらなくなった先では土に還れないモノばかり。
疑問をもたなければ、私たちはこのシステムに組み込まれていくだけです。
アートやデザイン自体には善も悪、希望も絶望もない。どう使うかは私たちの心に掛かっています。
おもいっきり話がそれましたが、
それならばと、授業外の放課後農芸で堆肥を作ろう!となったのです。
堆肥、生ごみコンポスト、緑肥、いろいろ勉強していきたいと思います。
たくましいメンバー達!!10名程で楽しく勉強していきます。

今は”常識”に対して疑問を持ち、実行している段階です。
もう一歩先、”疑問”を”問いかけ”にしていけたらと思います。
____________
記:農芸ファシリテーター 飯塚 咲季
放課後農芸とは
最近の投稿
最近のコメント
- ご報告 〜代表 引き継ぎ〜 に より
- 小麦の収穫! に より
- 堆肥隊、腐葉土つくり に より
アーカイブ
- 2025年5月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年10月
- 2021年7月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月